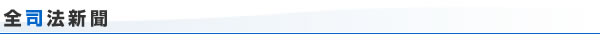 |
| |
|
�J���g�����߂���ω����`�����X�ɕς��āA
�v���Ƒg�D��O�i�����悤�I
��Q��S�����L����c |
|
| |

�n�A�E�x�����L�����I�����C���ŎQ��
�@4��20���A2024�N�x��2��S�����L����c���I�����C���ŊJ�Â��܂����B��c�ł́A5�`6���̍ō��ٌ��ŗv���O�i��ڎw��2025�N���v���ѓO�������j�̈ӎv������s���ƂƂ��ɁA7���̒�����ɂނ��đg�D�����E�g��ɂƂ肭�ވӎv������͂���܂����B
 |
| �����㏑�L�� |
�E��̗v�����ō��ٌ��ɏW�������邱�Ƃ��d�v
�@�J������Œ���ψ����́A�ō��ق��������߂�����Łu���̍���������������ؔ����Ă���v�Əq�ׂĂ��邱�ƂɐG��āA���̐Ŏ��͉ߋ��ő�ɂ��ւ�炸�A�h�q�\�Z���c��オ���Ă��邽�߂ɁA�Љ�ۏ�������A�K�v�Ȏ{���{�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝw�E���������Łu�S�i�@�́w���̍�������������x����E��̐l�����炳��Ă��d���Ȃ��Ƃ͍l���Ȃ��v�Əq�ׁA������ĉ^�����邱�Ƃ�A�����J�A�E�S�J�A�Ɍ��W���Đ���������K�v����������܂����B
�@�܂��A�g����̈��グ���܂߂��g�D�ƍ����̋c�_�ɂ��āu���c�����́A�����܂ŗ\�����c���n�߂�ɂ������Ă̖{���̍l�����i���ӎ��j���������́v�Əq�ׁA�g�D�Ɖ^�����ێ��E�O�i�����闧��ł̌��ݓI�ȋc�_�����߂܂����B
�@��㏑�L���͏��v���ѓO�������u�v���̏o���_�v�ƈʒu�Â��A�E��̗v�����ō��ٌ��ɏW�������邱�Ƃ��d�v���Əq�ׂāA�ō��ق��ėv�����A�E����ԕA�S������v�����̒�o�Ȃǂ̂Ƃ肭�݂ƂƂ��ɁA�v���O�i��ڎw���u��p�v�Ƃ���7��11���ɑ������ԊO�E����ƈ��������S1���̑S������v���[�g�s����z�u���Ă��邱�Ƃ���܂����B���̂����ŁA�l���A�J�����ԒZ�k�E���Ώk�����A�E���̌��N�Ǘ��E���S�m�ۓ��A�f�W�^�����ւ̑Ή��A�E�����x�Ɋւ���v���A�x�ɁE�x�ƁE������琬�x�����̏d�_�v�����ꂼ��ɂ��āA���ɗՂރ|�C���g��������܂����B
�@�܂��A���ґg�D������4��1����2���ɑS���łƂ肭�V�̗p�E���̃t�@�[�X�g�A�^�b�N�����������Łu���������̓t�@�[�X�g�A�^�b�N�ł͂Ȃ��A�p���I�ȂƂ肭�݂�A�V�̗p�ȊO�̖������҂�����ɂ��ꂽ�����������d�v�ɂȂ�v�ƕ��A�g�����������͑g�D�ƍ����̗\�����c�ɂ��āA���߂ă|�C���g���m�F���܂����B
�Ζ����ԊǗ��A�S������̎����v�̂Ȃǂœ��c
�@��c�ɎQ�������n�A�E�x���̏��L������́A�t�����̑����Ɋւ���āA�x�����ŗl�X�ȗv����O�i�������o���A�S�i�@��^���̊X����`�s���A�g�������̌����鉻���ӎ����Ē��r���ɂƂ肭�o���Ȃǂ�����܂����B�Ƃ�킯�A4�����Ɍ������ꂽ�������S���ɑ������邱�Ƃ�����A�u�������݂̂Ŕ��f���Ă���v�u�E����Ԃ������A�㋉�����狁�߂��Č������Ă���Ƃ����l�����Ȃ��v�u�ƍق͈��̎蓖�Ă����ꂽ���A���ꑫ��Ȃ��v���̔���������܂����B
�@���v�����ɑO�i��ڎw���ׂ��v���ɂ��ẮA���Ύ��Ԃ̔c���ɂ��āu���O�\�����`�[�����Ă���v�Ƃ̎w�E������A�q�ϓI�f�[�^�ɂ��ƂÂ��Ζ����ԊǗ��̕K�v�����c�_�����ƂƂ��ɁA�����̊ȑf���E�������Ɋւ���āu�S������̎����v�̂��ō��ق̐ӔC�Ő������ׂ����v���̈ӌ����o����܂����B�܂��A�ٔ����̐E���ɑ���p���n���ɂ��ĕ����̔���������A�u���Z���ɂ߂钆�ŁA���L���ɑ��Ė��̂���ڂ���������ٔ�������������ۂ�����v�Ƃ̎��Ԃ�����܂����B���̑��A��C�������̏��i���P�A�E�F�u�٘_�̉^�p�A�f�W�^�����̂��Ƃł̏�L�A�|�[�^���T�C�g�̌����@�\�̉��P�A�n���ł̓^�N�V�[�𗘗p���邱�Ƃ�����Ȃ��Ă�����ԂȂǂɂ��Ĕ���������܂����B
�t�@�[�X�g�A�^�b�N�Ɏ��g�x���Ő���
�@�g�D�g��ł́A�V�̗p�E���̉����ɂ��ē����n�فA���A�L���A�����Ȃǂ̍��ُ��ݒn���͂��߁A�t�@�[�X�g�A�^�b�N���ӎ����ĂƂ肭�x���Ō��ʂɌ��т���������A���̑O��Ƃ��āA���O�̈ӎv����̏d�v���A�}���鑤�̃}�C���h��ς��邱�ƁA���M�������ē��������邱�Ƃ���������܂����B�܂��A�u�V�̗p�̕��͋C���ς���Ă��āA�J���g���̘b���悭�����Ă����v�Ƃ��������G���o����܂����B���킹�āA����̉����҂ɑ���t�H���[��A������u��̖�A�O�̖�v�̂Ƃ肭�݂̏d�v�����m�F����܂����B
�@�g����̈��グ���܂ޑg�D�ƍ����̗\�����c�̒��ԕł́u�g�D�g��Ƒg����̈��グ�͗��������Ȃ��v�u�E�ގ҂�������̂ł͂Ȃ����v�u�g�������甽�̐����o����Ă���v�Ȃǂ̗��R���甽�Έӌ����o��������ŁA�u���J�ɐ����������ʁA���グ�͂�ނȂ��Ƃ����������������v�Ƃ̈ӌ�������A�܂��A�u���グ�̗��R�ɂ��v�u��̓I�ȋ��z�ɂ��v�u�{�����l�X�ȓw�͂����ė~�����v�Ƃ���������������܂����B
�E��́w���x��b�������A�S�i�@���E��ʼnʂ����������L���悤
�@��c�̂܂Ƃ߂ŁA��㏑�L���́u���_��ʂ��ĐE��̉ۑ肪��������ɂȂ����v�Əq�ׂāA�ō��ٌ��ň�ł������̗v���O�i����������Ă������ӂ��q�ׂ�ƂƂ��ɁA�u�w�E�ꑍ�_���E�v���g�D�^���x�ŐE��́w���x��b���������Ƃ�S�Ă̎x���Ŏ��H���A�w�E��̃��[���x�����S�i�@�̖�����S���ōL���Ă������v�Əq�ׂ܂����B
�@�܂��A�g�D�����E�g��ɂ��āu2024�N1���̒����ψ���ŘJ���g���w�����̃`�����X�x���K��Ă���Ǝw�E���A���N8���̒�����ł͐V�̗p�E���̃t�@�[�X�g�A�^�b�N�ɑS�Ă̎x���łƂ肭�ނ��Ƃ��N���Ă����B������������̒��ŁA�{�N4�����͂���܂ŐV�̗p�E���̉����g��ɋ�킵���x���ő����̐V�̗p�E�����������錋�ʂ��o�Ă���B���ꂪ�ς�����Ɗ����Ă���A���������ω����`�����X�ɕς��Ă������v�Əq�ׂ܂����B
�@�g�D�ƍ����̗\�����c�ɂ��Ắu�o���ꂽ�ӌ��͑S�Ď~�߂Č����������v�Əq�ׂ������ŁA����A4�����̊e�n�A�E�x������̓��c���ʂ̕A���N�x�̍����̎��s�A�{�����ł���x�o�팸�̍H�v�Ȃǂ܂��đ��c�Ă���������Əq�ׁA�u6�����_�̑g���������ő�̃|�C���g�ƂȂ邱�Ƃ���A���БS���őg�����g��������߂Ă��炢�����v�Ɖ��߂đi���܂����B
|
| |
 |
| |
|
����@������@�ɗv���O�i
�o�����̃^�N�V�[���p���_��� |
|
| |
|
�@�S�i�@�ł́A�ƍْ������̏o���Ȃǂ�O���ɁA�^�N�V�[���p���_��ɔF�߂�悤�v�����Ă��܂������A����@���������ꂽ���Ƃ��āA�ٔ����ł��^�N�V�[���p�̏_����}���邱�ƂɂȂ�܂����B���N�̗v�����O�i�������ƂɂȂ�܂��B�ō��ق́A���̎�|�����m���邽�߂ɁA4��21���t�ʼn����قɑ��鎖���A���o���Ă��܂��B
�@�������A���ɂ́A�^�N�V�[�𗘗p���邱�Ƃ��ł���ꍇ�ɂ��āA
�@�@�����̌�ʋ@�ւ��Ȃ����͉^�s�{�������������Ȃ��k���ɂ��ړ�������ȏꍇ
�A�@�p���ً̋}���⎞�ԓI�Ȑ���ɂ��^�N�V�[���ȊO�̌����̌�ʋ@�ւɂ��ړ��ł͗p���Ɏx��𗈂��ꍇ
�B�@�p���̖ړI�E���e����^�N�V�[���𗘗p���邱�Ƃ������I�ł���ꍇ
�@��3�������āA�u�����3�̏ꍇ�̂����ꂩ�ɊY������Ɣ��f����A�^�N�V�[�𗘗p���č��x���Ȃ��A�}���I�ɉ^�p����K�v�͂���܂���B�K���v���Ȏ����������̂��߂ɕK�v�ȏꍇ�ɂ́A�K�Ƀ^�N�V�[�����p�����悤�ɂ��Ă��������v�Ɩ��L����Ă��܂��B
�@�܂��A���J�⍓���Ƃ������C�ۏ����̏ꍇ�A�d���ו��������Ă����K�v������ꍇ�A�댯�Ȗ쐶�����Ƒ�������\��������悤�ȓ��H�Ȃǂ̋�̗�������āA�^�N�V�[���p�������ł���Ƃ��Ă��܂��B
|
| |
 |
| |
|
| �]�ƈ��̑�����S�g��������J�X�n���@�d�v |
|
| |
 |
�u�t�̒Ð썄����
�i�S�J�����L���j |
�@�S�i�@�{����4��24���A�S�J���ȘJ���g�����L���̒Ð썄������u�t�ɂ��������A�J�X�^�}�[�n���X�����g��w�K����I�����C���ŊJ�Â��܂����B
�J�X�n���Ƃ͉����A�ǂ��Ή�����̂�
�@�Ð삳��͍ŏ��ɁA2017�`8�N���Ɍ��J�Ȃ��p���n���̌������s�����Łu�ڋq�����悩��̒��������f�s�ׁv�����ƂȂ��ăJ�X�n����̌������n�܂������Ƃ�������N�����A���N��4���ɘJ���{���������i�@�����Ă�����ɒ�o���ꂽ�o�߂Ɏ���܂ł�������܂����B�܂��A���̔w�i�ɂ́A�t�`�[���Z���ȂǘJ���g���̂Ƃ肭�݂�����A��ƂƘJ���g�����A���ő����j�����肷��Ȃǂ̓��������邱�Ƃ��Љ��܂����B
�@�����āA�J�X�n���̒�`�ɂ��Č��J�Ȃ����Ԋ�ƂɎ����Ă���}�j���A���ł́u�ڋq������̃N���[���E�����̂����A���Y�N���[���E�����̗v���̓��e�̑Ó����ɏƂ炵�āA���Y�v�����������邽�߂̎�i�E�l�Ԃ��Љ�ʔO��s�����Ȃ��̂ł����āA���Y��i�E�l�Ԃɂ��A�J���҂̏A�Ɗ����Q�������́v�Ƃ���Ă�����̂́A��Ƃ�ƊE�ɂ���ĈႢ������Ƃ��������ӎ��������ꂽ�����ŁA�u���f�s�ׂ�̌�������A�Q�s�����������A�S�Ó��ȓ��ɍs�����Ƃ����A���P�[�g���ʂ�����B�J�X�n���͏]�ƈ��̑�����S�g�������A���N��Q��ސE�ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��Ƃ������Ƃ��d�����ĂƂ肭�݂������߂�K�v������v�Əq�ׂ��܂����B
���J�Ȃ̐E���������w�v�j�x�����肵�A��������
�@�܂��A�S�J���Ƃ̌��Ȃǂ��o�Č��J�Ȃ��s���Ă���J�X�n����ł́A�w�Ǐ����̐E���y�ї����ɂ̈��S�m�ۑ��v�j�x�����肳��A�������肳��Ă���Ƃ̂��ƂŁA�u�����E��̋��X�܂Œ蒅�����Ă������Ƃ��ۑ�ɂȂ��Ă���B�ŋ߂ł́A�r�m�r���ł̔�排����ւ̑Ή����ۑ�v�Əq�ׂ��܂����B
�@�܂��A�Q���҂̎���ɓ����āA���J�Ȃɂ�����d�b�ł̃J�X�n����ɂ��āu�d�b�͂قƂ�ǂ��i���o�[�f�B�X�v���C�ɂȂ��Ă�����̂́A�^���@�\�����Ă�����̂͗\�Z�̊W�������Ĕ������x�B����A�O�����璅�M���������ꍇ�A�܂��̓R�[���Z���^�[���ĒS�������ɐU�蕪����悤�ɂȂ��Ă���A�R�[���Z���^�[�œd�b�����ۂɂ́w���̉�b�͘^�����邱�Ƃ�����܂��x�ƃA�i�E���X�𗬂����ƂŁA�}�~���ʂɂȂ����Ă���v�Əq�ׂ��܂����B
�J�X�n����̋�̓I�Ƃ肭��
�i�����J���ȁw�J�X�^�}�[�n���X�����g���ƃ}�j���A���x���j
�J�X�n����z�肵�����O�̏���
1�j��{���j�E��{�p���̖��m���Ǝ��m�E�[��
�@���@�g�D�̃g�b�v���J�X�n����Ɍ�������{�p���E��{���j�m�Ɏ����B
�@���@�g�D�Ƃ��ăJ�X�n������]�ƈ������Ƃ�����{�p���E��{���j��
�@�@��̓I�ȂƂ肭�݁E�Ή����]�ƈ��Ɏ��m�E�[������B
2�j�]�ƈ��i��Q�ҁj�̂��߂̑��k�̐��̐���
�@���@�J�X�n�������]�ƈ������k�ł���悤���k�Ή��҂����߂Ă����A
�@�@�܂��͑��k������ݒu���A�]�ƈ��ɍL�����m����B
3�j�Ή����@�A�菇�̍���
�@���@�J�X�n���s�ׂւ̑Ή��̐�����@�Ȃǂ����炩���ߌ��߂Ă����B
4�j�Г��Ή����[���̏]�ƈ��ւ̋���E���C
�@���@�ڋq������̖��f�s�ׁA�����ȃN���[���ւ̋�̓I�Ή��ɂ��āA����E���C���s���B
�J�X�n�������ۂɋN�������ۂ̑Ή�
1�j�����W�̐��m�Ȋm�F�Ǝ��Ăւ̑Ή�
�@���@�J�X�n���ɊY�����邩�ۂ��f���邽�߁A�ڋq��]�ƈ�������̏������ƂɁA
�@�@���̍s�ׂ������ł��邩���m�F����B
�@���@�m�F���������Ɋ�Â��A���i�����r������A�܂��̓T�[�r�X�ɉߎ�������ꍇ�͎Ӎ߂��A
�@�@���i�̌������s���Ȃǂ̑Ή���}��B���r��ߎ��������ꍇ�ɂ͗v���ɉ����Ȃ��B
2�j�]�ƈ��ւ̔z���̑[�u
�@���@��Q�����]�ƈ��ւ̔z���̑[�u���s��
�@�@�i��l�őΉ��������A�������őg�D�I�ɑΉ�����B�����^���s���ւ̑Ή��Ȃǂ��s���j
3�j�Ĕ��h�~�̂��߂̂Ƃ肭��
�@���@���l�̖�肪�������邱�Ƃ�h�����߁A�Ή��̌���������P���s���ƂƂ��ɁA
�@�@�J�X�n������p���I�Ɏ��{����B
|
| |
 |
| |
|
| �m���ɐ��͓͂��Ă����@�T�d�R�c�g���̗� |
|
| |
| |
 |
�c���v�����I����
����c�����i�Q�c�@�j�O�ɂ� |
�@4��10���A�ٔ����E������@�����Ă̐R�c���Q�c�@�@���ψ���ōs���A���͂����T�����܂����B
�@�ٔ����̐l���́u�ٔ����E������@�v�Ƃ����@���ɂ��ƂÂ��Č��߂��܂��B����́u�����v�ẮA�ٔ����̒����47������������e�ł��邽�߁A�S�i�@�͂���ɔ����A3��6���A�O�E�Q���@�̖@���ψ��S���ɑ��ĐT�d�R�c�����߂�v���s�������{���܂������A���̐��ʂ����̖ڂŊm���߂邽�߂ɖT���ɍs���܂����B�Ȃ��A�O�c�@�̐R�c��3��14���ɍs���Ă���A���͂�������T�����Ă��܂��B
�@�ψ���ł́u�l������Ό���͉��Ȃ��v�u�ƍق͂���ɑ��Z�ɂȂ�v�Ƃ������c�_�����킳��A����̎��Ԃɑ������R�c���Ȃ���܂����B
�@�c���̔����̑����́A���������v���s����ʂ��Ĕ鏑��c���ɒ��ړ`�������ɂ��ƂÂ����̂ł����B�g���̍s�����m���ɍ�������Ă���Ǝ������܂����B���ɂ́u�ٔ����͗\�Z�����̂����肾�v�Ƃ̎w�E������܂����B�����炱���A�������̌���̐����A�\�Z�����̍����Ƃ��ĕK�v�Ȃ̂��ƍĔF�����܂����B
�@�@�Ă͉��E�������Ă��܂��܂������A����c���̑����́A�ٔ����̌���ɑ��闝����[�߁A�����̕K�v����^���ʂ���~�߂悤�Ƃ��Ă���p���������邱�Ƃ��ł��܂����B
���ЁA�����̖ڂŊm���߂Ăق���
�@�R�c�̗l�q�̓I�����C���ł������\�ŁA�A�[�J�C�u������܂��̂ŁA���Ј�x�A���Ă݂Ă��������i���O�c�@�A�Q�c�@�̂g�o�Ƀ����N������܂��j�B
�@�����A���ۂɂ��̏�ɑ����^�ԂƁA����ْ̋����A����l�߂���C�Ŋ����邱�Ƃ��ł��܂����B���p�ł͖��킦�Ȃ����̂��A����ɂ͂���u�s���Ă悩�����v�ƐS����v���܂����B��C���ƋL���Ɏc��̌��ł��B
�@�u�E��̎��Ԃ�`����v�\�\����͖{�����ł��A����c���ւ̗v���ł��ς��܂���B�����������X����Ă��邱�Ƃ́A���������ƂȂ̂ł��B
�@�c�����A���������A����̐����W�߁A����𐭍�ɔ��f�����悤�Ƃ��Ă��܂��B���̖�����S���Ă��邱�ƂɁA�ւ�������Ăق����Ǝv���܂��B
�@�T���Ƃ����o����ʂ��āA�u���͓͂��v�Ƃ����m�M�܂����B���̎������A�����̒��ԂƋ��L�������Ƌ��������Ă��܂��B
|