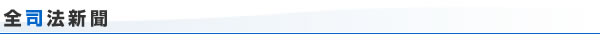 |
| |
|
2025年・新年のごあいさつ
「声をあげる」「声をかけあう」ことを今年の抱負に
中央執行委員長 中矢正晴 |
|
| |
|
若い人たちと話をするのが好きなので、そういう機会を与えていただけるととてもありがたい思いで参加しています。
しばらく話をしていると、小さな問題(だと本人が思っているケースも含めて)でも、職場で理不尽を感じた経験を話してくれることがあります。本人のことだけでなく、同期や同僚、同世代の人の話になると、さらに多くの経験を聞くことができます。
そんな時は「改めて労働組合にきちんと相談してみようよ」と声をかけます。理不尽なことを変えるのは無理だとは思わないし、今はまだ無理でも、いつか変えられる時がくると信じているからです。そんな時、裁判所に全司法があって良かったと思います。「使えるツール」があると自信を持って伝えられるからです。
理不尽なことは、我慢して、あるいは見ないふりをして、黙ってやり過ごしたように思っていても、心の深い部分に残っていきます。そして、職場は本質的に理不尽と隣り合せの場所です。今いる職場が上司や同僚に恵まれ、理不尽を感じにくい部署であったとしても、次に異動になった先も同じかどうかはわかりません。
だから、職場で理不尽なものに出会った時に「声をあげられる」ように、私たちの先輩は全司法を作りました。声をあげなければ変わらないし、声をあげれば変えられる、これまでの長い運動の積み重ねがそれを証明しています。
そのことは、社会全体のことであったり、仕事や生活に深く関わってくる政治のことでも同じです。声をあげれば必ず変わるし、変えられるのです。
そうは言っても「声をあげる」のは勇気が必要だったり、やっぱり面倒だったりします。気軽に「声をあげる」ことができるようにする必要があり、それは日常的にお互いに声をかけあうことではないかと思っています。
これから始まる2025年春闘は「声をかけあう春闘」を全司法のスローガンにしました。年始にあたって、組合員みなさんと確認し合う今年の抱負も「声をあげる」「声をかけあう」ことにしたいと思います。
|
| |
 |
| |
|
北と南から、支部の活動を紹介します
鹿児島支部・釧路支部 |
|
| |
 |
 |
| 鹿児島支部 |
釧路支部 |
アットホームな組合員同士の絆
釧路支部の特徴は、日本一の広大な管轄面積を感じさせないほどのアットホームな組合員同士の絆。支部のみならず分会や青年部での教宣紙の発行や今期は東日本最速の支部定期大会開催など、支部や分会、青年部が協力し合い、庁を超えた一体感のある活動を展開しています。
さらに、釧路支部役員の半数以上が30代以下という点も特筆すべきポイントで、若手とベテランが互いに刺激を与え合いながら活動を盛り上げています。今年4月に加入した2名の青年も、早速それぞれ分会役員と青年部役員として活躍し、支部に新たな風を吹き込んでいます。
コテージを貸し切って夜中まで盛り上がった青年部旅行会、お花見、キャンプ、一泊二日で行った学習会とその後の懇親会でのビンゴ大会、青年部組合員との鍋パーティー、組合員のお子さんとのぬいぐるみ遊び、豪華景品を用意して騒ぎ合った青年部のクリスマスパーティーなど、挙げればキリがないほど、組合員の記憶に残る活動を釧路支部ではたくさん行っています。
LINEオープンチャットで交流
鹿児島は、管内に支部、独簡等あわせて15か所を所管していて、日本一多くの支部等を抱えています。うち5か所は離島であり、組合員は県内各地に広く散らばっています。
そのような状況でも旗開きやクリスマスパーティーなどのイベントの参集率は高くなっています。このことに一役買っているのが、LINEのオープンチャット、題して『きばっど!鹿児島』です。各種イベントのお知らせや本部からの情報、要求実現の速報、組合員からの疑問点の投稿など、組合員への情報伝達ツールにとどまらず、組合員同士の交流の場になっています。
また、本部主催のオンライン会議に、複数人で集まって参加することが多く、これが界隈では『鹿児島スタイル』と呼ばれているとかいないとか…。とにかく、みんなで集まる!ことを大切に活動しています。
今回の特集号記事を書いてくれたのは、主に青年部員たちです。離れた場所にいても、組合活動に参加してくれるのはとてもうれしく、そして頼もしく感じています。
|
| |
 |
| |
|
ノーベル賞は核兵器廃絶を願って運動してきた
「日本国民への表彰状」
岡久郁子さんインタビュー |
|
| |
昨年、日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)がノーベル平和賞を受賞したことが話題となりました。折しも、2025年は被爆80周年にあたります。
そんな節目の年頭にあたって、全司法中国地連・広島支部等で長年活動され、現在は第2次「黒い雨」訴訟の原告団長として活動されている岡久郁子さん(2001年退職)にお話をお聞きしました。
夏は特にしんどかった職場の被爆者たち
振り返れば、原水爆禁止世界大会に初めて参加してから、50年にわたって核兵器廃絶、被爆者救援の活動に参加してきました。こうして運動を続けることができたのは、全司法が毎年の運動方針にそって誠実に活動をすすめていたからです。
かつては、裁判所の職場にも被爆者の方がたくさんおられ、夏が近づくと、しんどさが増すような状況がありました。いわゆる「原爆ぶらぶら病」と思われる人(在職中に前立腺ガンで死亡。家族に被爆の事実を隠していたという)、顔や手にケロイドを残していた女性(在職中に大腸ガンで死亡)、元気で退職したものの間もなく入院、死亡された方もおられます。
被爆体験を世界に伝え、次の世代に繋ぐ活動
1982年6月の第2回国連軍縮特別総会(SSDII)に被爆者の広末正司さん(書記官)を派遣。1988年5月のSSDIIIにも土井悦爾さん(事務官)を派遣しました。土井さんは原爆で下敷きになり、自分は自力で外に出て、通りがかりの兵隊を呼び止め母を助け出した体験をお持ちでした。職場では、国連への署名とカンパ活動が旺盛にとりくまれました。
その頃から、広島支部は毎年、被爆した組合員の証言を聴く会を開き、若い人に被爆体験の継承をはかってきました。また、国公労連婦人部が広島で全国集会を開いたときには、平和公園の碑をスライドにして上映し、被爆体験集を発行・配布しました。
1986年には国連の調査活動に協力して、組合員460名のうち、被爆組合員40名、家族に被爆者のいる人34名がアンケートに答えました。すでに41年が経っていましたが、まだ、「救護被爆者」「黒い雨被爆者」などは知られていない時期でした。
平和行進には、県内各地での行進とともに昼休みの平和行進もあり、延べ88人が参加したことがあります。これは私の記憶にある一番大勢が参加した行進でした。
原爆投下は過ちだったと認めさせたい~被爆者の願い
仕事では、原爆の裁判で速記官として法廷に立会し、勇気を持って国の被爆行政に立ち向かう人、それを支える弁護士や医師・科学者、支援する人たちを見てきました。どの被爆者も「自分の人生をまどうてくれ」の思い、原爆の投下は過ちだったとアメリカに認めさせたい、謝らせたいと心底願っていました。
退職後の60歳代の時に、「救護の3号被爆者」問題で訴訟に取り組んだ人たちが勝利しました。内部被曝を問題にしたこの裁判の勝利が「黒い雨」の提訴につながったわけです。
「黒い雨」を問題にしてきて42年、提訴して5年(原告84名)になります。2020年7月29日、全面勝訴の第1審判決がありましたが、国、県・市が控訴。1年後の2021年7月14日、広島高裁は1審判決を超える画期的な勝訴判決を出しました。
私が団長となった第2次訴訟(11月13日現在原告64名)では、次の2つについて明快な判決を求めています。
①黒い雨の降雨域について、地・高裁判決を生かすこと
②入市被爆者、救護被爆者にはその事実が証明されれば、疾病を要件とせずに被爆者手帳を交付してきた。これと同じ扱いをすること。
核兵器禁止条約、ノーベル平和賞を生かす日本政府に変えよう
2021年1月22日、国連で核兵器禁止条約が発効したとき、私は「ようやくここまで到達したからね」と亡くなった被爆者の顔を思い浮かべながら、心の中で叫びました。
昨年10月11日には、日本被団協にノーベル平和賞が授与されました。これは、被爆者をはじめ、核兵器廃絶を願って戦後79年間運動してきた日本国民への表彰状です。戦争に備えてその準備にお金も知恵も注ぎ込むような国づくりはやめさせなくてはなりません。
ノーベル平和賞に応えて、憲法9条を生かし、戦争でもめ事を解決しない立場を貫くよう政府に求めていきたいと願っています。
|