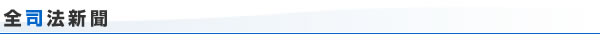 |
| |
|
�����́u���Ɏp���v�ς���
�u���S����RoootS�𗘗p���Ă��炢�����v�Ɖ�
�H�N���l���ǒ����� |
|
| |

���ɗՂޑS�i�@�{��
�@�S�i�@�{����12��9���A�ō��ٓ����l���ǒ��ƏH�G�N���������̂܂Ƃ߂ƂȂ�������{���܂����B�����ɂ��ẮA���@�����ɔ����ƍْ������̑������܂߂ď��Ɏp����ς��܂���ł����B�f�W�^�����ɂ��ẮA�K�v�ȉ��C���s�����Ƃ��āu���S���Ăq���������r�𗘗p���Ă��炢�����v�Ɖ��܂����B
�@���̑��A�Ζ����ԊǗ��V�X�e���̓W�J�A�X�g���X�`�F�b�N�̏W�c���͌��ʂ̊��p�A��C�������̃|�X�g�����Ȃǂő�������ƂȂ�������o���܂����B
���N�x�\�Z�ł̑���
�u�́A����w�������v�Ƃ̔F��������
�@�u�ٔ����̐l�I�Ԑ��̐�����}���Ă����K�v�����邱�Ƃɂ��āA�������ǂ̗�����ׂ��v�u�ő���̓w�͂��s���Ă���v�Ɛ����������ŁA�u���ƌ������̒�����߂�����A���N�㌩�W�����ȂLjꕔ�̎����������������͉����Ő��ڂ��Ă���Ƃ����������̓������̉��ŁA�ߘa7�N�x�̑������߂���́A����w���������̂ƂȂ��Ă���v�Ƃ̔F���������܂����B
�@������Ė{���́A6���ɐ��{���t�c���肵���u���̍s���@�ւ̋@�\�E����Ǘ��Ɋւ�����j�v������܂łƕύX����Ă��邱�ƁA��N�x�ȍ~�͎��������������ɓ]���Ă��邱�Ƃ������������Łu�V���Ȑ��x�����ւ̑Ή����K�v�ł���A�f�W�^�����̓������̎�Ԃ�����܂��܂������Ă����B�S�Ăɂ����āA�ٔ����̑������߂���͖��炩�ɂ���܂łƈقȂ�i�K�ɓ������v�Əq�ׂđ����ɑ���p�����������悤�������߂܂����B
�ƍْ������̑���
�lj��v���́u�l���Ă��Ȃ��v�Ɣے�
�@�ƍْ������̑����ɂ��Ắu�ߘa7�N�x�ɂ����ẮA�ƍْ�����5�l�����邱�ƂŁA�����Ƒ��@�̉~���Ȏ{�s�ɂނ��������E�������܂߁A�����������̖������ʂ������Ƃ��ł���Ɣ��f�����v�Ɖ��A�{�������߂��lj��v���́u�l���Ă��Ȃ��v�Ɣے肵�܂����B
�@�d�˂āA����̕��ь��c�̎�|���܂������������߂����Ƃɑ��Ă��u�ƒ�ٔ����Ɋ��҂���������K�ɉʂ�����悤�A���������A�K�v�Ȑl�I�E���I�Ԑ��̐������������Ă������ƂɂȂ�v�Ƃ̉��J��Ԃ��܂����B
���Ώk��
�����A���܂��u��������������w����O��v
�@���v�����̌����Ĕ��o���������A���i6��10���t���j�ɂ��āA�u�Ǘ��E�����Ζ����ԊǗ��̏d�v����F��������ŁA���ߋΖ��ɂ��ẮA�I�m���x�Ȃ��c�����A�K�Ȓ��ߋΖ����Ԃ̊Ǘ����s�����Ƃɂ��āA�Ǘ��E���ɑ���w����O�ꂷ��悤�A�����قɑ��Ď����A���o�����v�Əq�ׂ������ŁA�u��������������w����O�ꂵ�Ă��������v�Ɖ��܂����B
�@�܂��A�Ζ����ԊǗ��̃f�W�^�����Ɋւ���āA���N��1������ō��ق̈ꕔ�̕����Ŏ����I�ɓ������Ă���Ζ����ԊǗ��V�X�e���ɂ��āu���N1������ō��ق̑S�����ւ̓�����\�肵�Ă���B�܂��A����̓W�J�ɂ��Ă��������Ă���v�Ɖ��A�����قւ̓���������ɓ��ꂽ�����p���������܂����B
�@�����̊ȑf���E�������ɂ��ẮA���������u����܂ňȏ�Ɏ����̊ȑf���E�������A�Ɩ��v���Z�X�̌��������𐄐i���āA�ٔ����A�����ǂ��킸�A�g�D�S�̂Ƃ��Ē��ߋΖ��̍팸�ɂƂ肭�ޕK�v������ƍl���Ă���A������A�ʒB���̌�����������ɓ���Ȃ���A�ł��邱�Ƃ��珇�����₩�ɂƂ肭��ł��������ƍl���Ă���v�Ɖ��܂����B
 |
�ƍق̏[�������߂�
�E�ꌈ�c�i273�{�j���o |
�E���̌��N�Ǘ�
�W�c���͌��ʊ��p�Ɂu���炩�̍H�v�v������
�@�����^���w���X�̕s���������E�����}���ɑ������Ă��邱�Ɠ��������Č��N�Ǘ��{��̔��{�I�Ȍ��������s���悤���߂��̂ɑ��A�u�l�X�Ȏ����L����E�������邱�Ƃ��O���ɒu���Ȃ���A���N�Ǘ��{��̏[���ɂނ��Č�����i�߂Ă��������v�Ɖ��܂����B
�@�X�g���X�`�F�b�N�̏W�c���͌��ʂɂ��āA�u�W�c���͌��ʂ�E����̉��P�Ɋ��p�ł���悤���炩�̍H�v���ł��Ȃ����������Ă��������v�Ɖ��܂����B
�@�n���X�����g�ɂ��Ắu���̎�ނ��킸�A�����h�~���邱�Ƃ��A�E���������₷���E������ێ��E���シ�邽�߂ɕs���v�Ƃ��������Łu�n���X�����g�h�~�ɂނ��������ʓI�ȂƂ肭�݂ɓw�߂Ă��������v�Ɖ��܂����B
�@�J�X�^�}�[�n���X�����g�Ή��ɂ��Ắu�K�v�������I�ȓ����ғ��Ή��̎��H�Ɍ�������g�ɂ��āv�i2020�N10��30���t�������A���j�Ƃ���ɂ��ƂÂ��e���̎����t���[�������āu�g�D�Ƃ��ċB�R�Ƃ����Ή����Ƃ邱�Ƃɂ��A�����ғ��ɂ�邻�̂悤�ȍs�ׂ�}�~���Ă������ʂ�������̂ƍl���Ă���v���̔F���������܂����B������Ė{���́A���炩�Ɋ댯�E�������킯�ł͂Ȃ�����I�Ȏ��Ă��A���Y�E���ɂƂ��Ă͕��S�����d���A�u���Y�E������l�Ŗ�ʂɗ������Ȃ��v�g�D�I�Ή������߂���Ǝw�E���A�V�~�����[�V�����I�Ȃ��̂��܂߂����C�A���L�A�P���̕K�v����A�J�X�n�����Љ��艻���Ă�����ƂōŐV�̒m���ɂ��ƂÂ��ău���b�V���A�b�v���Ă����悤���߂܂����B
�f�W�^�����ւ̑Ή�
�q���������r�́u�s������������ꍇ�͑��₩�ɉ��C����v
�@�q���������r�ɂ��āA�u��s�������̋��͂̂������ŁA��v�ȑ���ɂ��Ẵo�O�͐o�����Ƃ��ł��A���̉��C��Ƃ��قڏI���邱�Ƃ��ł����B������A�s������������ꍇ�͑��₩�ɉ��C����̂ŁA���S���Ăq���������r�𗘗p���Ă��炢�����v�Ɖ��܂����B
�@�{������s������������o����Ă���ӌ����������āA�o�O��s������C����ΏI���Ƃ������̂ł͂Ȃ��u�g������v�̕������܂߂Č���̈ӌ��f�����A���C���Ă������Ƃ��K�v�ł���Ǝ咣�����̂ɑ��Ắu�O�����h�f�U�C���Ɏ����������̗��p���₷���̓O��Nj��ƐE���̗��p���₷���ւ̏\���Ȕz���Ƃ�����{�I�l�����Ɋ�Â��A������i�߂Ă��������v�Ɖ��܂����B
�E�����x
�ג�Ǘ��W���E�V���ȗތ^�̐��E�́A�����ɂނ��Č���
�@�u�g�D�������v�܂�����C�������̃|�X�g�����ɂ��āA�ג�Ǘ��W���ɂ��Ắu�W�̐V�݂ł���ȏ�A�Ǘ��W�̋Ɩ������ŌW��V�݂ł�����x�̋Ɩ��ʂ�����i���͍��セ�̒��x�̋Ɩ��ʂ������܂��j���Ƃ��K�v�ł���A���ق�K�͂̑傫���n�ƍق𒆐S�ɐ�����i�߂Ă���Ƃ���ł���A�����ł���i�K�ɂȂ莟������������v�Ɖ��A�V���ȗތ^�̐��E�ɂ��Ắu��C�������̐�含�̊��p�ɂ��ẮA���ӎ��������Ă���Ƃ���ł���A�V���ȗތ^�̐��E�̐ݒu�̘g�g�݂ɂ��āA�����̐ݒu�܂��āA����Ȃ�W�J���������Ă��������ƍl���Ă���A�����ł���i�K�ɂȂ莟������������v�Ɖ��āA���ꂼ��2025�N�x�̐����ɂނ����p���������܂����B
���ΐE��
�u����v���P�p���ꂽ��|�܂��ĉ^�p
�@���ΐE���̗̍p�ɂ��āu�l���@�K���ɂ����Č���ɂ��Ȃ��̗p�̏�����P�p���ꂽ��|�܂����^�p���s���Ă����v�Ɖ��܂����B����܂��āA�n�i�s�y�ѐl�ވ琬�̊ϓ_�܂������C���̎��{�����߂��̂ɑ��Ắu�v�]�����邱�Ƃ͏����Ă����v�Ƃ̉ɂƂǂ܂�܂����B
�@����ȊO�͏]�O�ǂ���ł����B�{������́A�ȏ�̑��A�l�ފm�ۂ�����ɓ��ꂽ�ƍْ������̈ٓ������琬�{��̌������A�l���@�̈ӌ��̐\�o�ɂ��ƂÂ��q�̊Ō�x�ɂ̕ύX���e�̎��m�O��A�ݔ��̈ێ����P�ɂ��ē��ɋ����咣���܂����B
|
| |
 |
| |
|
�S���̐N�P�P�S�l���ۋT�Ō�
Connect in �ۋT�i�����N�𗬏W��j |
|
| |

�Ί����L�O�ʐ^
�����i7���j
���ǂ���ƋՕ����U��Ō𗬐[�߂�
 |
| ���ǂ���ɑS�W�� |
�@12��7���`8���ɊJ�Â��ꂽ�u�������������� in�ۋT�v�ɂ́A�S�i�@����25�����܂ޑ���114�����Q�����A�听�������߂܂����B
�@1���ڂ͍����N�t�H�[�����^�c�ψ����̋g�����ꂳ�u2���ԂŊy�����v���o�����A�E��ŋ��L���A�g�D�g��ɂȂ��悤�v�ƎQ���҂ɔM�����b�Z�[�W��`���Ė����J���܂����B
�@�܂��Q���҂́A�ݐo�X�ŋՕ����̒��삤�ǂ�w�Z�Ɍ������A��~�Z�l�̔ǂɕ�����Ă��ǂ����̌����܂����B���߂ْ͋����Ă����l�q�̐N�������A�搶�̌y���ȃg�[�N�Ƒ剹�ʂ̉��y�̂������ň�C�ɑł������A�Ί炪���鎞�ԂƂȂ�܂����B���̌�A�Օ������U�A�ǑR�́u�f����ʐ^�v�œ��܂����߂�t�H�g�R���e�X�g�̂��߂ɂ�������̎ʐ^���B��Ȃ���A�H�ו������y���ޔǁA�����䗅�{��o��ǁA�������獁�쌧�̒n�������ޔǂȂǁA�ǂ��ƂŊX�̖��͂����\���܂����B
�@��̍��e��ł́A�����̎Q���҂��ʂ̔ǂ̐Ȃɑ����^��ŁA�P�g�E�ǂ����𗬂��Ȃ���A�t�H�g�R���e�X�g�̕\�����ł́A���̐���オ�肪�ō����ƂȂ�܂����B
2���ځi8���j
�������̔w�i�͍����g�D���ƘJ�g���c��̖@����
�@2���ڂ͌��w��i�I�E�n�N�X�E�j�搶�����������A�u���{�Ɗ؍��̒��������̈Ⴂ�v�ɂ��Ă̍u�����s���܂����B�؍��̐ϋɓI�ȃX�g���C�L�����������㏸�Ɋ�^���Ă��邱�Ƃ��Љ��܂����B�܂��A���{�̘J�g�W����Γ��ł��錻���A�g�D���̒ቺ��������̗v���Ƃ���A�u�J�g���c��i���j�̖@�����v�̕K�v������������܂����B
�@�܂��A�X�g���C�L���F�߂��Ă��Ȃ����{�̌������J���g���Ƃ��ẮA�u����̐����ׂ����E���グ�A�����Ă���E���݂̂Ȃ炸�A�L������ŎЉ�S�̂����߂Ă��邱�Ƃ�K�ɔc�����A�v���Ƃ��Č��Ŏ咣����v�Ƃ����ϓ_���d�v�ł���Ƃ̂��b������܂����B
�Ⴂ�����A�h�ɂ̘V�����A����͒P�g�����N�̗v�����I
�@���U��ł́A�u�����A�u�X�g���C�L���ł��Ȃ����ł��A�X�g���C�L���\���邭�炢�̏�M�������Č����邱�Ƃ̏d�v���v��u�؍��̘J�g���c���x�Ɋw�ԓ_�������v�Ƃ̓��e�����L����܂����B
�@�܂��A��薣�͓I�ȐE��ɂ��邽�߂ɂ͂ǂ�������悢���Ƃ����ϓ_�ł́A���Ɏ�N�w�̌������̒����̒Ⴓ��_��ł͂Ȃ��ٓ����x�A�V���������h�ɁA��z�߂���ƒ��蓖�A�ٓ����O�̓����Ȃlj��P���ׂ��ۑ�����L���邱�ƂŁA�P�g���������J�A�Ƃ��Ă̗v���̈���ƂȂ�b�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�����Ƃ����Ԃ�2���Ԃ��߂��A�Q���҂���́u����ɏZ�݂������炢�y���������v�u����Ȋy������ɎQ�����Ȃ��̂͂��������Ȃ��v�u���͂��J�Â���܂����v�Ƃ�������т̐�����������W��ƂȂ�܂����B
�@��������̂悤�Ȍ𗬂̏��ʂ��āA�P�g�������Ԃ�����A�e�E��ł̊����̊������ɂȂ��Ă��������ł��B
|
| |
 |
| |
|
�����������A���P���Ă������߁A�J���g���͂܂��܂��d�v
�n�A���L���S���҉�c�{�㋞�c���� |
|
| |
|
�����e�i���X���̑�@�̊m�ےlj��w���̗v�����m�F
 |
| ���L���̐����z���グ�A�ō��ق�Njy |
�@11��10���A�I�����C���Œn�A���L���S���҉�c���J�Â��܂����B���c�ň�Ԏ��Ԃ��|�����̂́A���v�����̍ō��ى��ď��߂Ď��{�����d�q���L�^�C�v���C�^�[�̃����e�i���X�ɂ��āA�e�E�ꂩ��o�Ă���s����ō��قɗ��ӂ����߂��������ɂ��Ĉӌ��������s���܂����B�����e�i���X���̑S�Ă̊��Ԃɂ����đ�@�̊m�ۂ��K�{�ł���_�A�ł��邾���Z���Ԃ̃����e�i���X�őS���̃^�C�v�������悭�����e�i���X���Ăق����Ȃǂ̐����オ��܂����B
�@�g�p6�N�ڂƂȂ�A�e�n�̃^�C�v�ɂ͌o�N�Ǐ�͂��Ƃ��s��Ǐo�Ă���Ƃ������Ȃ���A�C���̍ۂ̓^�C�v�������ɖ߂��Ă���܂Ő�������v�����Ƃ������ԕ�����܂����B���������ō��ق͑S����96��B���������œd�q���L�^�C�v���C�^�[�̍w���E�z�z���X�g�b�v���Ă��܂��܂������A�����e�i���X�Ƃ͕ʌ��Ăł�͂�lj��w���A�܂��^�C�v�̌v��I�ȍX�V�����߂Ă����Ƃ����_���ӎv���ꂵ�܂����B
�@���̂ق��A��c�ɐ�삯�Ď��{�������O�����̉���ɁA�S���̖�莖�ۂ�A���ɂ���Ď�����̎戵���ɈႢ�����铙�̎������_�Ȃǂ��ӌ��������܂����B
�d�q���L�^�C�v�̐����A�������⌤�C�ȂNj�̓I�ȗv�����������߂�
�@11��25���ɍs�����ō��ٌ��ł́A��c�Ŋm�F�����S���̈ӌ�����ɁA�d�q���L�^�C�v���C�^�[�̃����e�i���X�Ɋւ���v����A�lj��w���A�X�V�̗v�����͂��߁A���O�⒡���������Ă̏��i�v���A�������̉��P�v���A�܂��A���C�݂̍�����茒�N�f�f�̏[���A����Ǘ������̊ȑf���ȂǁA��̓I�ȗv�����ō��قɂԂ��܂����B
�@���L���{����~����27�N�������܂����B�S���̒n���قɂ͑��L�����z�u���������A���݂͑S���ő��L���z�u33���̂���3����1��11����1�l�z�u�ł��B���L���z�u��3�l�܂ł̏��l������24���ɂȂ�܂����B�e���ɏ��l���ŎU����Ă��鑬�L���̐����z���グ�A�����������A���P���Ă������߁A�S�i�@�̑��݂͂܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă������Ƃ��m�M�����S���҉�c�ƍō��ٌ��ł����B
|
| |
 |
| |
|
���ɂȂ�����j���m�����A�S�i�@�������
�g�c�������������s�ψ������� |
|
| |
 |
�S�i�@�{���ψ�������
�i1979�N�A57�j��
�g�c���� |
�@���������s�ψ����̋g�c�����i�悵���Ђ�̂�j����11��30���A103�ł��S���Ȃ�ɂȂ�܂����B
�@�g�c����́A�u�l�������v�ƈ��������ɑS�i�@�̉��U���d�|����ꂽ�U���˕Ԃ���1954�N�̓������Œ������s�ψ��ƂȂ�A56�N����63�N�܂ŏ��L���A64�N����79�N�܂ňψ����Ƃ��đS�i�@����������A���ɂȂ���E�ꓬ���̕��j���m�����܂����B
�@�u�ٔ����͍ٔ����������ׂ����v�Ɨv�������ٔ����������w���������Ƃ𗝗R��58�N��11�l�̑g�����ƂƂ��ɒ����ƐE�������܂������A22�N�Ԃɂ킽�邽���������o�āA��]�ґS���̐E�ꕜ�A���������܂����B
�@�E��́A�����F�D�A���j���a�^���ɐs�͂���܂����B
|