|
�@�S�i�@�{����6��5���`8���A���v���ѓO�����ɂ�����܂Ƃ߂̌������{���܂����B�ŏd�_�v���̂����A�������S�ʂ̏������P�A�f�W�^�����Ɋւ���e��{��A�ٔ������ɂ����镶���̎�舵���A�X�g���X�`�F�b�N�����p�����E������P�A�n�ƑO���̒��Ύ��Ԕc���ȂǁA�l�X�ȉۑ�ŗv���O�i�⑫������ƂȂ������܂����B�����܂��A�{����7��14���ɗ\�肵�Ă����u�v���[�g�s���v�̒��~���Ă��܂����B
�@�܂��A�l���ǒ����ɐ旧���āA�S54�x������̗v�����A�u��N�N��̒i�K�I���グ�̂��Ƃŏ��i�̓��B�_�ێ������߂鏐���v2123�M�i��1���W�j�A���L���̗{���ĊJ����3041�M���o���܂����B

�����������ɗՂޒ������s�ψ�
���i�^�p�̈ێ��Ǝ������̏������P����
���i�^�p�S�͈̂ێ�����p��
�@�u����܂œ��l�A�ސE��5���̘g�g�݂̈ێ��ɓw�߂����v�Ƃ̎p���������ƂƂ��ɁA�u�ٔ����̑g�D����ѐE���̓��ꐫ����������āA�\�Ȍ��茻�݂̏��i�^�p���ێ��ł���悤�w�͂������v�Ɖ��āA���̑��̐E��⋉�ɂ��āA��N�N����グ�ɔ������i�^�p�̌��|���͍s��Ȃ��l���������܂����B
��C�������̏������P�ɂނ����p��������
�@�܂��A���̖����������S�̂̏����Ɗ֘A�Â��ĒNjy�������Ƃ��āA�����������Łu��C�������̐�含�̊��p�ɂ�������悤�ɔz�����Ă��������v�Ɖ��A����܂ł����߂Ă��������ǁi�ہj���E�̃|�X�g�g�[�ɐG���ƂƂ��ɁA�x���E�ȍُ����ے��ւ̓o�p�A�ג�g�D�̌������ɂ���C�������|�X�g�̐ݒu�A���ϑg�������ɔ��������̒ቺ�������w�͂Ȃǂ̑O�i���s���A�S�i�@�������v������4�����i��O���Ɂu�����H�v�ł��Ȃ����������Ă݂����v�Ɖ��܂����B
�@�����́A�u���i�̓��B�_�ێ������߂鏐���v�ɑS�E���ΏۂłƂ肭�݁A�v���[�g�s����w�i�Ɍ��ɗՂ��ʂł��B
�g�D�E�@�\�̌������o���A�f�W�^�����͊������Ɍ������p��
�Q�O�Q�S�N�x�ȍ~�A�g�D�E�@�\�̌��������s��
�@�u����̕��������v�Ɋւ���āA2024�N�x�ȍ~�A�ٔ����S�̂̑g�D�E�@�\�̌��������s�����Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B�u����܂ł̑����`�g�D�i���E���K�͂Ɋւ�炸�A��{�I�ɂǂ̖{���ɂ������|�X�g���ݒu����Ă���g�D�j���������A�e���ɂƂ��čœK�ŁA�E�����{���Ƃ肭�ނׂ����j�I�����ɒ��͂ł���g�D�Ԑ����\�z����v�Ƃ��Ă���A���Ȃ�傫�Ȍ������ɂȂ邱�Ƃ��\�z����܂��B����̓����𒍎�����K�v������܂��B
�f�W�^�����Ɍ������p��������
�@�ٔ����̃f�W�^�����ɂ��ẮA�u�����̗��p�̂��₷���i������₷���g���₷���V�X�e�����j��O�ꂵ�ĒNj�����ƂƂ��ɁA�E���̗��p�̂��₷���i�����I�ȑ��쐫�A���[�U�[�C���^�[�t�F�C�X�̋��ʉ��A���������j�ɂ��\���z�����Ă��������v�Ƃ��������ŁA�K�v�ȗ\�Z�̊m�ۂɌ����čő���̓w�͂��s���p���A�E���̈ӌ��悷��p���������܂����B
�f�W�^�����̊�����������
�@�܂��A�E�F�u��c�̂��߂̊������A�����k�`�m�̌��A�|�[�^���T�C�g���g������L�A�i�E�m�d�s����̋����Ȃǂ�������A�u�����i�葱�̃f�W�^�����i�t�F�[�Y3�j�����������@�삨��ыƖ��̂���l�̌������@�̈�Ƃ��āA���؎����p�̖@������邱�Ƃ��������Ă���v���Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�@�Ȃ��A�e�����[�N���ɂ��Ă������p���������Ă��܂��B
�u�ٔ������ɂ����镶���̎�舵���v������
�@�V�X�e�����ɂ�鎖���̕W�����E�������܂��u�f�W�^������̍ٔ������ɂ����镶���̎�舵���v�ɂ��Č������Ă���Ɖ��܂����B�u�O�������Ȃ����v�Ƃ̗v���ɉ�������̂ł���A�ȑf���E�������Ɍ������傫�ȑO�i�ł��B���̑��A�ō��قɂ��}�j���A���⎷���������̐����A�������̓���ɂ��Č����p�������������ƂƂ��킹�āA�S�i�@���v�����Ă���S�����ꉻ�E�W�����ɂ�鏑�L�������̊ȑf���E�������Ɍ����āA���������z�����ƂȂ�܂����B
�����^���w���X�E�p���n����ɁA�X�g���X�`�F�b�N�����p
�X�g���X�`�F�b�N�ɂ��W�c���͌��ʂ����p
�@�����^���w���X�d�v�ȉۑ�ɂȂ��Ă���Ƃ̑S�i�@�̎咣�ɉ����A���N�x����X�g���X�`�F�b�N�̒������ڂɁu�d���̂�肪����E��̐l�ԊW�A�R�~���j�P�[�V�������v�ɂ��Ĕc���ł��鍀�ڂ�lj����A���݂�57���ڂ�80���ڂɑ��₵�Ď��{����Ɖ��܂����B���킹�āA�u�e���ɂ����āA�W�c���͌��ʂ�����Ɋ��p�ł���悤�������Ă��������v�u�e���ɂ����āA�n���X�����g���܂߂��E������P�Ɋ��p�ł���悤�ȍH�v���l���Ă݂����v�Ƃ��Ă���A�X�g���X�`�F�b�N���c�[���Ƃ��Č��N�Ǘ��{������O�i����������Ă��܂��B
�@�܂��A�ٓ����Ƀ����^���s������E�����������Ƃ܂��A�E���������C�̏d�v�����咣�����̂ɑ��āu��������ʓI���[���������C�����{�����悤�A�w�͂��Ă��������v�Ƃ̉������o���܂����B
�@�����̉𑫂�����Ƀ����^���s���̔����\�h���܂߂��Ƃ肭�݂����������悤�A�e���ŋ�̉������Ă������Ƃ��d�v�ł��B
���Ύ��Ԕc���ȂǂŁA�ō��ق̔F���ƐE����Ԃ̂������߂�w�͂����߂�
�l�I�Ԑ������́u�ő���w�́v
�@2024�N�x�\�Z�Ƃ̊W�ł͐l�I�Ԑ�������A���i�̂��߂̗\�Z�ƂȂ鋉�ʒ萔�ɂ��āu�ő���̓w�́v�p���������܂����B
�@�����ɂ��Ă͏�̌��������������A���{�́u����������v��v�ւ̋��͂�����w�͂̎p���͕����܂���ł������A�u���p�҃T�|�[�g���܂߂��f�W�^�����̑Ԑ������v��u���[�N���C�t�o�����X���i�̂��߂̐l�I�z�u�v�ɂ��Ă͓w�͎p���������܂����B���Ė{���́A�e�n�A�E�x���������Ŏ咣���Ă���E����Ԃ�������Ɣc�����������ŁA���������������ߍׂ������Đl���z�u���s���悤�d�˂Ď咣���܂����B
�u�K�ȋΖ����Ԃ̊Ǘ����s���悤������w����O��v
�@���Ώk���ɂ��Ắu���ߋΖ����߂̏���K���̓�����A���ߋΖ��̍팸�͂܂��܂��d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���v�Ƃ̔F�������߂Ď����A�u�g�D�S�̂Ƃ��Ď����̍������E�������𐄐i���āA���팸�ɂނ����Ƃ肭�݂�����܂ňȏ�ɂ����߂Ă����K�v������ƍl���Ă���v�Ɖ��܂����B
�@�ō��ق̔F����ƐE����Ԃ̂������̑傫�������ƂȂ��Ă��钴�ߋΖ����Ԃ̔c���ɂ��Ắu�Ǘ��E�����Ζ����ԊǗ��̏d�v����F��������ŁA�����E���̎��������������ߍׂ������āv�u�K�ȋΖ����Ԃ̊Ǘ����s���悤������w����O�ꂵ�Ă��������v�Ɖ��߂ĉ��܂����B
���ߋΖ��u�n�ƑO���ς��Ȃ��v���Ƃ�O��
�@����܂��A���ۂɂ͂���ȏ�̒��ߋΖ������Ȃ��猎30���Ԉȓ��ɒ������Đ\��������Ԃ��S���I�ɍL�����Ă�����Ԃ��咣����ƂƂ��ɁA�Ƃ�킯�u�Ζ����Ԕc���ɂ��ẮA�n�ƑO�A���x�݁A�x���ɂ�����Ζ��ɂ��Ă��ς����̂ł͂Ȃ��v�Ƃ̉������قɓO�ꂷ��悤�������߂܂����B
�@�������A�ō��ق̔F���ƐE����Ԃ����������Ă���ۑ�Ƃ��āA�玙�Z���ԋΖ���玙���ԂȂǂ̐��x�𗘗p���Ă���E���̋Ɩ��ʂ̒����ɂ��āu�\���ڔz�肵�Ă����悤�����ق����������w�����Ă��������v�Ɖ��܂����B
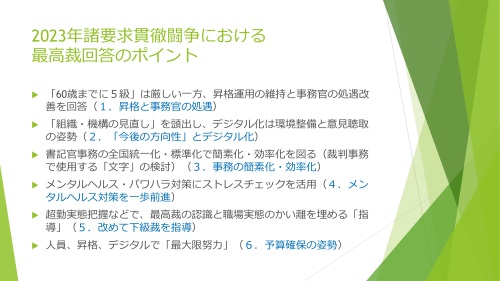
|