|
全司法本部は12月1日、最高裁徳岡人事局長と秋季年末闘争期の交渉を実施しました。デジタル化に関する動きが見えるとともに、事務の簡素化・効率化や事務官の研修制度等の要求が前進し、超勤実態や健康管理など多くの課題で改めて職場実態を伝える交渉となりました。
交渉に先立って、全国でとりくんだ「人員シフト反対を求める要請書」(全54支部分)を提出しました。
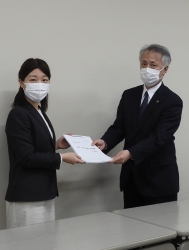 |
|
全54支部分の要請書を提出 |
人員
必要な人員の確保に「最大限努力」。
「内部努力」は姿勢変えず
2023年度の定員について「必要な人員の確保について、引き続き最大限の努力をしていきたい」との姿勢を示しました。
人員配置については、引き続き内部努力の必要性を強調し、「人員配置の見直し後の事務処理態勢等についても、十分検討した上で実行してきている」との認識を変えませんでした。地方の庁を中心にギリギリの人員で事務処理を行っており、病休や欠員等が出た時の負担が重くなっていることを指摘して、事務処理状況をきめ細かく見るよう改めて強く求めました。
超勤実態の把握
早朝など「実態把握は当然」「下級裁を引き続き指導」
サービス残業が全国的に広がっている実態を指摘し、改めて下級裁を指導するよう求めました。とりわけ、始業前の超過勤務の実態把握を強く主張しました。これに対して「官側が早朝、昼休み、休日を含め超過勤務の実態を把握する必要があることは当然」としたうえで「超過勤務については的確かつ遅滞なく把握し、適切な超過勤務時間の管理を行うよう、下級裁に対して引き続き指導を徹底していきたい」と回答しました。
最高裁事務総局において、「感染防止の観点にとどまらないテレワークの試行をする」ことを改めて表明しました。裁判所におけるテレワークについては、デジタル化の状況や人事院の動向も見ながら、組合員の意見を踏まえて対応することになりますが、勤務時間管理のあり方が最大の課題になります。最高裁が「必要に応じて職員や職員団体の意見を聞くなど、適切かつ誠実に対応していきたい」と回答していることを踏まえて、議論していくことが重要です。
事務の簡素化・効率化
秘匿情報の管理に関する事務フローなどを周知
民事訴訟手続において当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度が開始されるにあたり「秘匿情報の管理に関する標準的な事務フロー、書式例及び事務処理上の留意すべき事項」をとりまとめて周知したこと等を回答しました。
会計課の簡素化・効率化について「次年度についても、日本銀行代理店の統廃合が予定されていない支部も含め、歳入歳出外現金出納官吏の本庁集約実施を検討したい」と回答しました。また、12月のハラスメント防止週間の動画をDVDではなく、職員貸与端末で視聴可能としたことについて「より効率的に職員の業務の状況に応じて柔軟に視聴することが可能となる」との認識を示しました。
健康管理
「職場としてでき得る配慮をしていきたい」
メンタルヘルスを悪化させる職員が増加している実態を主張して追及したのに対して、「今後とも職員の健康保持に向けて職場としてでき得る配慮をしていきたい」と回答しました。長時間勤務の他にも、当事者対応や事務処理を行う上での緊張感、研修等での知識付与が十分に行われていないことによる不安感、各種ハラスメントなど、様々な原因ごとに対応を検討するよう強く求めました。
ハラスメント対策については、12月のハラスメント防止週間で職員の意識啓発を図る措置、10月に実施したハラスメント相談担当者等セミナーの概要について説明し、「次年度以降も実施していきたい」と回答しました。
裁判所のデジタル化
「職員との双方向のコミュニケーションの充実に努める」
システム開発等に当たって「最高裁と職員との双方向のコミュニケーションの充実に努め、職員及び職員団体の意見も踏まえながら検討を進めていきたい」との姿勢を示すとともに、システム(TreeeS)の開発、IT情報基盤の強化、情報の集約と共有などについて回答しました。
当事者サポートの方策として、TreeeSにおけるAIチャットボット機能の活用を検討していることを明らかにしました。
事務の効率化の観点から、J・NETメール送受信時の容量制限を10MBに緩和する旨回答しました。
また、引き続き「デジタル化のために必要な予算の確保に向けては、最大限の努力を行いたい」との姿勢を示しました。
職員制度等
「一定の経験を積んだ主任・調査員を対象とした研修」を実施
諸要求期に検討するとしていた50代の職員を対象にした研修について「実施する」と回答しました。
定年前再任用短時間勤務職員について「非常勤職員であり、その採用のみをもって常勤職員の定員が削減されることはない」と回答しました。これにより、高齢期のニーズに応じた働き方を実現すると同時に、職場の人的態勢整備に活用できる可能性が生まれました。また、定年年齢引上げに伴う昇格運用について、実質的な処遇の低下を招かないよう、改めて要求しました。
諸要求期に検討するとしていた事務官として一定の経験を積んだ主任・調査員を広く対象とした研修について「実施する」と回答しました。全司法が要求していた「研修制度の見直し」の中心となる研修が実現することになります。
任官前の家裁調査官補の退職が続いていることについて「今後とも適切な指導・育成に努めていきたい」と改めて回答したことを踏まえ、今年度以降の状況を注視する必要があります。
育児短時間勤務等
職場内で話し合うよう、引き続き下級裁を指導
育児短時間勤務等をとっている職員がいる場合に、管理職による業務量の調整や、周囲の職員の理解を得て職場全体で体制を作ることが十分にできていない実態を指摘し、改めて下級裁を指導するよう求めたのに対し、最高裁は「引き続き下級裁を指導していきたい」と回答しました。
庁費について、光熱水料に係る補正予算、器具備品整備表における基準単価の改定について説明しました。全司法の主張を重く受け止めた結果だと評価できます。
2023年度予算に向けた級別定数の改定については「引き続き最大限の努力を続けていきたい」との姿勢を示しました。
2022 秋年期人事局長交渉
「裁判所のデジタル化」関係の回答の動き
〇システム(TreeeS)の開発
「システム概要スライドに関する意見交換を予定しており、その結果を職員に還元することも検討している」「レスポンスについて高い応答性を確保するとともに、通信性能について裁判所職員だけでなく国民も利用するシステムであることを踏まえ大容量のデータのやりとりに対応できるよう強化する方向で検討を進めている」
〇IT情報基盤の強化
「J・NETの最適化に関するコンサルティングにおいては、将来的に発生することが想定される通信も含めてトラフィック量等を調査し…、ネットワークの最適化及びコスト削減が図られるようなJ・NETの全体構想について、複数案の提案を受けており、この結果も踏まえて検討している」
〇情報の集約と共有
「職員が執務に必要な情報を簡易迅速に取得したり、有益な情報を裁判所全体で共有したりすることが可能となるよう、検討を進めていきたい」「マイクロソフト365の各種機能紹介を、今月から全三、四回の予定で、J・NETポータルに掲載することを予定している」
〇TreeeSにおけるAIチャットボット機能の検討
「(mints について)AIチャットボット及び問い合わせフォームにより、機能や操作に関する利用者からの問い合わせに対応している…TreeeSにおいても同様の機能を検討中である」
〇メール送受信時の容量制限の緩和
「来年度の初頭頃を目途に、現行の2MBから10MBに変更するよう準備を進めている」
〇デジタル化に伴うサポートのための人員確保
「利用者のサポートのための態勢も含め、必要な人員の確保について努力していきたい」
〇総研におけるデジタル化を踏まえた研修設備
「可能な限り早期にインターネットに接続した研修を実施したいと考えている」
|