|
5月8日〜9日、第27回全司法中央労働学校を開催しました。今回は集合とオンライン併用での参加とし、グループトークなどを交えて、参加者が主体的に学習できるよう形式を工夫しました。
初日は、全労連(全司法も加盟している民間労組も含めたナショナルセンター)事務局長の黒澤幸一さん、大阪で労働組合などを対象に学習活動を企画・運営している関西勤労者教育協会講師の箕作勝則さんをそれぞれ講師として、賃金引上げの運動や、労働組合の組織運営について学びました。
2日目は、中矢委員長のコーディネートで職場の要求活動について、広島支部の福本律雄さんを講師に国公共済会の活用について学習しました。
労働者が賃金を要求するということ
―日本四半世紀に及ぶ賃金下落の実態から考える―
全労連事務局長 黒澤 幸一さん
 |
|
全労連事務局長の黒澤さん |
賃上げは「今の日本の最大の課題」
黒澤さんは冒頭に、日本はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中で、唯一実質賃金が下がり続けている国であること、平均賃金は約423万円でOECDに加盟する35か国中22位、アメリカの約763万円と比較すると44%もの開きがあり、隣の韓国よりも約37・9万円(月3万円以上)も低くなっていることを指摘しました。
また、最低賃金近くで働いている人が10年間で倍増、労働者の約3割にのぼることを示し、非正規労働者や低賃金の正社員が増えたことが主な要因だとしました。とりわけ、女性が低賃金に据え置かれていること、看護師や介護職員をはじめとしたエッセンシャルワーカーの賃金が他の業種に比べて低いことを指摘しました。加えて、コロナ禍が生活悪化に追い打ちをかける一方で、大企業はコロナ禍でも内部留保を増やしている実態を明らかにしました。
そのうえで、経済学の立場からも、非正規雇用の増加や低賃金が仕事の質を落として生産性を低下させ、経済も停滞させているとの指摘があることを示し、賃金を引き上げることが、今の日本の最大の課題になっていると述べました。
「最大の原因は、労働組合が賃金を要求してたたかわないから」
続いて「なぜ、賃金が上がらないのか?」と問題提起し、参加者のグループ討議を交えながら討論しました。様々な要因が上げられる中で、黒澤さんは「最大の原因は、労働組合が賃金を要求してたたかわないからだ」と指摘しました。
賃金は労使の力関係で決まるという原則や憲法が定める労働三権、「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」と定めた労働基準法の規定などにも触れながら、「私たちは労働組合に入ってこそ、使用者と対等の立場になれる」として、みんなが労働組合に加入することの重要性を説きました。
そのうえで、賃上げのたたかいでも「労働組合が労働者の立場に立ちきる」ことが重要だと述べました。22春闘で満額回答を勝ち取ったとは言え、そもそも数千円の賃上げ要求しかしていない連合の運動の問題点を指摘しつつ、諸外国ではストライキが当たり前に行われている実態も示して、全労連の運動としても、(民間では)法律で認められているストライキを背景にして、官民一体で賃上げのたたかいを強化する必要があると説明しました。
そして、最後に「It’sUnionTime(いまこそ労働組合)」の言葉で講演を締めくくりました。
「誰でも入れるたたかう組織」
〜労働組合と政治との関わりを考える〜
関西勤労協講師 箕作 勝則さん
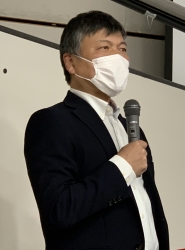 |
|
関西勤労協講師の箕作さん |
「政治闘争をするから組合員が増えないのか?」
「労働組合としての『あたりまえ』を基本に」と切り出した箕作さんは、「政治的な活動(政治闘争)を行うことに違和感を覚える組合員」がいることを前提に話を始めました。「一番身近な要求は賃上げや時短、休日などの要求。そうした職場の要求は切実で、多くの人が共感できるから、そうした要求をかかげた『経済闘争』をしっかりたたかうことが労働組合の活動の大前提」だと説明しました。
そのうえで、要求実現のためには政治闘争(注・要求実現のための政治的な分野での運動。「政治活動」ではない)も必要になると指摘しました。
続いて、「政治闘争をするから組合員が増えないのか」と問題提起し、参加者とのやりとりを通じて「政治闘争をすること」が組合員が増えない主な要因ではないと整理し、組織拡大が進まない要因について分析しました。アメリカの労働運動(レイバーノーツ)が整理している4つの組織化を妨害するもの(展望がない、恐怖、分断、混乱)を示し、「展望がない」(労働組合に入っても変わらない、無力だと考えられている)と「混乱」(労働組合について正しい情報が伝わらなかったり、誤った情報が伝わっている)という二つの要因があると指摘し、その解決のためには対話が重要だとしました。
また、労働組合は「誰でも入れるから、何でも話せる組織」であり、政治に関する問題でも労働組合役員が「これが当たり前」だと考えずに、相手の話をよく聴くことが大切だと述べました。あわせて、「労働組合が政治闘争にとりくまなければ、労働者が職場内で政治的要求に触れる機会はほとんどない」と指摘し、事実にもとづいて組合員との対話を重ねることが必要だとしました。
「おかしいことは、『おかしい』と言うのが労働組合」
自身の経験から、業務で使っているスマホが故障した場合、給料から天引きされ、「おかしい」と思いながらも、みんなが黙ってた職場で、労働組合役員経験者が「おかしい」と声をあげ、交渉で改めさせた事例をあげて、「おかしいことは、『おかしい』と言うのが労働組合」だと述べ、組合員と対話をしていくことで、展望を示し、混乱を解消し、たたかいを通して組織を強く大きくしていくことが重要だと指摘し、それが「労働組合の真骨頂」だとされました。
職場諸要求前進に向けた運動のすすめかた
労働組合があるから当局の目が職員に向き、働きやすい職場が作られる
 |
|
集合・オンライン合わせて56名が参加 |
2日目、「職場諸要求前進に向けた運動のすすめかた」と題して講義を行った中矢委員長は、最初に、労働組合の機関役員は、組合員が活動に参加できるようにするオルガナイザーだと述べました。
そして、労働組合の要求活動は「組合員の要望を役員が請け負って代わりに解決するものではなく、本人が一人では解決することが難しいから、みんなで力を合わせて解決する」活動であり、それをコーディネートすることが役員の役割だと指摘しました。
あわせて、「職場の問題点をみつけ出し、改善を求める存在(労働組合)があることで、使用者(当局)は一方的に物事をすすめるのではなく、働く者(職員)に目が向くようになり、その結果、働きやすい職場が作られ、仕事の質を高めることにもつながっていく」と指摘して、それが、労働組合の要求活動の最も重要な意義だと強調しました。
組合員に「展望」と「知識」を示しながら要求を「組織する」
また、単に「要求はありませんか?」と職場に丸投げするだけで要求が出てくることは、ほとんどなく、組合員に「展望」と「知識」を示しながら要求を「組織する」オルガナイザーの役割が重要になることを説明しました。
そのうえで、参加者と一緒に模擬の職場会を実施しながら、全司法が毎年6〜7月にとりくんでいる職場総点検・要求組織運動の目的を説明し、要求書づくり、交渉と折衝などの当局への働きかけ、ストライキ、プレート行動、署名、職場大会など労働組合がとりくんでいる様々な行動について、その意義と目的を解説しました。
国公共済会を組織強化・拡大のツールに!
「国公共済会を活用しよう!」と題して講演した福本さんは、国公共済会について「組合員だけが入れるお得な制度であり、優位性が豊富にある」と説明しました。
「加入することで、組合費で支出した分を相当程度カバーできる」ことを強調するとともに、「国公共済会に入りたいから、組合員を続けている」という人もいることなどを紹介して、国公共済会の加入者を増やす意義を説明し、「組織強化・拡大のツールとして積極的に使っていきましょう」と述べました。
また、そのために「全司法本部にも相談して、各地で組合員に国公共済会の説明をする機会を作りましょう」と呼びかけました。
|