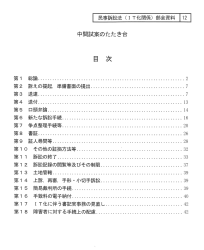 |
�@���R����o����
�u���Ԏ��Ă̂�������v�i�ڎ��j |
�@��N12��25���ɊJ�Â��ꂽ�@���R�c����i�ז@�i�h�s���W�j�����7���c�ŁA�u���Ԏ��Ă̂�������v�ɂ��ĐR�c���s���܂����B
�@���̒��g�ɂ��āA�S�i�@�����ɊS�������Ă��������𒆐S�Ɍ������Ă݂܂��B
�I�����C���\��
�u�`�����v���_�_
�@����������Ă��閯���i�ׂ̂h�s���ł́A�C���^�[�l�b�g�ɂ��\���Ă���������܂����A������`�������邩�ǂ������_�_�ƂȂ��Ă��܂��B
�@��������ł́A�@�`�������������ŁA�i�ב㗝�l�ȊO�̎҂Łu��ނȂ��������v�ꍇ�́u���̌���ł͂Ȃ��v�Ƃ���i�b�āj�A�A�i�ב㗝�l�ɂ��Ă͋`��������i���āj�A�B�`�������Ȃ��i���āj��3�Ă�������Ă��܂��B�`��������ꍇ�A���ʂŒ�o���ꂽ���ɂ́u�i��R�����ɗނ���R������n�݂��邱�Ƃ��l������v�Ƃ��A���L����������Ƃ��Ď��Ȃ����̔��f���s�����Ƃ��z�肳��Ă��܂��B
�@�S�i�@�́A�ٔ��葱�̂h�s�����u�i�@�A�N�Z�X�̌���v�Ɓu���������p���₷���ٔ����̎����v�Ɏ�������̂ƂȂ�悤�咣���Ă��܂����B�i�@�A�N�Z�X�̌�ނɂȂ���\��������I�����C���\���Ă̋`�����ɂ͐T�d�ł���ׂ����ƍl���܂��B�`�����ʼn����t����̂ł͂Ȃ��A�I�����C���\���Ă�I�����闘�p�҂�������悤�A���p���₷���V�X�e�����\�z���A�T�|�[�g�̎d�g�݂���邱�Ƃ������d�v�ł��B
�i�L�^�͓d�q��
���B���I�����C����
�@�i�L�^�͓d�q������邱�ƂɂȂ�A���̋L�^�͂Ȃ��Ȃ�܂��B�i���̒�N�A�������ʁE���̒�o���A�ٔ����́i�T�[�o�[�́j�t�@�C���ɋL�^������@�ɂ���čs���܂��B
�@�L�^���d�q������邱�Ƃ���A���ʂɂ��\���Ă��s��ꂽ�ꍇ�A���ʂ�d�q�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂����A�ٔ��������̎������s���ɂ������āu�̑Ή��Ƃ��āA�萔�������邱�Ɓv����������Ă��܂��B�܂��A�V�X�e�����B�Ⓖ���ł��A�ٔ������o�͂������ʂ�p����ꍇ�Ɏ萔����[�t������Ƃ����l������������Ă��܂��B�h�s���ɔ����āA���������V���ȗ��p�ҕ��S�̎d�g�݂����邱�Ƃ��T�d�ł���ׂ��ł��B���̂悤�Ȏ萔���̒����͎����Ƃ��Ă��ώG�ɂȂ�A�u�X�֔�p�̎萔���ւ̈�{���v���Ƃ̐������ɂ��^�₪�����܂��B
�@���B�ɂ��ẮA�t�@�C���ɓd�q���ށi�f�[�^�j���L�^���A���̎|���҂̓d�q���[���A�h���X�ɒʒm��������i�V�X�e�����B�j����������܂��B�ٔ����̓����҂ɑ��鑗�t�A�����҂̑�����ɑ��钼�����A���̎d�g�݂��g���܂��B�������A�����҂ɓd�q���[���A�h���X��o�^������K�v������A���ꂪ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�]���ǂ���A�X�����t�ɂ�邱�ƂɂȂ�܂��B�������B�͒��ɂ̌f���ł͂Ȃ��A�ٔ����̃E�F�u�T�C�g���Ɍf�����čs���܂��B
�����٘_�Ȃǂ̎葱��
�E�F�u��c�������p
�@�ٔ����������ƔF�߂�Ƃ��́A�����҂̈ӌ����āA�E�F�u��c����p���Č����٘_�̊����ɂ�����葱���s�����Ƃ��ł���Ƃ��Ă��܂��B�����҂��ٔ����ɏo�����Ȃ��Ă������٘_�������J����Ƃ������ƂŁA�������@�����̈�̃|�C���g�ł��B
�@�ؐl�q��ɂ��Ă��A�ؐl�̏o��������ȏꍇ�����łȂ��A�u�����ƔF�߂�ꍇ�ɂ����āA�����҂Ɉًc���Ȃ��Ƃ��v���E�F�u��c���ɂ����{���ł���Ƃ��Ă��܂��B
�@�h�s�c�[���̓������\�����p���邱�Ƃ�O��ɁA6�����ȓ��ŏI������u�V���ȑi�葱�v�̑n�݂���������Ă��܂��B����ɂ��Ă��A�����\���Ăɂ��b�āA�����ҋ����\���Ăɂ�鉳�āA�V���Ȏ葱�݂͐��Ȃ��Ƃ��镸�Ă�������Ă��܂��B
�@���_�����葱���ɂ��ẮA�d�b��c���̊��p�Ƃ��킹�āA�����I�����٘_�A�٘_�����葱�A���ʂɂ�鏀���葱��3��ނ̎葱���ǂ��������邩����������Ă��܂��B
�@�a���ɂ��ẮA�d�b��c���̊��p�Ƃ��킹�āA�u�V���Șa���ɑ��錈��v�������̘�ɂ̂ڂ��Ă��܂��B�܂��A����a���ɂ����āA���L���̒����L�ڂŊm�蔻���Ɠ���̌��͂�L����|�̋K���݂��邱�Ƃ���������Ă��܂��B
�@���̑��A�i�s���c�A�R�q�A���ψ����x�A�ʖ�l�A�Ӓ�l�A���A�ٔ����O�ɂ�����؋����ׂȂǁA�����̏�ʂŃE�F�u��c���̗��p���g�傷���������������Ă��܂��B
�X���\�[�p�~
���L�������̊g���
�@�����́u�d�q�������v�Ƃ��č쐬����A����Ɋ�Â��Č����n���A���B�͏o�͂������ʂōs�����V�X�e�����B�ɂ�邱�ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A�٘_�̍X�V�ɂ��āA���ʒq�����O���Ă��Ă��u�ًc���Ȃ��Ƃ��ɂ����r�����������݂Ȃ��K��v���Ă���ӌ������������Ƃ��Љ��Ă��܂��B
�@�S�i�@�̋����v���ł������u�X�֔�p�̎萔���ւ̈�{���v�����荞�܂�A�X�֔�p�̗\�[���x��p�~����Ƃ��Ă��܂��B�萔���̔[�t���@�̓y�C�W�[�ɂ��[�t��������Ă��܂��B�Ȃ��A�I�����C���\���Ă𑣐i����ϓ_������A�萔���̊z�ɍ��ق�݂���Ƃ����l�������L�ڂ���Ă��܂����A����ɂ��ẮA��ɏq�ׂ��萔�������Ɠ��l�A�i�@�A�N�Z�X�ɗ^����e���̗L����T�d�Ɍ������ׂ��ł��B
�@�h�s���ɔ������L�������̌������ɂ��Ă����y����Ă���A�S�ێ���A�i��̕�y�ыp���̈ꕔ�A�����̍X���Ȃǂɂ��āA���L�������Ƃ��邱�Ƃ��������Ă��܂��B
���u���Ԏ��Ă̂�������v�́A�@���Ȃ̂g�o�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B
�����i�葱�h�s���Ɋւ���S�i�@�̍l����
�����ψ���ɒ�N
�@�S�i�@�́A�ٔ��葱�h�s���ɂ���2017�N6��9���̐��{�̊t�c���蓖�����狭���S�������A�ߖڂ��Ƃɏ��L���k�b�A�v�����A�ӌ����Ȃǂo���Ă��܂����B�܂��A��N7���̑�77�������ł͖{�����Ɂu�ٔ��葱�h�s�������v���W�F�N�g�v�i�����o�[�͖����̂Ƃ���j��ݒu���A�S�i�@�̗v����l�����ɂ��Č������Ă��܂����B
�@�@���R�c��ł̐R�c���}�s�b�`�ł����߂��A�����i�葱�̂h�s�����{�i�����Ă��邱�Ƃ܂��A1��31���`2��1���ɊJ�Â�����81���ψ���ł͑�1���⑫�c�ĂƂ��āu�����i�葱�h�s���Ɋւ���S�i�@�̍l�����v���m�����܂����B
�v���W�F�N�g�ł̌������I����
���e���ڂɂ����āA���݂����������ȑf���E�������ł���悤�A�����_�ŗv�����ׂ����Ƃ͖ԗ��I�ɋc�_�ł����Ǝv���܂��B�h�s���ɂ��A�u���L���������ȑf���E���������ꂽ�v�A�u�]�������ٔ��������p���₷���Ȃ����v�Ƃ����������������Ă���悤�ɁA����A�F������c�_���Ă���������Ǝv���܂��B
�@�͏�@�^�[
���ٔ����ɉ�����h�s���̔g�́A�ٔ������̑��̕���֍L����������Ă�����A�R���i�Ђɂ�����ٔ������݂̍���ɕω������悤�Ƃ��Ă����肵�Ă��钆�ŁA�h�s���Ɍ������c�_�͂����F����̐g�߂Ȃ��̂ƂȂ�͂��ł��B���́u�l�����v�����������ɍٔ��葱�̂h�s���ɊS���Ă��炢�A���ꂩ��l�X�Ȉӌ����o���Ă��炦��Ǝv���܂��B
�@�ē��@�T�L
���v���W�F�N�g�ł́A�@���R�c�����٘A�Ȃǂ̓������ӎ����Ȃ���A�ٔ������L���̎��_�E���p�ҁi�����ҁj�̎��_�܂������c���s���܂����B�ٔ������Ɨ����Ď����F��┻�f���s���O��Ƃ��Ă̍ٔ��̉~���Ȑi�s�ɂ͏��L�����K�v�����A�����@���ɂ̂��Ƃ����ٔ��̐i�s�Ɠ����҂��Ȃ��̂����L���Ȃ̂��Ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@����@�G��
�������ɂ������ẮA�ō��قɜu�x�Ȃ��Ɉӌ���\�����邱�Ƃ��ł��A�����ƂƂ��ɁA�����̍ٔ����錠���̊g�[�Ɍ����ĉ^���������߂邱�Ƃ��ł���S�i�@�̑��݂ɂ��炽�߂Ċ��ӂ��Ă���B�h�s���̂Ƃ肭�݂�ʂ��āA�S�i�@�E�g�����̑������X�ɒb���悤�B
�@�q�R�@���t
�v���W�F�N�g�E�����o�[
�@������A���c�����A�͏�^�[�i�{���j�A�ΐ쏃�i���k�j�A�ē��T�L�i�����j�A����G���i�����j�A�吼��Ái�ߋE�j�A����h�u�i�����j�A�q�R���t�i��B�j�ȏ�A�h�̗�
|