|
全司法は、7月19~21日に第77回定期大会を開催し、向こう1年間の運動方針と財政方針を決定します。今年の大会は、新型コロナウイルスの感染拡大が私たちの暮らし、職場、活動に与えた影響を話し合い、これからの運動を考える重要な大会になります。要求前進、組織強化・拡大を全国一丸となってすすめるため、定期大会に向けて、職場からの積極的な討議を呼びかけます。
今号では、定期大会開催の意義や討論ポイントについて鳥井書記長に話を聞きました。
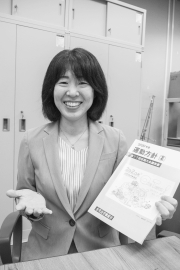 |
方針のポイントを語る
鳥井書記長 |
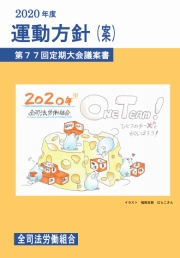 |
定期大会を「コロナ後」の活動再開の契機に
―コロナの不安がある中、大会を招集しましたね。
緊急事態宣言が段階的に解除され、経済や社会は徐々に再開の途を歩みだしました。まだまだ不安を感じている組合員の方もおられると思いますが、定期大会の招集は、社会活動を維持するための「政府のロードマップ」に沿った判断であると考えています。
この間、全司法の活動もコロナ禍の影響をまともに受けて、停滞を余儀なくされました。それを少しずつでも元の姿に戻していかなければなりません。全司法の活動再開の契機とするためにも、定期大会を招集することが必要だと考えました。
―延期や他の方法は考えられなかったのでしょうか。
大会は規約に定められた最高の議決機関であり、運動方針や予算の決定、役員の選出などの重要な役割を持った会議であることは言うまでもありません。加えて、全司法は最高裁に対し、国家公務員法に基づく職員団体登録を行っていますが、定期大会を毎年開催することを含めて、①規約に基づく組織運営を行い、②選挙によって役員を選出することが団体登録の要件となっています。全司法が、とりわけ最高裁との関係でこれまでどおりの活動を行うには、大会の開催が必要不可欠なのです。
オンラインによる方法や書面審議による方法も検討しましたが、議決権の行使や直接秘密投票による役員選挙が実施できるかなど、多岐にわたる課題を検討したうえの提案です。ご理解とご協力をお願いします。
―議案となる運動方針案は毎年かなりボリュームがありますよね。
この1年の社会の動き・裁判所の動きと、それに関しての全司法の考え方を説明しています。また、全司法の活動の報告と、今後の課題についても丁寧に記載しています。今年は議案書の内容もコロナ問題の影響を色濃く反映するものとなっています。シンプルで簡易なものも悪くはありませんが、大切なことを過不足なく記載し、組合員の皆さんにきちんと伝えるのも本部の役割だと思っています。
議案書を手にとっていただき、自分の職種にはどういう課題があるのか、民事裁判手続のIT化は今どういう動きになっているのか、超勤の上限規制が導入されて全国の職場はどうなっているのかなど、自分に関係のあるところや興味のあるところだけでも構わないので、目を通していただければと思います。読んでみれば「目からウロコ」な発見もあるんじゃないかな。そして、質問や意見・感想を、ぜひ各支部の代議員に託してください。
「これからの社会・これからの裁判所・これからの全司法」を考える大会に
―どういったことが今年の大会のポイントになりそうですか?
「これからの社会・これからの裁判所・これからの全司法」を考える大会になりそうな気がします。
新型コロナウイルスの感染拡大によるBCP発動・業務縮小態勢により、私たちの職場がどのような状況となったのか、職場実態を共有するとともに、職場をどのように元に戻していくのかを議論していく必要があります。コロナ後の社会は「コロナとの共存」とも言われていますが、裁判所内での感染を広げないための対策、登庁して執務にあたる職員の感染防止措置・健康管理・労働条件、在宅勤務を含む業務継続のあり方など、この間の動きやとりくみを総括し、当局に責任を果たさせることをはじめ、必要な対応を行う必要があります。
また、裁判手続のIT化がどんどん具体化しています。そうした動きや大量退職期を見据えて、最高裁が明らかにした「職員の今後の職務の方向性」では、「職員一人一人が本来の役割・職務に注力して専門性を活かすことのできる事務処理態勢を構築して、より活力のある組織を目指す」とした一方で、「退職者と同数の採用をし続けることの相当性についても改めて検討する」ことを明らかにしました。それを全司法としてどう評価し、どういう運動をしていくのか。皆さんと議論したいと思います。
―将来(これから)を語る、ということですね。
もちろん、現状においても解決しなければならない課題は職場に山積しています。そうした課題にもきちんと向き合う大会にしなければいけません。
人員シフト、超勤縮減、簡素化・効率化、パワハラ、宿日直等の問題解決を
―確かに本部には多くの悩みや要求が寄せられますね。
職場の繁忙度は増しているのに裁判所の定員は純減となり、とりわけ地方から東京及びその周辺の大規模庁への人員シフトが引き続き行われ、地方職場の負担や不満は非常に大きくなっています。適正迅速な裁判を実現するためにも、職員の休暇取得や健康管理の面にもきめ細かく配慮するためにも、人的手当や職場環境の整備が求められています。
超勤縮減に関しては、超勤の上限規制が導入されて1年がたちますが、正確な勤務実態の把握が管理職員の責任であるという認識は広がっておらず、「残業は減っているが、代わりに朝早く出てくる職員が増えている。でも朝の超過勤務は認められていない」との報告が寄せられています。
超勤縮減のためには、事務の簡素化・効率化をすすめていく必要がありますが、職場では裁判部・事務局ともに「適正化」やコンプライアンスが過度に強調されることで事務処理が煩雑になって硬直化し、事務量も増大する傾向にあります。
パワー・ハラスメント防止策については、人事院規則が制定されたことを受け、裁判所でも通達を改正しました。相談窓口の充実をはじめ今後措置される防止策を適切に運用させ、啓蒙や研修をより丁寧に行わせて、職場からハラスメントをなくさなければなりません。
宿日直の負担は都市部・地方部ともにどんどん大きくなっていますし、切実な異動要求を持っている組合員もたくさんいます。旅費などの自己負担も大きな問題です。そうした課題を全国で共有し、どのように解決していくのか、知恵を出し合いましょう。
組織拡大に向けて決意を固め合おう
―コロナの影響による業務縮小態勢のもと、組織的にも難しい状況になりました。
全司法は、コロナの状況下においても、動きを止めず、必要な活動は工夫しながらすすめることを基本に運動にとりくんできました。しかし、異動期・採用期をまたいで新型コロナウイルス感染防止対策が強化されたことから、新採用対策及び異動対策をはじめとする組織強化・拡大のとりくみに支障が生じ、組織拡大は思うようにすすんでいないのが現状です。
私たちの要求を実現させていくためにも組織拡大は極めて重要であるということは、皆さんも十分ご理解いただいていると思います。具体的な成功体験やうまくいかなかった反省を共有し、組織拡大・強化に向けて一層奮闘していく決意を固め合いましょう。
―活発な議論を期待したいですね。
意見を出すというと、本部提案に対する指摘や、「自分はこう思う」と主張するイメージが強いかもしれませんが、職場の実態や課題を共有することも大会の意義の一つです。本部方針を補強する立場からの発言や職場実態の報告でも構いませんので、多いに議論に参加してください。
全司法は、「組合員のどんな小さな要求も大切にして、みんなで解決を目指す」というスタンスで活動してきましたし、「みんなで決めて、みんなで実践すること(組合民主主義)」を貫いてきました。その現れが全国すべての支部からの代議員制による定期大会でもあります。私たちもそれを引き継ぎ、この大会も成功させましょう!
|