 |
|
一緒に「職場を作る」仲間になろう! |
| |
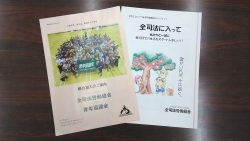 |
「君がいれば、手は届く」
新採用歓迎パンフとビラ |
4月の採用・異動を経て、多くの職場でメンバーが入れ替わったこの時期、全司法は4月異動を契機に一人でも多く仲間を増やしたいと考えています。新採用はもちろん異動された職員も対象に、ぜひ、職場みんなで声をかけあって、組合員の仲間を増やしましょう!
私たちが特にアピールしたいこと、それは、労働組合に入るということは「職場のルールを決める」一員になるということです。
裁判所の職場は公務の中でも「働きやすい職場」だと言われています。しかし、それはけっして、自然にできたものではありません。長年にわたって、全司法が職員の立場に立って当局に働きかけることで出来上がった、全司法の活動の「成果」なのです。
「正式な職員代表」として意見を述べる
最高裁長官は全司法について「信頼関係にもとづき、率直に問題意識をぶつけ合い、問題解決をはかっていく」関係だと表明しています。
このように、長年の運動の結果、全司法は裁判所当局から名実ともに正式な職員代表と認識されており、「意見を聞き、誠実に対応する」ことを約束されています。
全司法に加入しても不利益を受けないことはもちろん、当局は全司法を「敬意を表する」相手として受け止めているのです。
これを足がかりに、私たちは様々な課題で要求や意見を当局に出し、「職場のルールを決める」仕組みを作っています。
職場の人員配置に要求を反映し、世論を作る
各職場の人員配置は、基本的に毎年4月に決められますが、最高裁は国の予算状況や事件動向をもとにしつつ、全司法の要望も「十分に踏まえて検討する」としています。
あわせて、全司法では「全司法大運動」等によって、裁判所の人的・物的充実と裁判所予算の拡充に向けた世論を作り、国会に直接働きかけるとりくみを行っています。
こうしたとりくみの結果、職場実態からすると、まだまだ不十分ではありますが、全国的には、書記官を中心に一定数の人員を確保させる成果を勝ち取っています。
「サービス残業があってはならない」を基礎に
長時間労働が社会問題になっていますが、全司法は超勤縮減とサービス残業根絶の課題を継続して交渉でとりあげ、大きな到達点を築いています。
とりわけ、「サービス残業や持ち帰り仕事については、あってはならない」との最高裁の回答は重要で、超過勤務手当が全額きちんと支給されるルールを作らせるとともに、民間企業はもとより、他の行政府省でもサービス残業が蔓延している職場状況と対比して、裁判所を働きやすい職場にしてきました。
一方、この課題は、常に職場実態を点検し、繰り返し交渉を続けていかなければ、すぐに「絵に描いた餅」になっていく課題でもあります。そうした意味でも、今後とも、全司法の役割が重要です。
また、休暇取得をはじめ、時差通勤庁やフレックスタイム制などについても、全司法が意見を反映させることで、裁判所の職場に合った運用をさせることができています。
人事評価、再任用など、裁判所に見合った制度に
2007年に国家公務員に人事評価制度が導入されるにあたって、裁判所組織の特殊性、裁判所職員の職務の特性をふまえた制度を作らせました。とりわけ「行政府省のように目標管理的な手法は採らない」とさせたことは、「目標と課題」をノルマにさせず、仮に目標が達成できなくても、仕事ぶりを見て、頑張っていれば評価する仕組みにしたということであり、きわめて大きな成果です。
また、再任用制度については、原則として希望者全員が、フルタイムで再任用される運用が行われています。これは他の行政府省では未だに実現していない到達点です。
「女性が働きやすい職場」を作ってきた
「女性の活躍」が言われる時代になり、今では国の政策として「女性の採用・登用拡大」が行われていますが、全司法はずっと以前から、女性差別をなくし、母性保護の権利を保障し、管理職を希望する女性がきちんと登用される仕組みを作るよう、とりくみをすすめてきました。「女性が働きやすい裁判所の職場」は一朝一夕にできたのではなく、こうした運動の積み重ねで作られてきたものです。
休暇に関する制度の解説と概要等を取りまとめた「出産・育児・介護に関する休暇及び休業制度ハンドブック」は、こうした運動の中で、全司法の要求を受けて最高裁が作成したものですし、当局が育児休業の代替要員確保に努力するのも、全司法との交渉結果をふまえたものです。
「国民のための裁判所」の期待を受けて
全司法が職場の労働条件改善とともに「国民のための裁判所」実現という方針を掲げ、そのために様々な団体・個人と一緒に運動する立場をとっていることも、「職場のルール」づくりの上で重要です。とりわけ、この国の平和や民主主義を守っていくうえで「裁判所で唯一の労働組合」に対する外部からの期待は、私たちが思っている以上に強いことをあわせて指摘しておきたいと思います。
「働きやすい職場」を守るために
その他、全司法が関わって作られてきた「職場のルール」は挙げればキリがありません。
こうしてできあがった「働きやすい職場」ですが、将来に向けてこれを守っていくことも、全司法の運動なしにはできません。
日本全体の労働環境が悪化していくもとで、労働組合がないか、あっても機能しない職場は、どんどん「ブラック化」していきます。それを食い止め、働きやすい職場を守ることができるのは、やはり労働組合だけであり、裁判所で言えば、できるだけ多くのみなさんが、全司法に加入し、とりくみに参加することにあります。
そうした力をもっと大きくするためにも、ぜひ、この4月、組合員の仲間を増やしましょう!
|