|
5月15~16日、第22回全司法中央労働学校を熱海で開催しました。全国から51名が参加し、情勢、理論、運動の三つの分野での講演を聞き、グループ討議で理解を深めるとともに、地連・支部を越えた交流の機会となりました。
 |
| 青年若手が数多く参加 |
 |
| 講師の石川康宏さん |
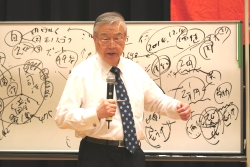 |
| 講師の中田進さん |
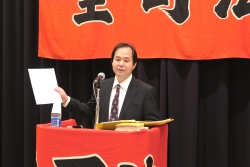 |
| 講師の中矢委員長 |
国民がようやく、憲法の意義にたどり着いた
石川康宏さん(神戸女学院大学教授)の情勢の講演では、安倍政権が改憲をめざすもとで、2012年に自民党が発表している「日本国憲法改正草案」が、「日本を国民が権力を制御する立憲主義の国から、権力が国民を従属させる抑圧の国へ変えること」を目的とし、(1)天皇中心の復古主義の国へ、(2)アメリカとの共同戦争ができる国へ、(3)国民が自己・家族責任で生きる国へ、(4)「おこぼれ」経済運営を国是に、(5)権力への批判を許さぬ国へ、という特徴を持っていることを解説して「内容を知れば多くの人は賛成しがたい、よく学び、広く知らせることが必要」だと強調しました。
一方、日本国憲法が、不戦や社会権の保障といった世界史の流れの中で作られた「世界史の先端をいく憲法」であることを明らかにし、「日本国民の憲法の理解が十分でなく、これに追いつく努力が必要だ」としたうえで、昨年以来の戦争法廃止の動きとともに広がっている「2015安保」市民運動について、「日本の国民・市民は、世界政治の近現代的発展をようやく自らの力で達成するところまでたどりついた」として、その歴史的意義を評価しました。
また、市民運動の中でのSEALDsのとりくみに触れて、「自分の言葉で話すこと」「『見え方』に徹底的に気を配ること」という特徴をあげ、「労働組合運動も彼らから学ぶべきところが多い」と指摘しました。
賃金は「労働力の対価」、生活費で決まる
中田進さん(関西勤労協講師)は、軽妙な語り口と参加者とのキャッチボールを通じて理解を深めていくスタイルの講義で参加者の笑いを誘いながら、「賃金は労働(成果)ではなく、『労働力』(働くことができる力)に対して、その使用料として支払われている」「『労働力』の価値は生活費であり、賃金は本人の生活費、家族の生活費、仕事をする力を身につけるための費用を基本に、労使の力関係で決まる」「労働者には賃金を受け取る権利がある」といった、労働組合の基礎理論となる賃金についての考え方を、わかりやすく解明しました。
全司法は一つ
中矢正晴中央執行委員長は昨年に引き続いて全司法の歴史について講演。「1980年代以降の全司法の歴史と運動について」と題して、労働戦線の統一(全労連・連合の結成に至る経過)、3・18事務総長見解、司法制度改革、公務員制度改革などに触れ、様々な問題に直面した時に、「全司法は一つ」を合言葉に全司法がどのように意思統一し、合意形成の努力をしてきたのかという話を軸にしながら、今の裁判所の仕事や全司法の運動につながるとりくみの経過を説明しました。
参加者の感想
講演(1)
「安倍改憲の道か、日本国憲法の道か」
最近話題になっていることの問題点や、なぜ問題になるのかということを分かりやすく解説していただけたので素直に入ってきました。今の憲法と(自民党の)改正案との比較をここまで見やすい形で教えていただいたのは初めてだったため、自分でも勉強してみようという意欲がわきました。(東北地連)
☆
今まで、憲法改正について問題があることは分かっていたつもりだったのですが、講義をお聞きしたことで、確信に変わりました。正直なところ、勉強不足だったところもあり、自民党とは何か?など政治背景を知ることで、自分たちの都合のよいことばかりを憲法に入れて(都合の悪いことは消す)国民の為に考えているわけではないなと今回知ることが出来ました。権力をしばる為にあるものを権力者がつかいやすいように都合良く変えちゃダメですね。(近畿地連)
講演(2)
「経済のしくみと賃金の基礎理論」
「賃金=生活費」という考え方は初めてきいたもので大変勉強になった。成果主義の問題点を考える上で重要だと思った。講演の内容も大変おもしろかった。(北海道地連)
☆
「労働力」という発想がなかったので、仕組みを聞いても最初は、なぜ利益が出るのか不思議な気分だった。こういった仕組みの理解が広がれば、賃金に対する関心が高まり、意見交換、主張ができると思う。(中国地連)
講演(3)
「1980年代以降の全司法の歴史と運動について」
自分が生まれた頃からの社会情勢と裁判所、組合の活動を見直すことで、職員制度など、根幹となっている部分を知ることができ、有意義な講演でした。(東京地連)
☆
全司法は裁判所に一つしかないとの言葉がすごく印象に残りました。今後、裁判所は、山あり谷ありを歩むとしても、何がおきても全司法が前に立って、たたかい、道を切り開いていく必要があるので、自分がその道を作っていく側になれればと思いました。(中部地連)
☆
今日の職場環境があるのは、これまでの先輩方の活動の結果だということをあらためて実感しました。そのことを知らない若手職員が多いので、もっと伝えていく必要があると思いました。(九州地連)
|