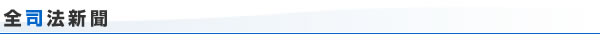 |
| |
|
|
職場から一声かけ 加入のチャンスをプレゼントしよう |
|
| |
|
10月1日、全国各地の裁判所で、およそ60名の職員が新たに採用されました。各支部では、青年等を中心に歓迎会やガイダンス等が開催され、全司法への加入がすすんでいます。採用から1か月近く経過した新採用職員に対して、職場や仕事の様子を聞くとともに、全司法に加入するチャンス(機会)をプレゼントしましょう。
全国6支部で全員加入
本年10月に採用された職員は、全国で60名近くにのぼります。全国各地の裁判所で、支部や青年部を中心に歓迎会やガイダンス等が開催され、労働組合の説明や全司法への加入の呼びかけ等が実施されています。
この間、採用から1か月あまりですが、既に6つの支部では、新採用職員全員が全司法に加入されました。
前の職場はブラックだった
年度途中の採用者の中には前職のある方もいます。転職され、全司法に加入された方からは、「前の職場はブラックだった。夜遅くまで働いても、残業代なんて出なかったし、有給休暇があっても取れなかった。あのまま働き続けていたら…」というような声も聞きます。
一方で、「裁判所は前の職場よりも働きやすいと思う。だけど、ひとつひとつとってみるとやっぱりおかしいのではないかと思うこともある」との声も聞こえます。
「働きやすい職場のままがいい」「おかしなルールは改善していきたい」との思いで全司法に加入された方もいます。
最高裁は「サービス残業はあってはならない」と交渉で回答し、超過勤務を行った場合は必ず手当が支給されることになっています。また、全司法は超勤縮減と年次休暇を取得しやすい職場環境の整備を求めて運動をしています。
身近な新採用者の声を聞こう
新採用職員が全司法に加入する理由は様々です。例えば、「いろんな人と出会いたい」「困った時に助けてもらいたい」などです。
その悩みや思いに応えるために、まずは職場から一声かけ、話を聞いてみましょう。
もちろん、一声かけるのは、全司法に既に加入している方に対しても同様です。裁判所に採用されてからしばらく経って、いろんな悩みや思いが生まれてきている人もいるはずです。
同じ職場に、または身近な職場に最近採用された方がいる場合は、ぜひ一声かけて話を聞いてみてください。新たな要求や加入のきっかけになるかもしれません。
加入は「権利」 プレゼントしよう
労働組合に加入することは憲法や法律で定められた「権利」です。まずは、新たに職員になられた方々に加入の「チャンス(機会)」をプレゼントすることからはじめましょう。
|
| |
 |
| |
|
超勤縮減、評価制度など今後につながる回答
〜秋年期第1回給与課長交渉 |
|
| |
 |
|
給与課長との交渉に臨む全司法本部 |
全司法本部は、10月13日、最高裁春名給与課長と秋季年末闘争期の第1回交渉を実施しました。超過勤務縮減や「フレックスタイム制」などに関わる労働時間、IT情報システム化、10月から実施されている見直し後の人事評価制度、宿日直事務の負担軽減などの課題で要求を主張し、今後の検討につながる回答を引き出しました。
【超勤縮減・労働時間】
フレックスタイム制
職務の特性や組織の特殊性を踏まえ、対応を検討
「超過勤務の縮減をすすめるに当たってサービス残業や持ち帰り仕事が生じることのないよう、より一層下級裁を指導していきたい」「今後とも、管理職員が部下職員の事務処理状況等をきめ細かく見て、職場実態に合った事務の簡素化、合理化に向けた具体的な方策を講じるよう指導を徹底していきたい」との基本姿勢を維持しました。また、繁忙である家裁については「適正かつ迅速な処理を図るため、事務量に見合った人員配置の観点から書記官を中心に大幅な増配置がされてきているほか、各庁において合理的な事務処理の推進や事務の簡素化等のとりくみがされてきている」、事務局については「事務手続きの見直しやIT化などにより、従前から事務処理の簡素化、効率化をはかってきており、『超過勤務縮減のための取組事例集(四訂版)』を活用するなどして、各庁各部署の実情に応じたとりくみがされている」との認識を示しました。
7〜8月に一部の職場で実施・試行された朝型勤務については「次年度については、現在取りまとめている裁判所における今年度の朝型勤務の実績等の結果や行政府省の動向を踏まえ、裁判所における対応についての検討をすすめる必要がある」と回答、また、「フレックスタイム制」の導入に関わっては「各行政府省における検討状況等について情報の入手に努めるとともに、裁判所の職務の特性や組織の特殊性を踏まえ、裁判所における対応についての検討をすすめる必要がある」との姿勢を示しました。
【IT情報システム化】
裁判所の意見や要望等は主管する省庁に伝える
各府省共通システムの導入スケジュールの延期や運用上の不具合が、かえって事務処理に支障を来し事務改善と逆行している実態を踏まえた追及に対し、最高裁は「主管する省庁に裁判所の意見や要望等は引き続き伝えていくこととしたい」との姿勢を示しました。また、従来行ってきた業務との関連性を丁寧に説明するような裁判所独自のマニュアルの作成を求めたところ、「SEABISの物品調達システムについては、購入と供用に関する操作については個別の操作マニュアルを作成して各庁に配布を行ったところであるが、操作上の疑問があれば職制を通じて質問するようにしていただきたい」と回答しました。
インターネット接続を一部制限する措置に関して、最高裁は10月8日に暫定インターネット閲覧用パソコン(閲覧用PC)を整備することを明らかにしましたが、同措置が当分の間継続すること、閲覧用PCの整備台数が職場実態からすると十分ではないことから、さらなる増設を求めました。
【人事評価制度】
評価者の評価能力、面談技法の向上を図りたい
評価者訓練の充実等に向けては「新たに管理職員になる職員も含めて評価者の評価能力、面談技法の向上を図りたい」と回答しました。また、10月からの職員カードによる評価と人事評価シートによる評価の統合により、人材育成の目的が後退しないよう求めたのに対し「OJT担当者とその上司等の間でも十分な意見交換を行い、必要な情報提供を図ることにより、計画的かつ継続的なとりくみが組織的に実践されるものと考えており、評価が統合されても裁判所における人材育成が後退することはないものと考えている」と回答しました。
【宿日直】
連絡係職員に待機義務は生じない。外出など制約されない
裁判官の「泊まり込み・登庁」実施庁の拡大の要求に対し、給与課長は、本年4月から広島地裁本庁が希望により泊まり込む体制から裁判官全員が宿泊する態勢に変更したことをあらためて回答し、本年10月1日現在で、裁判官が宿泊する態勢をとっている庁が13庁、希望により泊まり込む庁が12庁あることを明らかにしました。
また、連絡員体制の導入や運用に当たって、対応する支部の意見を十分聞くよう下級裁への指導を求めたことに対し「連絡係職員の待機義務が生じるものではなく、待機義務がない以上、外出はもとより、食事、入浴、休息又は睡眠等についても制約されているわけでもない」「待機義務に関し、そのような要望があったことは、受け止めたい」と回答しました。
|
 |
| |
|
|
|
| |
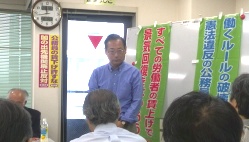 |
|
決意表明で会場を沸かせた本藤さん |
「公務員賃下げ違憲訴訟」の第2回口頭弁論が10月14日に東京高裁で開かれました。
国公労連は傍聴行動とともに東京高裁前要求行動と報告集会を展開し、全司法は原告2名を含め、本部と東京地連でとりくみに結集しました。
片山元大臣などの証人尋問は必要
弁論では控訴人代理人2名が証人採用の必要性について意見を述べました。
佐渡島弁護士は「一審判決や被控訴人(国)は、公債発行残高が700兆円前後であることや公債依存度が50%前後であることを理由に、国の財政事情が悪化していると評価している。しかし、国の財政事情については国債金利で判断すべきであり、日本の国債金利は超低金利であることから、我が国の財政事情は給与減額の必要性が認められるほどには悪化していない」と主張しました。
また、野本弁護士は、片山元総務大臣が国会審議の中で、公務員の賃下げを行う場合は「労働基本権の回復の問題は避けて通れない問題だ」と発言していること、一審で平山元人事・恩給局次長が「人事院勧告尊重を前提に賃下げを検討していた」と証言しているが、元大臣の国会等での発言と食い違っていること等を指摘して、元大臣の尋問が必要であると主張しました。
控訴人が申請している片山元総務大臣などの証人の採否は、今回は行われず、次回期日は2月15日10時30分に指定されました。
『労働者は黙っていない』姿勢を鮮明に
口頭弁論後の報告集会では、代理人の加藤弁護士から「賃下げ違憲訴訟は憲法論であり、控訴審では地裁判決の誤りや論理矛盾を明らかにしていく。とりわけ、人事院をなくす法案が出ていたにも関わらず、一審判決で政府が人勧尊重という立場に立っていたと認定したこと、国の財政事情の悪化のもとで東日本大震災復興財源の確保のためだったということ、この二つの大ウソを明らかにしていきたい。『労働者は黙っていない』姿勢を鮮明にし、公正な審理が尽くされるよう全力をあげよう」と述べました。
また、各単組からの決意表明では、原告の中から全司法立川支部の本藤幸一副委員長が発言し、「憲法違反の公務員賃下げは許せない。憲法尊重擁護義務を負う国家公務員労働者として、憲法を守る運動に積極的にかかわっていく」と決意を述べました。
集会の最後に、鎌田国公労連書記長から「公正判決を求める署名」や宣伝行動などの行動強化と、この裁判を2016年春闘や「まもろう憲法・国公大運動」の中で位置づけてたたかうことが提起され、確認されました。
|
 |
| |
|
|
|
| |
|
21年目となる2015年度の「全司法大運動」がスタートします。「国民のための裁判所」実現をめざし、裁判所予算の拡充や定員の獲得に向けた継続的なとりくみであり、職場諸要求実現や組織強化拡大と並ぶ全司法の中心的なとりくみの一つです。
高まる全司法大運動の重要性
社会経済の状況が大きく変化する中で、裁判所に持ち込まれる事件は複雑困難化し、事件処理においてもより高い専門性が求められています。社会的注目を集める事件の係属が相次ぐ中、これらの事件処理についても適正・迅速化の要請が日ごとに強まっています。
職場では、家族構成の変化や高齢化社会の進展などを背景に、家事事件を中心に事件数が増加し、家裁の繁忙状況が顕著になっています。同時に、地簡裁からの人員シフトも限界となっているとともに、事務局の恒常的な繁忙状況も依然解消されていません。
こうした状況のもと、国民の負託に応え、適正・迅速な裁判を実現するためには、裁判所の更なる人的・物的充実が必要となっています。そのためには何より、国家予算全体の0・32%にとどまる裁判所予算の拡充が必要であり、裁判所の人的・物的充実を求める全司法大運動の重要性はこれまで以上に高まっています。
|
衆議院
自民党
柴山 昌彦
若狭 勝
公明党
漆原 良夫
大口 善徳
遠山 清彦
民主党
階 猛
横路 孝弘
柚木 道義
共産党
穀田 恵二
志位 和夫
赤嶺 政賢
塩川 鉄也
笠井 亮
高橋千鶴子
宮本 岳志
池内さおり
梅村さえこ
大平 喜信
斉藤 和子
清水 忠史
島津 幸広
田村 貴昭
畑野 君枝
畠山 和也
藤野 保史
堀内 照文
真島 省三
宮本 徹
本村 伸子
|
参議院
自民党
三宅 伸吾
公明党
矢倉 克夫
民主党
江田 五月
前川 清成
有田 芳生
共産党
山下 芳生
市田 忠義
小池 晃
大門実紀史
井上 哲士
紙 智子
仁比 聡平
田村 智子
倉林 明子
吉良よし子
辰巳孝太郎
|
|
|
2014年度年度全司法大運動 請願署名紹介議員 |
採択されれば国会の総意
全司法大運動の署名は憲法第16条で保障された請願権に基づく国会請願署名です。署名は、紹介議員を通じて国会に提出し、国会で採択されれば、請願内容が内閣へ送付され、政府や裁判所当局は請願事項について誠実に処理する義務を負うことになります。
国会請願の採択は「全会派一致」が原則であるため、国会で採択されることは文字どおり「国会の総意」となります。ここに、全司法大運動が果たす大きな意義と役割があります。
毎年多くの請願が国会に提出される中で、採択されるのはわずか数件となっており、その中でも裁判所の人的・物的充実を求める請願は毎年採択を勝ち取っています。また、先の第189通常国会においては、衆参あわせて昨年度を超える45名の紹介議員を得ることができました。これらは、私たちが求める裁判所の人的・物的充実の必要性について、国会内で確実に理解と共感が広がっていることの証左であり、与党である自民党、公明党からも紹介議員を得ることができていることからも窺えます。
こうした運動の積み上げによって、他省庁では大幅定員削減や新採抑制が強行される中においても、裁判所ではわずかな減員にとどめ、裁判官・書記官では一定の増員がはかられていることにもつながっています。
一筆でも多く、国民世論の形成を
これらの情勢のもと、全司法大運動は「数の追求」と「広範な世論形成」を2本柱にとりくみをすすめていきます。国会で採択を得るためには、衆参両院で法務委員を選出するすべての政党・会派の賛同を得る必要があります。そのためには、より多くの署名を集めることが重要です。今年度も1人20筆を目標に集約することを提起しています。まずは職場内で、職員全員とその家族、友人などから署名を取り切る運動をさらに大きく広げましょう。
また、街頭での宣伝や各種集会等での対話により、国民の理解と共感を広げながら、一筆でも多くの集約をめざすと同時に、国民世論の形成にも努めていきます。全国一丸となった運動で、今年度も請願採択を勝ち取りましょう。
|
 |
| |
|
|
|
| |
|
これまで、わたしたち裁判所職員は、国家公務員共済年金に加入していましたが、被用者年金制度の一元化により、本年10月から厚生年金に加入することになりました。
ポイントは、(1)国家公務員も厚生年金の被保険者(加入者)となる、(2)共済年金の保険料が厚生年金の保険料と統一される、(3)共済年金の3階部分(職域部分)が廃止され、新たに「年金払い退職給付」が創設される、の3点です。
【これまでの制度】
我が国の年金制度は、全国民共通の国民年金による基礎年金を土台(1階部分)として、民間被用者には厚生年金制度が適用され、国家・地方公務員及び私学教職員には共済年金制度が適用されていました(2階部分)。さらに、民間被用者には企業によっては企業年金が、また、共済年金には職域年金制度が存在していました(3階部分)。
この職域年金は、共済年金制度が公的年金制度としての性格を持っていると同時に、公務員制度の一環としての性格を持っているため、公務の能率的運営に資する観点から、公務員の身分上の制約等の特殊な立場を考え、公務員の退職後の生活の安定に寄与する目的で昭和60年に創設されたものです。民間の企業年金がかなり普及している点も考慮して設計されているといわれています。
【なぜ一元化されたのか?】
民間被用者には厚生年金制度、国家・地方公務員及び私学教職員には共済年金制度が適用され、両者の間には制度的な差異や保険料の高低がありました。「今後の少子高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間サラリーマンや公務員を通じ、同じ保険料を負担し、同じ年金支給を受けるという年金制度の公平性を確保することにより、公的年金に対する国民の信頼を高めるため、被用者年金制度の一元化を行う」とするのが政府の説明ですが、実際には、そもそもの制度の違いを無視して「公務員は優遇されている」という主張がマスコミ等を通じて展開された「公務員バッシング」が背景にあります。
【一元化後】
共済年金から厚生年金に移行したことにより、今後の年金制度は国民年金制度の基礎年金部分を1階部分とし、2階部分は厚生年金制度となり、3階部分(職域部分)は廃止されることとなりました。
なお、廃止される職域部分は、(1)施行日(10月1日)前に年金権を有する人や、(2)施行日前の加入期間を有する人に対しては、施行日以降においても、加入期間に応じた職域部分が支給されることとなります。
【年金払い退職給付】
一方、一元化に向けて設置された有識者会議では、「公務の特殊性に配慮した公務員制度の一環としての年金」とすること等とした報告書が取りまとめられました。また、人事院からは「国家公務員の退職給付が終身年金の共済職域と退職手当から構成され、服務規律の維持等の面から重要な意義を果たしてきた経緯や、民間では企業年金を有する企業が過半を占めていることを考慮した対応が必要」などといった見解が示されました。
これらを踏まえ、新たな「年金払い退職給付」が公務員制度の一環として設けられることになりました。なお、その財源は新たに積み立てていくため、本年10月からは長期掛金に加えて、年金払い退職給付に係る掛金の徴収が始まりました。
|