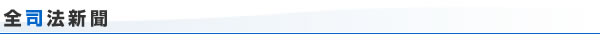 |
| |
|
「職場に根ざした活動」で全司法の再生・継承を!
全司法第71回定期大会 |
|
| |
|
全司法は、7月21日から23日、静岡県伊東市において、「職場に根ざした運動と総対話で仲間の輪を広げよう〜一人ひとりが要求実現、組織拡大の担い手に〜」をメインスローガンに、110名参加のもとで第71回定期大会を開催しました。国民生活を犠牲にし、「戦争できる国」づくりを進める安倍政権下での情勢をふまえ、要求課題や組織課題などについて活発な討論を展開し、向こう1年間のとりくみの方針と中央執行体制を確立しました。とりわけ、今大会は「『職場に根ざした労働組合』としての全司法の存在意義を確認し、その再生と承継の決意を固めた大会」となりました。
大量退職期見据え着実なとりくみを
 |
|
すべての議案について圧倒的多数で可決 |
 |
大会をリードした議長団
(愛知・水野代議員、大阪・中本代議員) |
 |
|
大会宣言を提案する坂本代議員(沖縄) |
 |
|
退任役員のあいさつ |
大会は、議長に愛知支部水野茂幸代議員と大阪支部中本千里代議員を選出して始まりました。
門田中央執行委員長のあいさつの後、来賓として、国公労連の川村中央執行副委員長、全法務の実川中央執行委員長、裁判所退職者の会全国連合会の石山会長より、熱のこもった激励と連帯のあいさつを受けました。
本部からは、2014年度運動方針案(第1号議案)及び財政関係の報告・提案がありました。運動方針の提案の中で阿部書記長は「早い地域では5年後、全国的に見て7〜8年後から大量退職・大量採用の時代が始まる」と分析し、その時期を目標に全司法の組織と運動を継承・発展させるためのとりくみを始めることを提起し、「全司法組織強化・拡大プロジェクト」に基づくとりくみを着実に、前にすすめることが大切だと強調しました。
大会1日目の終わりには青年協の浜田事務局長から青年協の活動報告があり、8月30〜31日の友好祭典成功に向けた決意が示されるとともに、青年の学習活動への先輩組合員の協力が呼びかけられました。
「職場に根ざした」活動の原点に戻って
討論は2日目から3日目の午前中まで続けられ、代議員・オブザーバーから延べ100(文書発言1名含む)の発言がありました。本部への意見や要望のほか、各支部におけるとりくみの実情報告や次年度への決意なども積極的に発言され、本部方針が豊かに補強されました。
なかでも、職場から出された要求や職場で起きた問題をきちんと取り上げ、その解決のために努力している発言が多かったことが特徴で、「職場に根差した労働組合」の原点に戻って、要求実現のために奮闘しようという方向性が全国的なものになりつつある状況が示されました。
討論終了後、阿部書記長が総括答弁を行い、「労働組合としてやるべきことはすべてやるということ、要求実現と組織の強化・拡大の課題を一体のものとして捉えとりくむこと、互いが互いを思いやり、困った人を見過ごさず、全司法が職場に見えるとりくみを行い、要求の前進、組織の拡大に向けて、それぞれの持ち場で、お互いに力を尽くす決意を固めあうこと」が呼びかけられました。
引き続いて行われた採決では、すべての議案が可決されました。
書記次長に井上氏、青年協議長候補に山本氏 国公派遣に豊田氏を選出
3日目の午後から行われた役員選挙では、立候補者全員が信任されました。本部専従役員では、齊藤書記次長、花岡中央執行委員(国公労連派遣)が退任し、井上弘樹氏(愛知)が書記次長に、豊田勝利氏(京都)が国公労連派遣の中央執行委員に、山本一樹氏(大阪)が青年協議長候補の中央執行委員にそれぞれ選出されました。
また、永年組合員表彰、機関紙コンクールの表彰、全司法大運動署名の表彰も行い、3本の決議と大会宣言を採択しました。
全司法の歴史と活動を踏まえ、「全司法組織強化・拡大プロジェクトを『全司法再生の方針』として実践していこう」と呼びかける中矢副委員長の閉会あいさつの後、門田委員長による「団結ガンバロー」で大会を閉会しました。
大会期間中には、(1)「全厚生闘争団を支える会」個人加入の呼びかけを行い、13口の加入が、(2)青年友好祭典2014に向けた物品販売にとりくんで、55、400円の収益が、(3)人事院あて「怒りの寄せ書き」にとりくみ、36筆の集約がありました。
なお、今回の大会には本部役員を含めて女性が17名参加し、近年では最も女性の参加者が多い大会となりました。
 |
|
「団結ガンバロー」で大会締めくくり |
|
| |
 |
| |
|
総括答弁(要旨)
一人ひとりの心に寄り添い、要求実現に努力する姿で職場の信頼を勝ち取ろう |
|
| |
 |
|
総括答弁する阿部書記長 |
【情勢】
アベノミクスの「成長戦略」の名の下、安倍首相は労働者保護のための様々な規制を取り払い、労働法制の改悪をすすめている。現在の深刻な労働の実態を招いたのは、財界・大企業が唱える「新自由主義」と政府の「構造改革」路線であることは明白であり、今こそ企業の社会的責任を果たさせ、誰もが安心して働き続けられる社会への転換が求められている。民間の労働破壊はいずれ公務の職場にも持ち込まれかねない大きな問題であり、民間の仲間と一緒に反対の運動を構築していく必要がある。
【司研運動】
職場の身近なテーマを取り上げ、目的意識的に議論していくことは、より良い仕事のあり方を模索するとともに、職場に全司法の存在感をアピールすることにもつながる。司法の民主化と「国民のための裁判所」実現をめざすには、裁判所内外の様々な意見を聞き、改善に向けどのようなとりくみができるか、日常活動の中で検討していくことが必要である。
【全司法大運動】
職場での署名集約をはじめ、外部団体や地域にも足を出し、署名数の向上と国民世論形成をめざし奮闘することを全体で確認したい。また、長年のとりくみが法務委員を中心とした国会議員の理解と共感につながり、多くの紹介議員の獲得に至っている。今後も地元・中央での議員要請行動を継続するとともに、とりくみの広がりを作っていきたい。
【賃金引き上げのとりくみ】
今夏の人勧では、公務員賃金の改善とともに「給与制度の総合的見直し」が焦点となっている。8月初旬の人勧まで、その問題点を指摘しながら、最後まであきらめずにたたかう決意を固め合いたい。
【賃下げ違憲訴訟】
「賃下げ違憲訴訟」のとりくみは、単に一時的な賃金カットだけでなく、今後の私たちの働くルールにも関わる大きな問題。とりくみの意義を職場にも呼びかけ、今後提起される行動に積極的に結集していきたい。また、判決日が10月30日に指定されたことを踏まえ、判決後に全司法として配置する原告団会議に、原告の積極的な結集を呼びかけていただきたい。
【震災からの復興支援】
震災復興が遅々としてすすまず、まだまだ時間もかかることから、本部としては引き続き、震災復興支援のための東北物産品販売を継続していきたい。震災を風化させることなく、今後も被災地に心を寄せてとりくんでいくことが大事であることを強調しておきたい。
【少年法の理念をいかすとりくみ】
第186通常国会で、検察官関与の拡大や法定刑引き上げ等の内容を含む少年法「改正」法が成立した。「少年の健全育成」理念とは反対の方向で「改正」されたことは遺憾だが、当面とりくむべき課題なども見極めながら、少年法対策会議の開催を検討していきたい。
【憲法と平和、民主主義】
安倍政権の解釈改憲の動きに対して、私たち公務員には憲法遵守義務があり、まして裁判所は憲法を解釈する権限を持つ唯一の国家機関であり、裁判所で働く私たちにとって政府の勝手な憲法解釈を認めることはできないことから、反対の立場で運動を強めていく必要がある。また、安倍政権がすすめる「戦争できる国づくり」に反比例して国民・労働者の生活や雇用は切り崩されており、組合員とその家族の生活を守る役割を担う労働組合として見過ごすわけにはいかない。職場でのオープンな議論を保障しつつ、こうした立場からの運動を強めていく必要がある。
【社保・共済】
裁判所共済運営審議会で、全司法推薦の運審委員が半数(5名)を占めていることを踏まえ、事業計画に対する要望事項のとりまとめ等にも積極的にとりくみ、意見反映を強める必要がある。また、学習会への講師派遣要請等には本部としても積極的に応じていきたいし、支部視察の際には運審委員を活用した事前の座談会などで、学習や理解を深めてもらいたい。
【職場諸要求】
増員課題に関して、政府が「新たな定員合理化計画」を打ち出し、最高裁も協力姿勢を崩していないことから、職場の繁忙度に反して今後さらに厳しさが増すことが予想される。各級機関においても秋の交渉に向け、具体的な職場名を挙げながら追及を強めてもらいたい。
増員が厳しい情勢の下、職員の健康保持やワーク・ライフ・バランス実現の面から、超勤縮減は非常に重要な課題となっている。労使ともにとりくんでいかなければならない課題であり、組合としても真正面からとりくんでいかなければならない課題であることを指摘しておきたい。
宿日直廃止・縮小のとりくみでは、「宿日直制度の見直しを求める提言(第52回定期大会決定)」を見直す時期に来ているのではないかとの発言があった。現在まで宿日直および連絡員の廃止が一定すすんできたものの、これ以上の廃止・縮小については頭打ちの状態となっていることも踏まえ、同「提言」の見直しをはかることも含め、今後検討していきたい。
【男女平等実現のとりくみ】
政府の女性登用拡大推進計画のもと、裁判所でも採用・登用拡大計画が策定され外形的な枠組みは整いつつあるが、女性が管理職に登用される場合の環境整備が追いついていない実態もあることから、当局への追及や意見交換を強めていくことが求められる。また、女性の権利向上ばかりがクローズアップされがちだが、男女ともに働きやすい職場環境へと改善していく視点が大事であり、男女で利害が対立する構図を作るのではなく、お互いに協力できるところは協力していく意識でとりくむことが重要である。
【組織】
組織強化・拡大に向けた本部の考え方のエッセンスは、中央委員会で確立した「全司法組織強化・拡大プロジェクト」に込められている。同プロジェクトの3つの実践の柱((1)日常活動の充実・強化、(2)職場・階層で核となる組合員の育成、(3)体系的な学習の強化)を意識してとりくまなければ組合員拡大には結びつかないということを改めて指摘しておきたい。
また、日常活動を充実させ職場に全司法の存在感を示さない限りは、職場からの信頼も勝ち取れない。職場に全司法の存在をアピールし、職場に根ざしたとりくみを地道に粘り強く続けていくことが求められる。一人ひとりの心に寄り添い、要求実現に向け努力する全司法の姿を、職場にしっかり見せていくことが重要である。
【まとめ】
労働組合として「やるべきことはすべてやる」ということ、要求実現と組織の強化・拡大の課題を一体のものとしてとりくみ、互いが互いを思いやり、困った人を見過ごさず、全司法が職場に見えるとりくみを行い、要求の前進、組織の拡大に向けて、それぞれの持ち場でお互いに力を尽くす決意を固め合い、がんばっていこう。
|
| |
 |
| |
|
|
|
| |
|
全司法機関紙コンクール総評
日本機関紙協会常任理事 桜井 輝治
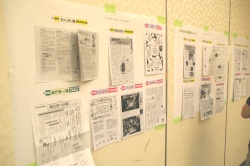 |
| きかんしコンクール入賞作を掲示 |
今年の全司法機関紙コンクールは、昨年を大幅に上回る34紙の参加でした。それでもまだ発行されていて未参加の機関紙も多くあるようです。全司法の機関紙活動の現在と課題を明らかにするためにも、年数回しか発行できなかったという機関紙もこのコンクールには参加していただきたいと思います。
今年の特徴点と課題について述べます。全司法の機関紙は各支部それぞれ形も内容も異なり、個性的に発行されているのが「全司法の良さ」といえます。そこに流れているものは、「仲間の声を大切にする」という組合員が主人公との編集姿勢が共通に流れていて、これが全司法の持つ強さとして感じました。
そして、発行回数が多いというのも大きな特徴です。分会の日刊紙が健在なのも賞賛に値しますが、支部でも月刊発行が当たり前で、月2回刊以上もいくつもあり、機関紙を発行することで、職場に「組合の風、全司法の風」を届け、組合の存在感を示しています。こうした機関紙発行が「何でもものを言える」雰囲気を作っている点は、機関紙の力を発揮する点で重要なことです。
特に分会機関紙と女性部・青年部機関紙が元気に発行されている点も大切なことです。分会機関紙を中心に、職場の声やコラムを通して、職場の共感を広げ、職場世論を形成している点にも注目したいと思います。どの分会機関紙もいろんな視点から意見が出され、職場要求やいろんな仲間の声が紙面を飾っています。機関紙というメディアがあるからこそできることです。
一方、課題としては、各地で機関紙編集経験者が退職していく中で、全体として機関紙の形が崩れてしまう傾向がみられます。でも現状では「形は問わず、とにかく大切なことを書き発行すること」が大切であり、次の段階で、「読みやすい形、読まれる内容」にするためにはどうしたらいいのか、編集者が問題意識を持って編集をすることが大事なことです。「読まれるためには、仲間の声と職場の要求を大切にする」「大きな見出しで分かりやすい紙面に」「複数段組みにしてニュースの大小を表す」「コラムで大切な視点を提供する」など、他の機関紙から学んでほしいところです。
最近の傾向で、仕事が忙しいために、集団編集体制があっても集まれないなど、多くのところが編集委員会が組織されずに、「1人編集」で作られていることが全体の問題として指摘されます。機関紙は1人でも作れますが、読まれる機関紙を作るには「みんなの力で作る」という集団編集が欠かせません。1人編集ではどうしても「お知らせ・報告機関紙」になりがちです。いろんな視点で作りにくくなります。編集委員会は組合活動家を要請する場でもあります。「職場の声を聞く、要求をまとめる、記事にする、見出しをつける、分かりやすくレイアウトする」作業は、組合運動の基礎的な力を身に付けます。ぜひ編集部を組織して若い人たちの学ぶ場にしてほしいものです。
機関紙は普段何気なく職場で配布されますが、組合員の手元に確実に届く労組のメディアです。職場に共感の輪を広げ、みんなの気持ちを一つにすることもできます。紙1枚でも確実に職場の民主主義と組合員を守ることができる、発行することで存在感を示すことができる、力があるのが機関紙です。定期発行ができないと、組合員からは「組合が何をしているのか見えない」ということになります。組合員に対する毎月届けられる手紙として、機関紙を大切にした支部活動を基本にしていただきたいと思います。
|
全司法第33回機関紙コンクール
入選作品
|
|
| 第1部門 − 地連・支部 |
| 優秀賞 | 全司法中部(中部地連) |
| 優秀賞 | 全司法しずおか(静岡支部) |
| 優秀賞 | 全司法大阪(大阪支部) |
| 優秀賞 | くろしお(宮崎支部) |
| 努力賞 | 全司法秋田(秋田支部) |
| 努力賞 | 全司法あいち(愛知支部) |
|
| 第2部門 − 分会 |
| 優秀賞 | するが(静岡支部静岡分会) |
| 優秀賞 | こぶし(福岡支部福岡分会) |
| 努力賞 | 日刊みんじ(東京地裁支部民事分会) |
| 努力賞 | おはようけいじ(東京地裁支部刑事分会) |
| 努力賞 | あしたか(静岡支部沼津分会) |
| 努力賞 | 気流(福岡支部小倉分会) |
|
| 第3部門 − 青年・女性・職種等 |
| 優秀賞 | ちゃっきり娘(静岡支部女性部) |
| 優秀賞 | 日向かぼちゃ(宮崎支部女性部) |
| 努力賞 | あゆみ(愛知支部女性部) |
| 努力賞 | いぶき(愛知支部青年部) |
| 努力賞 | ちえのわ(石川支部女性部) |
| 努力賞 | 紅(福岡支部女性部) |
| 特別賞 | 新庁舎への道(福岡支部庁舎対策委員会) |
|
| 第4部門 − 中央行動報告 |
|
|
|
|
| |
 |
| |
|
|
|
| |
恒久的な賃下げとなる「給与制度の総合的見直し」阻止、公務員総人件費削減反対、公務・公共サービス拡充をはじめ、最低賃金の大幅引き上げ、集団的自衛権行使反対などを掲げ、全労連・国民春闘共闘などの主催で夏季闘争7・25中央行動が実施され、全国から集まった全司法の仲間34人が参加しました。
この夏一番となる猛暑の中、昼休みには日比谷野外音楽堂で総決起集会が開催され、2000人が結集したのを皮切りに、各省庁前で要求行動が繰り広げられ、国公労連をはじめとした公務の仲間は厚労省・人事院前に結集し、奮闘しました。その後、参加者全員で銀座デモを行い、「賃上げで景気を回復しよう」「大企業は内部留保を賃上げと中小企業に回せ」などのシュプレヒコールやアナウンスをしながら、街ゆく人々へアピールしました。
全司法は、中央行動に先立ち午前中に出発集会を開催し、中央行動の目的・意義についての意思統一とともに、14年人勧をめぐる情勢と「給与制度の総合的見直し」の問題点についての学習会を行いました。
参加者の声
学習会は有意義
○(総合的見直しの)具体的な問題点、背景など聞くことができ、有意義でした。ポイントだけでも支部で話したい。
○地域によって格差がこれから広がる可能性が高いということがよく分かりました。当支部は下がる地域にあたるので、できる限り阻止していきたい。
○全国規模の集会は、迫力が違います。普段聞く機会の少ない他の組合の話を聞けるのは貴重な体験でした。
○「給与制度の総合的見直し」への怒りが改めてわいてきました。アメリカの労組代表の連帯の発言もあり、大きな集会の雰囲気が高まりました。
○行動の前に学習することで問題点の再確認や意思統一ができるので有意義だと思います。最新の情報を聞けるのも助かります。
|
| |
 |
| |
|
賃下げ違憲訴訟結審 判決は10月30日
歴史の検証に耐えうる判断を |
|
| |
東京地方裁判所における「公務員賃下げ違憲訴訟」第12回口頭弁論が7月17日に開かれ、弁護団を代表して4人の弁護士と原告団を代表して宮垣国公労連委員長が最終陳述を行いました。これにより全司法の40名を含む370名の組合員が原告となった「違憲訴訟」は結審となり、いよいよ10月30日に判決となります。
この日の午後1時30分から開かれた口頭弁論は民間の仲間も多数駆け付け、法廷は満杯となりました。弁護団の1人である加藤弁護士は、「これまで裁判所は、人事院勧告に基づかない給与減額をおよそ想定してこなかった。その勧告制度を確信犯的に無視した減額措置の違憲性が問われた事案である。これまでの裁判例をふまえ、歴史的検証に耐えうる憲法判断を求める」と陳述しました。また、国公労連宮垣委員長は「仮にこの裁判で被告・国の主張が認められれば、公務労働者は無権利状態に陥ることになる。公正な判断をお願いする」と述べ、陳述を締めくくりました。
国公労連は、口頭弁論終了後に報告集会を開き、弁護団から、これまでの裁判の経過と原告、被告双方の主張などを改めて確認し、本日の弁論のポイントが説明されました。その中で、この裁判を通じて、政府が一方的に合憲判断とするために新たにつくられた要件や証拠として提出しなかった様々な情報が明らかとなるなど、被告・国の不誠実さも明らかになったことが強調され、これまでの運動で得た成果は大きいことを全体で確認しました。また、原告団の一員でもある中矢副委員長が決意表明を行い、「私は、裁判という仕組みが国民の権利義務を守り、社会に役立つ制度であるとの自信と誇りを持って裁判所で勤務してきた。今回、自ら原告として裁判を利用する立場となったが、本件を通して裁判所に納得できる判断を示していただき、その判決を胸に、引き続き誇りを持って、裁判所に奉職してまいりたいと思う」と述べ、大きな拍手に包まれました。
違憲訴訟の結審を受けシンポ開く
国公労連と全労連公務部会は、「公務員賃下げ違憲訴訟」の結審を受け、7月26日に東京都内で「賃下げ違憲訴訟と公務員労働者の権利」と題してシンポジウムを開きました。結審した「公務員賃下げ違憲訴訟」の意義を再確認し、公務労働者の権利回復の方向を話し合うことが目的で、自治労連、全教、全大教からも多数参加し、ともにたたかうとの決意表明もありました。
パネリストからは、「理屈では裁判に勝って当然だが、理屈だけでは勝てない。政府の違憲性・不当性を広める運動が必要だ」と強調され、今後、公正な判決を求める署名をはじめ最後までとりくみを強めることを全体で確認しました。
|