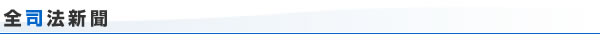 |
| |
2012年人事院勧告
平均7.67%の官民較差なのに改定せず |
|
| |
8月8日、人事院は国会と内閣に対して勧告および報告を行いました。この間、私たちは人事院勧告に基づかない一方的な賃下げという暴挙に対し、実支給額比較にもとづく給与回復・改善勧告を求め、国公労連が提起するとりくみに結集してきました。しかし、人事院は、「賃下げ特例法」を「未曾有の国難に対処するため」として政府の姿勢を容認し、労働基本権制約の「代償機関」たる責務を放棄した勧告を行いました。本号では2012年の勧告内容とその問題点について改めて確認し、秋季年末闘争に向け、給与法および人事院規則の改正を許さないとりくみをすすめていくことが必要です。
55歳超「良好」でも昇給ゼロ
勧告内容は「給与改定・臨時特例法」の施行により、平均7・67%(2万8610円)の官民較差があり、国家公務員労働者の生活に大きな影響を及ぼしていることを認識しながらも、給与法に定められた給与月額を基礎として官民比較をすることが適当であるとして月例給、一時金ともに改定を見送りました。
今回の人事院の対応は、民自公の三党密室談合による議員立法で作られた「賃下げ特例法」を容認し、公務員総人件費削減を押しつける政府に屈服したうえで、自己保身に走ったものといわざるを得ません。
一方、50歳代後半層の給与水準を抑制するため、55歳を超える職員は、標準(「良好」)の勤務成績では昇給を停止させるとともに、3級以上の高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減させる措置を講ずるとしています。
年齢に特化した形での昇給抑制と高位号俸からの昇格対応号俸の引き下げは、公務における人事管理上の特性をまったく無視した差別であり、勤務成績が「良好」でも昇給しないとすることは人事評価や能力・実績に基づく人事管理とも矛盾していると言えます。公務の実態を踏まえた納得し得る根拠やデータを開示させ、十分な交渉・協議の保障など、手続き面を含めた誠実な対応を政府に求めていくことが重要です。
このほか、地域別の民間給与較差は概ね2ポイント前半に収れんされてきており、所期の目的は達成したという認識を示したうえで、今後とも、各地域の官民給与の動向等を注視していきたいとしていますし、次年度以降、現在調査対象としていない産業における事務・技術関係職種の状況を把握して調査対象とすることや民間企業における組織のフラット化等へ対応することなど、官民比較における調査対象職種の拡大や給与比較を行う際の職種の対応関係の在り方等についても言及しています。
引き続き、人事院の動きに注視し、調査方法やデータの恣意的な運用をさせないとりくみを強めていく必要があります。
退職手当の改悪を閣議決定
8月7日、政府は人事院から示された退職給付に係る官民比較調査の結果および「共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議」の報告を踏まえ、国家公務員の退職給付について402・6万円の官民較差があるとして、国家公務員退職手当法の改正案を早期に国会に提出し、支給水準の引き下げを行うことなどを内容とする閣議決定を行いました。
閣議決定にあたっては、全司法が加盟する国公労連に対する納得できる合理的な説明もないまま大幅引き下げを行っただけでなく、経過措置をとるとしながらも、2013年1月からいきなり100分の6(平均3・42月分)ずつ、9ヶ月ごとに減額するなど、一方的な切り下げを行いました。
国家公務員は退職後を含めてさまざまな制約が課せられるという公務の特殊性や一般的に退職金は賃金の後払い的性格を有することなどの実態をふまえず、民間水準のみを唯一の理由に機械的に削減する極めて乱暴なやり方であり、第一線で奮闘している多くの職員の生涯設計を狂わせ、青年層を含めて働きがいや将来への期待を打ち砕くものであり断じて容認できません。
政府・使用者の提案が事実上強要され続けられる中で、何ら対抗する手段がないという無権利状態を打開するためにも、現在、国会に提出されている公務員制度改革関連4法案の抜本的な修正を行わせ、労働基本権を全面回復させることは待ったなしの課題と言えます。
|
| |
 |
| |
|
|
| |
8月6日、全司法本部は「裁判所の人的・物的充実求める請願署名」の採択にむけた国会議員(法務委員)要請を行いました。議員要請が初めての参加者も多かったことから、前日に「全司法大運動」の意義・目的について学習し、具体的な要請方法についても打ち合わせた。
また、事前に訪問・要請をしていた谷博之法務副大臣から応諾があり、約30分間の懇談をもつことができました。要請行動には本部および各地連の代表を含め、総勢23名が参加しました。
学習会
「全司法大運動」学習会では、国会請願の意義・目的や採択までの具体的な手続の流れ、請願された後の具体的な効果などについて本部から説明を行った後、翌日に請願を行う際に訴えるポイントなどについて、各班で打ち合わせを行いました。
特に、地元国会議員に対しては、職場実態を説明する機会が少ないことから、どうやったら具体的かつ分かりやすい説明になるのかを参加者で検討しました。また、目前に迫った人事院勧告をめぐる情勢や問題点についても報告があり、全体で学習を深めました。
国会議員へ要請行動
国会議員要請行動は、参議院議員会館会議室で行動内容を確認するための「団結式」を開き、法務委員でもある井上哲士参議院議員が国会開会中で忙しいなか駆けつけてくれ、私たちの要請を受けてくれました。
要請では地連ごとに衆参両院の法務委員の事務所を訪問しました。議員(秘書)の対応は様々でしたが、概ね私たちの要請内容について聞いてくれ、丁寧な対応でした。
2日間にわたって実施した今回の学習会と要請行動について、参加者からは「全司法大運動の意義を肌で感じることができた」「署名がどのように活用されているのか理解できた」「初めての議員要請だったが、直接要望を伝えることができていい経験となった」「多くの人に参加してもらいたい」などの感想が寄せられました。
谷副大臣と懇談
議員要請を行った午後には、谷法務副大臣と議員事務所応接室で意見交換等を行いました。谷副大臣からは、裁判所の人的・物的充実についての理解が示され、「(請願署名が)採択された場合は、政府として誠実に対応するよう努力する」旨の表明がありました。 |
| |
 |
| |
| ノーモアヒロシマ・ナガサキ・フクシマ 原水禁世界大会 |
|
| |
|
原水爆禁止2012年世界大会が広島で8月4日から、長崎で8月8日から開催され、海外代表も含めて約6、800人が参加しました。広島大会2日目の5日には、「国公労連平和の集い」が広島市内で開催され、全司法からも参加しました。
今年の世界大会は、NPT(核拡散防止条約・5年ごとの検討会議)再検討会議の2015年開催にむけて世界から核兵器をなくす運動を発展させるとともに、福島第一原発事故から大きな広がりをみせている原発ゼロを求める運動と連帯して開かれました。特に、NPT再検討会議にむけて「核兵器全面禁止の国際アピール署名」をとりくみの軸にして、核兵器禁止条約の交渉開始を求める広範な多数派を国際的に形成していくこと、いかなる核被害者も出さない未来を作り上げることなどが、全体として確認されました。
被爆者作らないことが大切
「国公平和の集い」では、広島県原水協の高橋信雄代表理事から「ヒロシマからフクシマを考える」との演題で講演がありました。
同理事長は、原爆は大量の放射性物質を広範囲に放出して「黒い雨」を降らし、広島にいた人以外にも放射線障害を発生させ、以来67年たった今でも、被ばく者には原爆の苦しみが続いていると告発しました。
14年前に起こった「東海村臨界事故」も、亡くなった方は一度に高線量の被ばくをしたことで、急性放射線障害が発症したと言われています。また、福島第一原発事故によって、高線量の下で復旧作業が続けられています。一日も早い事故収束と除染や被害状況の的確な把握、そしてその対応が求められており、原発から脱却し、「被ばく者を作らないことが放射線治療の最善の方策」であることを改めて認識した大会でした。
(出口朋宏)
|