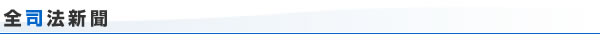 |
| |
裁判員制度へ人的・物的充実を
5・25衆参法務委員請願行動
|
|
| |
|
5月25日、全司法本部は、全国8地連24支部からの全国上京団34名とともに、8ヶ月間にわたって全国で集められた「全司法大運動」署名5万筆以上をたずさえ、裁判員制度をはじめ司法制度改革を支える『裁判所の人的・物的充実を求める請願』が国会で12年連続採択されるよう請願行動を行いました。中央行動日の午前10時過ぎ、衆議院第一議員会館内で団結式を開き、班別になって衆参法務委員会の国会議員54名への要請行動を実施。公務員削減の逆風が吹き荒れる中、与党議員事務所へも果敢に訪問し、裁判所の窮境を説明し、概ね、丁寧な対応を受けることができました。その後、請願行動のあと国会内で再び全体会をもって、仁比聡平参議院議員(日本共産党)の出席を受け、残る請願署名の提出を行いました。当日は、激しい雨降りでしたが、午後には、国公労連夏季第一次中央行動に結集しました。
|
| |
 |
|
| |
|
雨ついて中央行動
公務員制度法案等の廃案をめざして
|
|
| |
|
5・25上京団に1500人
「公務員制度」関連法案は、衆議院本会議、同内閣委員会で趣旨説明が行われ、5月18日から審議入りしました。
法案は、労働基本権を先送りしたまま能力・実績主義の人事管理を導入するとともに、人事院の機能を縮小・内閣権限を強化するものです。
一方、5月25日、降り続く雨の中、公務員制度関連法案や社会保険庁の解体・民営化法案などの廃案を求めて、公務労組連絡会などによる中央行動が、社会保険庁、人事院前要求行動、日比谷野外音楽堂での中央総決起集会、国会請願デモ行進、国会議員要請などが展開されました。全司法は、全国上京団として34地連・支部から63名が参加、午前中は全司法独自に大運動署名の請願行動の後(上記)、午後からの社保庁前要求行動等へ参加しました。あいさつに立った国公労連福田委員長は、「法案の本質的な議論が尽くされていない」とひきつづくたたかいを訴えました。
|
| |
 |
|
| |
|
誠実に対応する
公務員制度改革 裁判所制度設計
退職手当・年金の情報収集 07諸要求 第1回給与課長交渉結果
|
|
| |
|
全司法本部は、5月15日、諸要求貫徹闘争期における要求前進をめざし、公務員制度改革、旅費・庁費、諸手当、休暇・育児休業、男女平等・母性保護、次世代育成支援、宿日直、権利、社保・共済制度の9項目について、最高裁事務総局人事局垣内給与課長との第1回交渉を実施し、以下の回答(要旨)を得ました。
公務員制度改革に関しては、今通常国会に提出された国家公務員法等改正法案に触れ、能力・実績主義に基づく人事管理の導入、再就職に関する規制について、「基本的な枠組みについては準用する」との基本姿勢を示し、労働基本権問題については、「行革推進本部に設置された専門調査会の検討を見守りたい」と回答しました。また、「裁判所の制度設計については、勤務条件に大きく影響する問題でもあることから、これまで同様、職員団体と誠実に対応していく姿勢に変わりはない」と述べました。
関連して、分限処分については、「裁判所として新しい枠組みを設けたり、特別な運用をすることは考えていない」、再就職管理については、「裁判所職員再就職等監視委員会および官民人材交流センターに代わる(中略)最高裁判所の組織をどのようにするかは、今後の検討課題」と回答しました。また、新たな人事評価制度の試行については、「行政府省の動向等も参考にしつつ、公布日から2年以内という国家公務員法改正法案の施行時期もにらみながら」「試行の実施は不可欠と考えている」と述べ、本年度中の試行実施が予想されます。
評定書の開示については、「開示は考えていない」と回答、勤勉手当の公平・民主的な運用については、従前水準の維持を示しました。
なお、府省間配置転換については、来年度も本年度並みの受入れになる見込みを示しました。
旅費法についても「2004年4月に財務省から出された通知をふまえて、旅費法の範囲内で適切な運用に努めたい」「意見・要望は、財務省に伝えて行きたい」と述べました。組合からは、航空機パック問題を追及し、引き続きの対応を求めました。庁費については、「今後も必要な予算確保に努力する」との従前回答を踏襲しました。
諸手当に関しては、住居手当や新幹線通勤の問題の切実さに言及しつつ、「要望を人事院に伝えたい」と回答しました。組合からは、寒冷地手当の改善、超過勤務手当の割増等を追及し、「意見を伝えて行きたい」との回答を得ました。
有給休暇、育児休業・介護休暇の取得状況等については、別表のとおりです。有給休暇の取得環境が引き続き改善していると認められます。ただし、代替要員の確保は充分ではなく、切実な課題です。
新たな育児短時間勤務制度については、「子育て中の職員にとって利用しやすいものとなるように、(中略)運用を検討したい」と回答し、自己啓発等休業制度については、「公務の遂行や職員のキャリアアップに支障がないよう運用したい」と述べました。いずれも8月実施予定です。
男女平等・母性保護に関しては、採用時の男女比等を示しながら、改善維持を説明し、特に、2月に人事院規則等の一部改正があり、セクハラ防止やその研修について、当局の努力規定が義務規定に高められたことから、「裁判所においても人事局長通知(3月14日)を発出し」「いっそうの意識啓発をはかりたい」と回答しました。
宿日直に関しては、全司法第62回定期大会での「提言」について、「検討すべき選択肢の一つ」とし、加えて、「政府のe‐Japan構想等からも新たな環境が生じつつある」と認めながらも、令状主義・関係機関の姿勢等から改善が進んでいません。
権利については、従前とおり、「誠実な対応」「下級裁当局への指導」を約束しています。
社保・共済制度の改善については、「共済組合は国とは別個の(中略)法人」として、正面からの組合対応を回避しつつ、「要望は共済組合に伝える」と述べました。また、退職手当・共済年金については、職員の関心が高いことは十分認めつつ、「情報収集に努め、取りうる範囲で対応していきたい」と回答しました。
全体には大きな前進は認められないものの、公務員制度改革の中での新たな評価制度の検討、育児短時間勤務制度・自己啓発等休業制度の開始、セクハラ防止等での新制度の開始等があり、職場でのいっそうの実態点検が必要となっています。本部では、引き続き職場諸要求貫徹に向け、努力します。
|
| |
 |
|
| |
|
速記官が寄せ書き
07年諸要求 統一要求の前進めざし
|
|
| |
|
2007年年諸要求貫徹闘争期に統一要求の前進をめざして、行(2)職、速記官と青年が独自に署名、寄せ書きなどにとりくみます。
行(2)職の要求内容は前号(2032号の2面)でお知らせしていますが、速記官は、「5級昇格の抜本的改善、ステンチュラ本体・消耗品の官支給」の重点要求の実現をめざして一人ひとりの寄せ書き行動にとりくみます。上記寄せ書きの重点要求は昨年の地連担当者会議で確認されたもので、6月22日までに本部集約して26日の最高裁人事局長交渉に提出します。
青年協は「明るい未来に向かって花開け!ひまわり一言要求行動」をとりくみます。この行動の目的は、未来を嘱望されている青年の要求が花開くよう、ひまわりの花びらに青年一人ひとりがもつ要求を記入し最高裁に提出してその実現を求めることにあります。また、記載されている要求はおおむね現地当局にも見せるべきものが多いことからその写しを各支部交渉等の場にも提出するようにします。青年協では、6月11日の第3回拡大委員会後の最高裁交渉で手交することにしています。
|
| |
 |
|
| |
|
| |
| |
|
5月14日、強行成立した国民投票法は、公務員・教育者の運動が広範に規制され、最低投票率をもうけず、1割台、2割台の賛成でも改憲が成立するなど、憲法が定める国民主権、思想信条・表現の自由、憲法96条の趣旨に反する違憲の疑いの強いもので、断じて容認できません。
根本的な問題点は?
まさに「改憲の道筋をつける」ための手続き法案です。
9条改憲に手をつけるために、(1)国民投票の制度と憲法審査会をつくることによって、改憲のレールを敷く、(2)両院の3分の2の賛成を得る「改憲派の共同」をつくって改憲発議の準備をする、という狙いがあります。
安倍首相が今国会での成立に固執したのは、自分の内閣で改憲に踏み出すためにほかなりません。
改憲しやすい仕掛け
投票法は、問題だらけの欠陥法案です。国民の意思を正確に反映させずに、改憲に誘導する仕掛けが何重にも仕込まれています。
最大の仕掛けは、国民投票に最低投票率の規定を設けておらず、「有効投票の過半数の賛成」という低いハードル設定であり、投票率によっては有権者の1〜2割台というごく少数の賛成で改憲が成立します。
これでは、主権者国民の多数意思によってのみ憲法改正ができるという憲法96条に反しています。
審議は凍結されない
改憲を準備する憲法審査会が国会に設置されます。改憲案の発議こそ3年間は凍結されていますが、改憲のための審議は進められ、3年後に即発議ということになります。
公務員の運動を規制
公務員・教育者の自由な意見表明や国民投票運動を、「地位利用」を理由に制限を加え、そのうえ「政治的行為の禁止」という公務員法上の規制も検討するとしています。
500万人にのぼる公務員・教育者の主権者としての国民投票運動の自由が奪われるばかりか、公務員労働組合の運動への制限が懸念されます。
改憲広報は無制限
広報協議会による改憲案の広報を無制限に認めています。改憲政党が主導する協議会によって、国費による改憲キャンペーンが野放しに行われることになります。
カネで改憲を買う
テレビ・新聞での有料広告は、投票日前2週間以前は自由で野放しになります。
国民の公正な情報へのアクセスが保障されず、財界など資金力のある改憲派が「カネで改憲を買う」危険が懸念されます。
改憲のため一括投票
改正条文によっては、国民の賛成反対の意思は様々です。投票法では、「関連する事項ごとに区分して」の投票であり、何が関連するのかは明確にされていません。
9条を変えるために一括投票に道を開く危険が大きく、国民の意思を著しくゆがめます。
|
| |
 |
|
| |
|
元気をもらった!
公務と民間の分断許さない
全司法は40人 国公女性交流集会ひらく
|
|
| |
|
5月11・12日に、東京・神奈川県内で、第37回国公女性交流集会が開催されました。
約300名規模の集会で全司法からも40名が参加しました。
格差の記念講演
一日目は東京・星陵会館での全体集会で、記念講演、基調報告等がありました。二宮厚美神戸大教授の「格差社会化のなかの国民の暮らしと労働ー公務バッシングと女性いじめの根源ー」という講演では、格差の広がり、公務と民間の分断を許してはいけない、というお話がありました。
集会後は、国会議員要請と人事院要請に分かれての行動でした。議員要請は、初めての人も多く「いい経験になった」という感想も聞かれました。
終了後は、貸し切りバスで横浜へ移動しました。夕食交流会は中華料理で、お子さん連れの方もまじえて、にぎやかに行われました。
アトラクションでは、神奈川の弁護士さんたちの「歌う9条の会バンド」が登場し、平和ライブが行われました。「全司法の方々にはお世話になっています」というコメントもあり、エールの交換をしました。
母性・基地分科会
二日目は四つの分科会と二つの分散会へ分かれての参加でした。
分科会は「家族と仲間のメンタルヘルスケア」「食の安全」「母性を守り生き生き働きたい」「神奈川の基地被害の実相」というテーマで行われました。
分散会は二つのコースに分かれて、米軍基地等を、バスや船を使って見学しました。神奈川県は、沖縄県に次ぐ第二の基地県だということを改めて感じる企画でした。
若い人たちを含めて大勢の参加があり、楽しく学んで元気のでる集会になりました。
|
| |
 |
|
| |
|
| |
| |
|
4月に新規採用者が全国の職場に入りました。各支部では歓迎する様々な行動が行われました。前号につづき中国地連と札幌支部から通信がきました。各支部は早期新採全員加入めざして奮闘しています。
各地のメーデー 全司法も参加
5月1日は労働者の祭典。各地のメーデーに全司法からも代表が参加しました。思いをプラカードにたくした甲府支部、大運動署名を集めた旭川支部、雨にもまけず参加した愛知支部から写真が届きました。
|