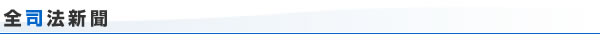 |
| |
|
TUNAG��Θb�̃c�[����
���邭�A�y�����A���C�悭�������Ă������I
�Q�O�Q�T�N�x��P��S�����L����c |
|
| |

�I�����C����76�����Q�����ĊJ��
�@10��4���A���N�x�̑�1��S�����L����c���I�����C���ŊJ�Â��܂����B�S���̒n�A�E�x�����L���ɃI�u�U�[�o�[��������76�l���Q�����A�H����N���ɂ����Ă̂Ƃ肭�݂�b�������܂����B
�J���g����������������������オ����
�@����ψ����͊J������ŁA34�N�Ԃ��3������Ȃǂ̐l���@�����̑O�i�ʂɂ��āu�J���g���������������珟����ꂽ���ʁB�����E��ɓ`���đg�D�����E�g��ɂȂ���K�v������v�Ƃ��������ŁA�u�������A�����㏸�ɒǂ������A�������P�ɂ͌q����Ȃ������v�Ǝw�E���āu���N�̏t���ň��������啝���グ��������邱�ƁA���킹�āA����Ō��łȂǂ̕����������邽�߂̉^���ɘJ���g�������W���邱�Ƃ��d�v�v�Ǝw�E���܂����B
�@���̌�A����̉�c�̓I�����C���ɂ��1�������ŊJ�Â��ꂽ���Ƃ܂��A3�̃p�[�g�ɕ����āA��㏑�L���̒�ĂƎQ���҂ɂ�铢�_�����݂ɍs���܂����B
�E����Ԃ��ō��قɓ`�����������
�@�ŏ��̃u���b�N�i�H�G�N���������߂����Ɖۑ�j�ŁA��㏑�L���́u�ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A12�����{�܂łɑΉ����ǂƂ̌������{���邱�Ɓv���ƒ�N���܂����B������āA�������̒n�A�E�x������A�Ή����ǂ��u�㋉���̌���łȂ��ƌ��͂ł��Ȃ��v�u���������Ō������Ă��ł��Ȃ��v�ƌ����Ă���Ƃ̕�����܂����B��㏑�L���́u�\�Z�z�������m�肷��O�Ɍ����s��Ȃ���ΈӖ����Ȃ��v�Əq�ׁA���_�������̌��ł͂Ȃ��u�x�����o�����E����Ԃ��ō��قɏ�\����悤�A�����ق�Njy���邱�Ƃ��d�v�v���Əd�˂Đ������܂����B
�����㋤���e���▯���ٔ��f�W�^�����ւ̕s��
�@2�ڂ̃u���b�N�i�H�G�N�������ɂ�����d�_�v���j�ł́A�������������ɓ]���Ă�����ƂŁA�E��̔ɖZ��l���z�u�i�����j�̕K�v���ɂ��Ĕ���������܂����B�܂��A�V�X�e���J���̒x���p�\�R�����͂��߂Ƃ����@��̃X�y�b�N�̒Ⴓ���܂߁A�����㋤���e�������▯���ٔ��f�W�^�����̑S�ʎ{�s���}���邱�Ƃɑ���s���̐����o����܂����B
�@�܂��A�u���ǂ͏㋉�����猾���āA�l���炵���肫�Ől���z�u���l���Ă���v�u�p���n���������Ă���B�Ƃ�킯�A���̍ٔ�����Ǘ��E�ɂ��p���n���������v�u���������܂炸�A��x�Ȃǂ̑�֗v�����݂���Ȃ��v�u�h�����̊���������ɂȂ�A���ǂ��Ə��\���̕ύX�ɂ��Ē�Ă��Ă����v�u���^�i�蓖�j�̎x���F�莖�����W���ƁA�x�����x���Ȃ��ĐE�����s���v����\���������A����������v�ȂǁA�Q���������L������E����Ԃɂ��ƂÂ��ӌ���A�n�A�E�x���Ŗ��ɂȂ��Ă邱�Ƃ�����܂����B
�s�t�m�`�f���u�Θb�v�������߂�c�[���Ƃ���
�@�Ō�̃u���b�N�i�g�D�����E�g��̂Ƃ肭�݁j�Ɋւ���āA��㏑�L�����u�s�t�m�`�f��V�̗p�E���ɑ���w�Z�J���h�A�v���[�`�x�Ɋ��p������A10���E11���Ŏ��{���N���Ă���E���ł̃e�[�}�ɂ���ȂǁA�w�Θb�x�̃c�[���Ƃ��čő�����p���A�g�D�����E�g��������߂Ă������v�ƒ�Ă����̂��āA�u�g�����̃X�}�z�ɒ��ځA���A���^�C���ŏ�͂��͉̂���I�v�Ƃ������s�t�m�`�f�ւ̊��҂ƂƂ��ɁA�u�g�������W�߂ēo�^�������Ă݂����v�u�Ǔ����܂߂ăI���O��z�u���đg�����̓o�^�������߂����v���̐ϋɓI�Ȕ������o����܂����B
�@�g�����g��ɂ��ẮA��82��������̂��ƂɂȂ�C���Ă��Ă����a�̎R�x������u�V�̗p���g���ɉ������邽�߂̃n�[�h�����ł�����艺���A�܂��������āA�J���g���̂��Ƃ�m���Ă��炢�A�Q�����Ă��炤�Ƃ������������ߍׂ���3�N�ԑ����ė������ƂŁA�g�D�������ɓ]�����v�Ƃ̕�����܂����B�܂��A10���V�̗p�ɑ��铭�������ɂ��Ă̕�����A�u���邭�A�y�����A���C�悭�������Ă������B���L���������łȂ��ƁA�N�����Ă��Ȃ��v�Ƃ̌Ăт���������܂����B
�@��㏑�L�����u���̏H�A�܂��͖����̃}�C���h��ς��A���Ŋm�F����373�l�̑g�����g��Ɍ����āA�H�i�K����S�Ă̒n�A�E�x�����S�͂������ĂƂ肭�����v�Əq�ׂĉ�c���܂Ƃ߂܂����B
|
| |
 |
| |
|
�E���c�̂̈ӌ��͊W�@�ւɓ`���悤�ɂ�����
�ō��َ����������� |
|
| |
|
�@�S�i�@�{����10��2���A�u2025�N�l���@�����̎戵�����Ɋւ���v�����v�Ɋ�Â��A�ō��َ��{���������Ƃ̌������{���܂����B
�������P�����̂��݂₩�Ȏ��{��v��
�@���^�����ɂ��ẮA34�N�Ԃ��3���������ł��邱�Ƃ܂��A���݂₩�Ȏ��{�����߂܂����B���킹�āA�����㏸�����炸�������P�ɂ͕s�\���Ǝw�E���A�n���Ζ��E�����܂ߔ�r��ƋK�͂��u1000�l�ȏ�v�Ƃ��āA���ׂĂ̐���̕���グ�Ɋ��p����悤���߂܂����B
�@���蓖�ɂ��ẮA�����ŏo���ꂽ�}�C�J�[�ʋ̉��P�̎��{�Ƃ��킹�āA���}�����x���̗v���������A���ԏꗿ��������グ���ɂ��l���S���Ȃ����悤���߂܂����B�܂��A��N�̊����ɂ��ƂÂ��n��蓖�̈��������~��v�����܂����B
�@���������͒������P�ɂ��āu�E���c�̗̂v�]�͊W�@�ւɓ`���悤�ɂ������v�Ɖ��A�蓖�ɂ��Ắu����̓�����������Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
���Ύ��Ԕc���̓O��ƕK�v�Ȑl���̊m�ۂ�
�@�����Ɠ����ɏo���ꂽ�u�������l���Ǘ��Ɋւ���v�ł́A���ߋΖ��̏k�����d�v�ۑ�Ƃ�����j��������܂����B����܂��A���N1���̋Ζ����ԊǗ��V�X�e���������_�@�ɁA�n�ƑO��x�����܂߂����ߋΖ��̎��Ԕc����O�ꂷ��悤���߂܂����B
�@�܂��A�����u�l���S�����ǂɂ��ɖZ�����ւ̏\���ȗv���m�ۂ�l���z�u�̍œK���v�ɂ����y���Ă��邱�Ƃ���A2026�N�x�ٔ����\�Z�̊T�Z�v���ɂ�����54���̌����v���͓�����������̂ł͂Ȃ��A�����㋤���e���̓����A�����ٔ��f�W�^�����̃t�F�[�Y3�{�s�A�Y���ٔ��̃f�W�^�����Ɍ����āA���炽�߂ĕK�v�Ȑl���̊m�ۂ��������߂܂����B
�@���������́A�u����܂ňȏ�Ɋe�펖���̊ȑf���E���������̎�g�𐄐i���āA�ٔ����A�����ǂ��킸�A�g�D�S�̂Ƃ��Ē��ߋΖ��̍팸��}��ƂƂ��ɁA�����ʂɉ������K���Ȑl���z�u�ƂȂ�悤���������w�͂��Ă��������v�u�K�Ȓ��ߋΖ����Ԃ̊Ǘ����s���悤������w����O�ꂵ�Ă��������v�Ɖ��܂����B
�l���@�̓����܂��J�X�n������v��
�@���ׂẴn���X�����g����Ǝ��������������߂܂����B���ɃJ�X�^�}�[�n���X�����g�ւ̑Ή����������߁A�l���@���A�J�X�^�}�[�n���X�����g�̋K���������������Ă�����Ƃōٔ����̓����܂����Ή������߂܂����B
�@���������́A�u�l���@�K���̎�|���܂��A�i�����j�n���X�����g�h�~�Ɍ����������ʓI�Ȏ�g�ɓw�߂Ă��������v�u�J�X�^�}�[�E�n���X�����g�Ɋւ��ẮA�p���[�E�n���X�����g�ɂȂ蓾��悤�Ȍ����ɑ��ẮA�g�D�Ƃ��ċB�R�Ƃ����Ή������߂��邱�Ɠ��̔F�����A���������L���Ă������Ƃ��d�v���ƍl���Ă���v�Ɖ��܂����B
���A�x�e�����E���̏������P��
�@���ΐE���̑ҋ����P�Ƃ��āA�N���x�ɂ̕t�^��q�̊Ō�x�ɂ̗L�����A�e��蓖�̎x���Ȃǂ�v�����A��ΐE���Ƃ̕s�����Ȋi������������悤���߁A�u�����]�����[���v�̓K�p�A�C�������̓P�p�����߂܂����B
�@���������́A�u����Ƃ��l���@�̓������������A�l���@�ɂ����ĉ��炩�̌��������s����ꍇ���ɂ́A�K�v�Ȍ��������������Ă��������v�Ɖ��܂����B
�@�܂��A50�`60��̐E���ɂ��āA55�ł̏�����~��60����E���̋��^��7���ɂ���ȂǁA���^�������������A���������ƃ��`�x�[�V�����̒ቺ�������Ă��邱�Ƃ��w�E���A�������P�����߂܂����B
�@���������́A�u�E���c�̗̂v�]�́A�W�@�ւɓ`���悤�ɂ������v�Ɖ��܂����B
|
| |
 |
| |
|
| �e�n�A�ŐN�̌𗬃C�x���g���J�� |
|
| |
|
�@�R���i�ЂŊJ�Âł��Ȃ������e�n�A�ł̐N�̌𗬃C�x���g���������A�S�i�@��ʂ����N�����̂Ȃ��肪�L�����Ă��܂��B8���ɂ́u�l���N�F�D�W��v���A9���ɂ́u���k�N�̏W���v�����ꂼ��J�Â���܂����B
�l���N�F�D�W��A���ɍĊJ�I
�@8��23���y��24���ɁA�l���N�F�D�W����J�Â��܂����B
�@�V�^�R���i���s�ɔ����A���炭�J�Â��ł��Ă��Ȃ��ł͂���܂������A�l���n�A�A�N���̕��X�̋��͂̂��ƁA�l���e���̐N�ɎQ�����������A���Ƃ��J�Âɂ������邱�Ƃ��o���܂����B
�V��ŁA�̂��āA�w��ŁA�Ȃ������\�\�l���̐N����
 |
| �܂�����ƁA���㉷��O�Ŗ� |
�@1���ڂ́A�����b�N�����J�Â��܂����B
�@�����b�N�́A���v���_��50�_�ɂȂ�悤�ɁA�̖_�𓊂��ēI��|���Ă����Ƃ����V���v���ȃQ�[���ł��B�������A���͒N���i�����܂߂āj�o�����Ȃ��A���߂͎�T��̏�Ԃł������A3�l1�g�Ńv���C�����Ă������ŁA�ǂ̓I��_�����A�ǂ̂悤�ɑ���`�[���̎ז������Ă������ȂǁA�e�`�[���̌��������āA�ƂĂ��y�������Ԃ��߂������Ƃ��o���܂����B
�@���̌��0����A���e��ƁA������n�݂A���ꂼ�ꂪ��b�ɉԂ��炩���A�e�r��[�߂܂����B
�@�E��ł͂Ȃ��Ȃ����݉���Ȃ����N��̐N�Ɗւ�肪���ĂȂ����ŁA�u�F�D�W��ɂ��F�X�Ȑl�Ƃ��b���o���Ă悩�����v�Ƃ�����������A���߂ėF�D�W��̑���������܂����B
�@���e��̌�́A�J���I�P�Ŏ��Ԃ�Y��ĔM�����A���Z�����w���̍��̋C�����ɖ߂��Ċy���ނ��Ƃ��o���܂����B
����I�ɊJ�Â��A�N�̒c����[�߂Ă�������
 |
| �̂��s��������̌�́A�^�����[�h�S�J�I |
�@2���ڂ́A�w�K����J�Â��܂����B����N���c���ɍu�`�����������A���̌�O���[�v�ɕ�����A�u���E�w�K�E�𗬁v�݂̍�����A�N���E�n�A�E�x���Ƃ���3�̘g�g�݂��ƂɌ������܂����B
�@���߂āA�g�������̈Ӌ`�A�ړI�ɂ��čl����ǂ��@��ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�Ō�ɁA���㉷����ό����܂����B�V�����J���N�����v�̏�f�≷��X��ʂ蔲���A��N�A���N�Ԃ̉��C�H�����o�đS�ىc�ƍĊJ���������㉷��{�ق̑O�ŏW���ʐ^���B�e���A���U�ƂȂ�܂����B
�@���i�A�Ȃ��Ȃ��𗬂ł��Ȃ������̐N�ƌ𗬂��ł���M�d�ȋ@��ł���A����悤�₭�ĊJ���邱�Ƃ��o�����̂ŁA���e�ʂŃu���b�V���A�b�v��}��A���������I�ɊJ�Â��A�l���̐N�̒c����[�߂Ă��������Ǝv���܂��B
�i���Q�x���j
2�N�A���A���N�́u�c��v�œ��k�N�̏W�����J��
 |
�厩�R�Ɛ㉟���I
���k�N���J������ɐ[�܂� |
�@9��27������28���ɂ����Ă�2���ԁA���k�N�̏W�����H�c���̓c��ŊJ�Â���܂����B���k�ł͐N�̏W�������炭�r�₦�Ă��܂������A�n�A�ƐN���̋��͂̂��Ƃɍ�N�������A���N������2��ڂ̊J�Âɂ������܂����B
�@�n���ŗL���Ȃ͂��݂��̃s�U��H�ׂȂ��玩�ȏЉ���ς܂��A14�l�̎Q���҂͑��X�ɗV���D�ɏ�荞�݂܂����B�ڂ̊o�߂�悤�ȐV�̉��A���{��[���ł���c��ő厩�R�̗͂������܂����B�݂ɂ������Ǝv���A�p�Z�ƂȂ������w�Z�i���݂͊w�K�{�݁j��K�ꂩ�Ă̐����Ɏv����y���A����܂ʼn�������Ƃ��Ȃ��g�����ƂƂ��ɃX�����{�[�g�𑆂��A�C�Â��Ώh����̃R�e�[�W�ɓ������Ă��܂����B�R�e�[�W�ł͊w�K��J����A�N���E�n�A�E�x���ɂ�������A�w�K�A�𗬂̗��z���ƌ���A������ɂ��Č�����s���܂����B�[�H�͋��͂��Ȃ���J���[���C�X�����A�ԉƉ�����J��[�߂܂����B�ӂƋ�����グ��A�F���֓����o���ꂽ���ƍ��o����قǂ̐��X���L����A���ꐯ�Ɋ肢���������N�����܂����B
�������S��悩��^�c�܂Łu�N��́v�\�\������2���ԂŒ��Ԃ�
 |
| �ԉ̖��邳���܂Ԃ����Ί� |
�@2���ڂ̃o�[�x�L���[�ł́A�H�ނ̏�����������A�S�~�̕��ʂ�Еt���Ȃǂ�N�Ɍ�����ł��Ȃ��X�̐N�������I�ɍs���A���R�̌b�݂𑶕��Ɋy���݂܂����B������2���ԂŌ݂��̊���m��Ȃ������N���A�܂�Ő̂���̗F�l�̂悤�ɒk���A�ʂ��ɂ��݂Ȃ�����U����l�q�͂܂��ɍ��N�̏W�����听���ł��������Ƃ������Ă��܂��B
�@���N�̏W���̊��͎i��i�s��֔ԂʼnA�\�Z�W�A���V�[�g����W�A�\��W�A���W�ȂǂƑ����̎d���S���čs���A��l�ɕ��S����Ȃ��悤�ɍH�v���čs���܂����B��N�Ɣ�ׂĉ�c������オ��A�������������Ă��܂��B�W���͌𗬂����̖ړI�ł͂���܂����A���҂̊w�K�̋@��ł�����܂����B
�@���k�̊e�x���̐N���A�N�ł����鎞�Ԃ͂��܂�c����Ă��܂���B���̑g���������x���Ă�����X�����ނ�����A���̐N�������������p���Ȃ���Ȃ�܂���B���łɎx����n�A�̖����ƂȂ��Ă���N���������܂��B���k�N�̏W���́A����ׂ����ɔ����A�c�����m�F����ƂƂ��ɁA�V����̊����̗\�s���K�ƂȂ��Ă����ł��傤�B
�i�H�c�x���j
|
| |
 |
| |
|
���v�H�ٔ����̃f�W�^�����@��Q��
���N�T���́u�t�F�[�Y�R�{�s�v�ւ̌��O |
|
| |

�t�F�[�Y3�{�s�̌��O�ɂ��Ĉӌ�����
�@10��2���A���N5������{�s����閯���ٔ��f�W�^�����t�F�[�Y3�ւ̌��O����A�{�s���������߂Ă���ٌ�m�̕��X�̂��b�����������܂����B�u���炩�̗��R�œd�q��o�ł��Ă��Ȃ������ꍇ�ɁA�s���v�Ɉ����邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����v�u�����������Ŏ{�s������łs���������r�Ɉڍs���A�f�[�^�ڍs���ł��Ȃ��Ȃ�A�L�^�Ǘ������G�ɂȂ��ĉߌ�̌����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v�u�f�[�^�ڍs�̂��߂ɋƖ��ϑ����ׂ��ł͂Ȃ����v�Ȃǂ̂��ӌ������������܂����B
�@������āA�S�i�@�́u�{�s�̉����v�͗v�����Ă��Ȃ����̂́A���ꂩ��́u�V�X�e���J���̒x��ɂ��A��������x��ԁA�O�x��ԂɂȂ�v�u�E���[�����̃X�y�b�N���Ⴂ�v�u�`�[���Y��������e�i���g�ڍs���Ɍ���ɏ\���ȏ�������Ȃ������o���܂���ƁA�ٌ�m���͂��ߓ����҂���̖₢���킹�Ɏx��������������ꂪ����v�u���L���̑������Ȃ��A���ɒn���ł͌�������Ă���A�l�I�̐����s�\���v�Ȃǂ̌��O�����b�����܂����B
�@�܂����A9��8���ɂ́A�ō��ق���s���������r�ɂ��āu���������ɂ��ẮA���i�K�ł́A�{�N12�����߂����č�Ƃ������߂Ă���A�x���Ƃ�2025�N�x���ɂ͊������錩���݁v�Ƃ��������ƂƂ��ɁA���������ɂ��Ắu2027�N�x���A����̓I�ɂ́A2027�N3���̉����Y�i�@�̈ꕔ�{�s��A���N9�����̂f�r�r�ւ̈ڍs�Ƃ���������������āA�������邱�Ƃ��߂����v�Ƃ��āA����܂ł̗\�肩�炳��Ɍ��|���ɂȂ����������܂����B
�@���v�����̎����������Łu�ԋ߂ɔ������t�F�[�Y3�S�̑Ԑ��Ō}���邽�߂ɁA�������Ǘ��V�X�e���i�q���������r�j���n�߂Ƃ���e��V�X�e��������I�ɉғ����A��Q���ɂ����Ă͐v���ȑΉ����ł���悤�\���ɔz�����Ă��������v�Ƃ����̋�̉����������߂���̂ł��B
|