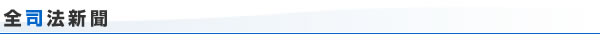 |
| |
|
離婚後共同親権の導入、民事訴訟手続デジタル化フェース3などに
対応できる職場の態勢整備を要求
2025年秋季年末闘争のポイント |
|
| |
|
「地連・支部が主役」となる秋季年末闘争がスタートしました。家庭裁判所の人的態勢整備や民事訴訟手続デジタル化フェーズ3への対応が喫緊の課題になっています。
秋季年末闘争の重点課題や地連・支部におけるとりくみのポイントについて井上書記長に聞きました。
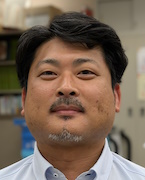 |
| 井上書記長 |
秋は組合員の切実な要求を実現させる重要な時期
○秋は「地連・支部が主役」と言われるのはなぜですか?
秋年期は、来年4月期の人員配置をはじめ、異動要求の実現や昇任・昇格発令など、組合員の切実な要求を実現させる重要な時期です。
最高裁は8月29日、次年度予算案の概算要求を財務省に提出しました。予算案として確定するまでに若干の変動はありますが、裁判所全体の大枠がほぼ決まったことになります。今後、12月の予算案確定にむけて、下級裁との間で配置定員等の検討(見直し)が行われることから、12月初旬までに対応当局との交渉を実施し、地連・支部の重点要求の実現を求めていく必要があります。そうしたことから、秋は「地連・支部が主役」と言われています。
また、最高裁回答を活用する観点から、最高裁回答とかい離している実態がある場合は「職場実態は最高裁回答と違う」と指摘し、改善を求めていくことも重要です。
家裁の人的態勢整備、デジタル化が重点課題
○秋の重点課題は何ですか?
2026年5月までに離婚後共同親権の導入等を含む改正民法が施行され、同時期までに改正民事訴訟法が全面施行されることから、新たな制度の導入に備えることが喫緊の課題です。加えて、今後は刑事裁判のデジタル化にむけた検討・準備や新しい情報通信インフラ(GSS)への対応等も課題となります。
離婚後共同親権等の導入や民事訴訟手続デジタル化フェーズ3に対応するため、書記官や家裁調査官等の増員をはじめとした裁判所の人的・物的充実は欠かせません。とりわけ、子の意思把握等の重要な役割を担う家裁調査官の大幅増員は欠かせないことから、予算確定までに追加で増員要求を行うよう追及を強めます。
デジタル化への対応に関わっては、RoootSやmintsをはじめとしたシステムの改修を求めます。あわせて、職員貸与パソコンについて、デジタル化に耐えうる性能を持ったパソコンに更新することも含めた対応を求めます。
個々の職員の負担がさらに重くなる?
そうした状況のもとで、最高裁は次年度予算案の概算要求で、増員要求と定員合理化等との差し引きで「△54」となる要求を行いました。
職種ごとで見ると、書記官は6年連続で増員要求なし、下級裁の事務官及び行(二)職は引き続き定員合理化の受け皿とされています。また、定員合理化協力分とは別に医療職72人の定員を減員するとしています。
離婚後共同親権等の導入を見据えて増員が欠かせない家裁調査官については10人の増員要求を行いましたが、家裁の人的態勢整備が求められているもとで全国でたった10人の増員要求というのは到底納得できるものではありません。
事務官についても、これまで「事件処理の支援のための体制強化」として最高裁の増員要求を行ってきましたが、概算要求では、ワークライフバランス推進定員2人の増員要求しか行いませんでした。その一方で、裁判所共済組合の統合等に伴う予算上の措置として「下級裁から最高裁への振替要求を行っている」と説明していることから、デジタル化等の検討・準備のための最高裁の態勢整備は下級裁から引き上げた定員により行われることになります。
メンタル不調や両立支援制度利用の増加で職場のマンパワーが足りない
ここ数年で事件数は増加に転じ、この間の法改正による裁判手続や新たな制度導入への対応が求められるなど、個々の職員の負担が重くなっています。また、職場では、長年に渡る人員削減、育児や介護等の両立支援制度を利用する職員の増加、病気による休暇や休職、急な退職、欠員を補う採用ができていない等により、定員上の配置があっても実際に勤務している職員が少なく、余裕がないことが職場の繁忙度を高める要因になっています。とりわけ中・小規模庁では、もともとギリギリの人的態勢となっているもとで、両立支援制度利用者や病休者等が出るなどした場合に応援等の対応もできず苦慮している実態があります。
メンタルヘルスの不調を抱える職員の増加も深刻です。病休取得者に加えて、職場には短期間の休暇取得や治療を受けながら出勤している職員が相当数いることから、まずはメンタルヘルスを悪化させないための対策を求めていくことが必要です。
地連・支部において、こうした切実な職場実態を対応当局に伝え、職場のマンパワーが足りていないといった実情を踏まえた人員配置を求めていく必要があります。あわせて、そうした職場実態を最高裁に上申するよう追及を強めていく必要があります。
超過勤務について、管理職からの声掛けはありますか?
○最高裁回答の活用とはどういうことですか?
例えば、超過勤務について、最高裁は「適切な超過勤務時間の管理を行うことについて、管理職員に対する指導を徹底するよう、下級裁に対して事務連絡を発出し」たと回答しています。同事務連絡には、「管理職員から部下職員に対し、事前の申告等についての声かけを行う」「部下職員や部下職員の属する係の業務内容や進捗状況を含め適切に管理する」と記載されていますが、職場でこうした声かけ等は行われているでしょうか。超過勤務時間は、各庁の配置定員を検討するための指標となっているものですから、超過勤務が適切に把握されていない職場がある場合は速やかに是正させる必要があります。
また、カスタマーハラスメントに関しても、事務連絡を発出したことを受けて「組織として毅然とした対応も求められること等の認識を広げていくことが重要」と回答しています。
こうした事務連絡の記載に沿った運用が職場で行われていない場合は改善を求めていく必要があります。
TUNAGを組織強化・拡大のツールに
○組織強化・拡大はどのようにとりくめばよいですか?
第82回定期大会決定である「373人の組合員拡大」にむけて、秋段階から全ての地連・支部が全力をあげてとりくむことが求められます。そのためには「新たな組織方針」(「仲間を増やす」「参加する人を増やす」「担い手を増やす」とりくみに全力をあげて、全司法をみんなで一緒に活動する組織に変えよう)に基づくとりくみを着実に実践していくことが重要です。
「仲間を増やす」とりくみとしては、新採用職員の加入拡大はもちろん、役降り職員や非常勤職員の組織化、「年内に対話する対象者」のピックアップと働きかけを提起していますので、全ての支部で一人でも多く組合員を増やすことが求められます。
「参加する人を増やす」「担い手を増やす」とりくみとしては、10・11月に職場会の実施を提起していますので、全ての職場で職場会の実施を追求してください。
「TUNAGForZenshiho」(全司法版ツナグ)は10月1日にリリースしました。ツナグの導入を新採用職員への「セカンドアプローチ」に活用したり、職場会でのテーマにするなど、ツナグを活用して運動を活性化させ、組織強化・拡大をすすめていきましょう。
2026年度裁判所予算案(概算要求)
全司法本部作成
|
| |
 |
| |
|
「ジェンダー平等」の視点から職場の課題を交流
国公女性協秋の全国代表委員会 |
|
| |
|
9月15日、国公女性協2025年秋の全国代表委員会が、加盟する7単組と3県国公・女性協スタッフも含め22名が参加してオンライン併用で開催されました。例年は2日間の日程で開催されますが、今年は他の会議との兼ね合いや暦の関係で、1日の日程となり、参加者は昨年の半分弱でしたが、活発で有意義な討論と交流を行いました。
 |
| 集合とオンラインで22名が参加 |
全司法からも多数参加して発言
午前中は、全司法から国公労連に専従役員として派遣している関口女性協議長から、各単組の状況にも触れながら活動の経過と到達点及び運動方針案の提案があり、午後からは4つの班に分かれ、「ジェンダー平等の社会の実現」等をテーマに分散会が行われました。
1班は全司法の落合が参加し、宿日直におけるジェンダー平等として、以前は女性が割り当てられていなかった日直も女性職員が増えたことに伴い割り当てられるようになったことや、岡山支部での裁判官の泊まり込み令状当番でベッドは男女別に2台あることを発言したことをきっかけに、全医労や国土交通労組から災害対応や非常時における男女別の寝具確保の難しさなどについて話が広がりました。
2班には牧坂女性対策部員が参加しました。男性の育児休業期間が短期間であることや、女性職員数は増えても女子トイレの数は増えていないこと、子どものいない女性の声を拾うことの難しさなどについて話し合われました。
3・4班はオンライン参加者の分散会で、愛知支部の安藤さんと宮崎支部の武藤さんが各県国公の特別代議員として参加しました。生理休暇が取得できない繁忙な職場実態、女性が多い医療職では2級からなかなか昇格できず低賃金となっていること、世の中が平和でないとジェンダー平等は実現できない等の発言がありました。また、組合活動について、休日の会議の在り方や、家庭の中から楽しめる組合活動を見せることの大切さについて発言がありました。
全司法から議長に関口さん、副議長に根本さんを選出
分散会報告後に全体討論があり、各単組の活動報告や組織拡大についての討論を行いました。2025年度の役員体制では、昨年に引き続き全司法から関口香織議長(神奈川支部)と根本厚子副議長(東京地裁支部)が選出されました。全司法として引き続き全力で二人を支えていきます。
|
| |
 |
| |
|
新連載 大丈夫?裁判所のデジタル化 第1回
パソコンのスペックが不足している?! |
|
| |
|
ウインドウズ11アップグレードで感じたこと
ウインドウズ11のアップグレードに伴い、その後の債権執行システムのインストール時に、手順書に記載がない画面が表示される、ポップアップブロックが頻発して作業が止まる、インターネットが閲覧できなくなる、文字変換が出来なくなる等の問題が多発しています。
また、アップグレード後、パソコンの挙動が重くなったという印象を抱く職員が非常に多く、アプリ版のチームスはもちろん、ブラウザでの作業についても支障が出ることがあり、職員に支給されている端末について、ウインドウズ11を安定、軽快に作動させるスペックを満たしていないことがうかがわれる事態となっています。
本来、ウインドウズ11へのアップグレード、GSS環境の導入と、デジタル化に対応した十分な性能を持つ職員端末の更新は一体であるべきですが、端末更新が先送りとなったことが問題であるところ、現在の端末で勤務時間管理のシステム化、民事訴訟手続デジタル化のフェーズ3、刑事手続のデジタル化を迎える形となれば、端末のスペック不足によって、勤怠管理事務が滞る、裁判事務に支障が出る等の問題が発生することが容易に想像できます。早期の端末更新等、事務の停滞を避けるための対策が求められます。
|
| |
 |
| |
|
ベテラン職員の処遇改善を強く要求
10月昇格期最高裁交渉 |
|
| |
|
10月昇格期最高裁交渉
全司法本部は9月18日、「2025年10月期における昇格改善要求書」に基づき、最高裁棈松人事局総務課長と交渉を実施しました。交渉に先立ち、各地連・支部から集約した昇格該当者名簿を提出しました。
人勧や定年引上げの影響についても回答せず
10月期の定数配布について、4月期と同様の基準で配布したのか追及しましたが、発令前であることを理由に回答しませんでした。
また、今年度の人事院勧告と同時に出された報告にもとづいて来年4月から実施が予定されている在級期間に係る制度の廃止が最高裁の定数配布基準に与える影響はあるのかを追及しましたが、これについても、明確な回答は行いませんでした。
公判部専門職等の事務官以外の処遇水準について、定年年齢の引上げにより、影響が出ていないのかを追及しました。事務官5級の占有期間が延長されず、60歳となる年度に5級昇格ができず、昇格時期が後退していますが、これと同じことが、例えば書記官5級(占有2年、58歳昇格が実績だと思われる)で生じていないか懸念されています。これに対して「問題意識は理解した」と回答するのみでした。
「新たな類型の専門職」発令の拡大などを要求
行(二)職については、部下数制限により従前の発令実績から明らかに後退している事実をあらためて指摘し、人事評価で仕事ぶりを適切に評価して賃金に反映させるなど、処遇を後退させないための方策や展望を示すよう追及しましたが、従前回答を繰り返しました。
事務官についても、従前回答を繰り返したのに対し、ベテラン職員の処遇改善を強く主張しました。特に50歳前後の3級職員について、昇格を意識した配置や指導を行うとともに、新たな類型の専門職ポストを拡大することで4級昇格を実現するよう求めました。
昇給停止、昇給「頭打ち」などの影響を追及
事務官は、3級の長期在級者が全国的に多く、55歳を過ぎて昇給停止となっている職員も少なからず存在します。また、55歳になる前に最高号俸に達して、事実上の昇給停止となる不利益を被る職員もいます。人事評価で上位の評定を多く得た職員ほど早く最高号俸に達し、より長期に不利益を被っています。このような制度上の矛盾を生じさせないよう、最高号俸に達する前に昇格させるよう強く求めました。
なお、10月期の占有期間を限定的に延長する枠組みによる昇格発令予定者数については「0又は1」と回答しました。
|