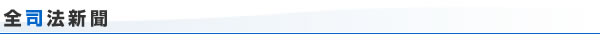 |
| |
|
�f�W�^�����̉ۑ�����L�A�Y���ٔ��f�W�^�������l����W���
��S�R��i�@���x�����W�� |
|
| |
|
�@6��22���A��43��i�@���x�����W����I�����C���ŊJ�Â��܂����B���̏W���2�N�Ɉ�x�J�Â��Ă��܂����A����́u�ٔ����̃f�W�^�����A���Ə����v�Ƒ肵�A�E��Ői�߂��Ă����ٔ����̃f�W�^�����ɂ��āA����Ɖۑ�����L����ƂƂ��ɁA�Y���ٔ��̃f�W�^�����ɂ��Ċw�сA�S�i�@���v�����Ă���u�ߏ�Z���^�[�\�z�v�ɂ��ċ��L����W��Ƃ��܂����B�W��ɂ�64�����Q�����܂����B

64�����I�����C���ŎQ��
�ٔ����̃f�W�^������
�i�@���x���v�ȗ��̑�]��
�@�W��ł́A�ŏ��ɒ���ψ�������A�S�i�@���u�����̂��߂̍ٔ��������v�Ƃ����^�����j���f���Ă���Ӌ`�ɐG��A���̒��ł���u�i�@���x���������v��J���������P�Ɓu�Ԃ̗��ցv�Ƃ��ĂƂ肭�ނ��Ƃ̏d�v�����q�ׂ�J�����������܂����B
�@�����āA�W��̊�u���Ƃ��āA�@���R�c��E�Y���@�i���ʐM�Z�p�W�j����̈ψ��Ƃ��ČY���ٔ��̂h�s���̐R�c�Ɋւ��ꂽ�ٌ�m�̋v�ۗL��q����Ɂu�Y���葱�̂h�s���`���̂��߂ɍs�����`�v�Ƃ����e�[�}�ł��b�����������܂����B
�@�S�i�@�{�������2�̂̕����A�u�ٔ����̃f�W�^�����A����܂ł̌o�߂ƍ���̉ۑ�v�Ƃ����e�[�}�ŕ����������s�ψ��i���L���S���j�̓���֎i����́u�����o�c�e�����邱�Ƃ��f�W�^�����ł͂Ȃ��v�Əq�ׁA�u�ٔ����̃f�W�^�����͎i�@���x���v�ȗ��̑�]�������v�Ƃ��āA�u�����̂��߁v�̃f�W�^�����ƂȂ��Ă��邩�A�������Ď����ʂ������Ă��Ȃ����A�l���炵�̌����ɂȂ��Ă��Ȃ����A�u�u���Ă��ڂ�v�ɂȂ��Ă���E���͂��Ȃ������̎��_���猩�Ă����K�v������Ǝw�E���A�u�킽�������̗͂Ŗ����̍ٔ��������肠���悤�v�ƌĂт����܂����B
�@�u�ߏ�Z���^�[�\�z�v�ɂ��ĕ�����㏑�L���́A�E���̕��S�ʂ��猻�݂̏h�����ɂ��ߏ������E�ɂ��Ă���Ƃ��āu�h�����E�A�����̐��������������ɂ��Ă���v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA�@���R�̗v�j���q�i�āj�ɗߏ�̃I�����C���������荞�܂�Ă��邱�ƁA�ō��ق��Y���̃f�W�^�����̂��߂̃V�X�e���J���ɓ��낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ���āA�u�Y���葱�̃f�W�^�����͑S�i�@�����N�v�����Ă����w�ߏ�Z���^�[�\�z�x�����̍ő�̃`�����X���v�Əq�ׂ܂����B
�y��u���̗v�|�z
 |
| �v�ۗL��q�ٌ�m |
�Y���ٔ��h�s��
��^�ҁE�퍐�l�̌������ʼn߂���Ă͂����Ȃ�
�d���I�L�^���߁A�I�����C���ڌ�������
�@�`���A�v�ۂ���͌Y���ٔ��̂h�s���ɂ��āu�����S�̂ɂƂ��ăv���X�ɂȂ�葱�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�����Ƃ����̂͑S�Ă̍����ł���A��^�ҁE�퍐�l�����R�Ɋ܂ނ��Ƃ��ʼn߂���Ă͂����Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B
�@�܂��A���٘A�͖@���R�̕���I�������i2023�N12��18���j�ɉ�������o���A�@���R���Ƃ�܂Ƃ߂��v�j�i���q�j�Ă̑S�̂ɔ����闧����Ƃ��Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A���̍ő�̗��R�Ƃ��āA�d���I�L�^���߂ƃI�����C���ڌ��������܂����B
�@�����āA�v�j�i���q�j�Ăɉ����āA�ȉ��̂Ƃ���|�C���g���������܂����B
�P�D�i�ׂɊւ��鏑�ނ̓d�q��
�@�����������ɂ��ẮA�V�X�e������̕���������̂ł͂����肵�Ȃ����A�����ł͐i�s�Ɋւ����`�[���Y�ŋ��L����ď������Ă���̂ŁA�Y���ł����L�ł���Ε֗��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă���B�@���R�ł́A�q��̉����f�[�^����������A���F�߂�����肪�����ƈӌ����q�ׂ��B
�@���ޓ��̉{���E���ʂɂ��āA�d���I�L�^�ɂ��Ắu�����K�v�v�Ƃ������ƂɂȂ�A���ӎ��������Ă���B�I�����C���Ő\����������āA��{�I�ɂ͓��ʂ�F�߂�ׂ��ł͂Ȃ����B
�@�\���ē��ɂ��āA�I�����C�����`���t����ꂽ�����Ƃ͈Ⴂ�A�Y���͐g�̍S��������̂ŕK�����������Ɠ����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�@���R�ł͑��ӂɂȂ��Ă����B�ٔ����Ƃ��Ă͈ꌳ���ł��������悢�Ǝv�����A�Ⴆ�A�����ɂo�c�e���ł���@�킪�ݒu�����A�o���ɂƂ��ėǂ��̂ł͂Ȃ����B
�@������ł́A�{���L�^���o �c�e�Œ�o�����̂ŁA�u�����؋����ׂ̑ΏۂɂȂ����̂��v�Ƃ�����肪������B�v���p�e�B����܂߂āA�L�^�㖾�����ė~�����ƍl���Ă���B
�@���q�̓��e���L�^�����d���I�L�^���ɂ��āA�d�q�f�[�^��������₷�����Ƃ͋��ʔF���ɂȂ��Ă������A��������̑�֑[�u���܂߁A������Ȃ��S�ۂ��ǂ�����̂����킩��Ȃ��܂܁A�R�c���I������B
�Q�D�ߏ�̔��t�E���s���Ɋւ���K��̐���
�@���Ƃ��ƌ����I�����C���Ƃ����b�������͂����A�{���@�ւ��I�����C�������������R�ɑI�ׂ�悤�Ȃ܂Ƃ߂ɂȂ��Ă���B�{���@�ւɓs�����ǂ����邤���ɁA�ٔ����̎������p���N���Ă��܂��̂ŁA�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͋��L����Ă���͂������A�K����͎��R�ɂ��邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@���s�Ɋւ���āA�f�[�^�Ȃ̂Łu�������ꂽ�̂��v�������܂��ɂȂ�B�ł��錠�͍s�g�̏�ʂȂ̂ŁA������h�~�A���t���ꂽ�ߏ�̉���A�������ꂽ�̂����ł���d�g�݂����ׂ��B
�R�D�d���I�L�^������鋭�������̑n��
�@�{���@�ւ��n�[�h�f�B�X�N���������čs���ăf�[�^��ۑ����A�����������������u�L�^���ߕt�������v�̐��x����������Ă��邪�A�����͂�����I�����C���łł���悤�ɂ������Ƃ����b�ł������Ƃ���A���������������Ƃő���ɂȂ����B
�@�u���������f�[�^������͂�������A�o���Ă��������v�Ƃ������e���������ƂɈقȂ�A�u�����o���Ȃ����Ɓv�������̑ΏۂɂȂ邩�킩�炸�A�W�Ȃ��f�[�^�܂Œ�o���邱�ƂɂȂ��肩�˂Ȃ��B
�@�܂��A�N���E�h���Ǝҁi�O�[�O���Ȃǁj�������l�ɂȂ����ꍇ�A�{�l�i���ی��́j���m��Ȃ����ŏ����Ƃ�ꂽ��A��t��ٌ�m�̋��⌠��A���ȕ��ߋ��ۓ������s�g�ł��Ȃ��Ȃ�B���R���E�R���͂ł��邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A���̎��������S�ۂ��ꂸ�A���������\���Ẵ`�����X����Ȃ���������Ȃ��B
�@����ɁA���������f�[�^�̗��p�A�ۊǂ̃��[�����Ȃ����߁A�ƍ߂Ɩ��W�ȍ����̏����܂߂đ{���@�ւɎ��W�E�~�ρE���p����邨���ꂪ����A�v���C�o�V�[���̐N�Q��A�J���g���E�s���c�́A���}�A�@�֓��̊����Ď��̂��߂Ɏg����̂ł͂Ȃ����Ƃ����������������B
�S�D�葱�̃I�����C�����Ɋւ������
�@�ى�^����������̓I�����C���łł��邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A�I�����C���ڌ�������ė~�����Ƃ����ٌ�m��̗v�]�͎�����Ȃ������B�ڌ��́A�����S�u���ł͓����n�����g���āA������A�I�����C���łł��Ă���̂ŁA�ł��Ȃ����R�͂Ȃ��B�ى�^��������������̂ł���A�ڌ��ŗL�̗\�Z������قǕK�v�Ȃ��͂��B�Ƃ�킯�A�n���ł͂����ւ�Ȏv�������ĕٌ슈��������Ă���̂ŁA�i�K�I�ɂł����Ў������ė~�����B
�@�����O�����葱�͗��p�ł���Ǝv�����A��]����Δ퍐�l���o�Ȃł���悤�ɂ��A�ٌ�l�Ƃ��R�~���j�P�[�V�������Ƃ��悤�ɂ��Ă��炢�����B�܂��A�I�����C���Ō������������ꍇ�A�o�삵�����Ƃ����퍐�l�̊�]�������Ă��F�߂Ȃ����Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ��Ă���͖̂��B
�@�ٔ����I�C�葱�͌��@���E�@���Ȃ��o�������́B���҂̎����͂ł��Ȃ��̂ŁA�ꏊ���m�ۂ��Ȃ���Ȃ炸�A���悻�����I�ł͂Ȃ����A�Ȃ������̂܂ܓ����Ă���B
�@�ؐl��Ӓ�l�̐q��Ȃǂɂ��ẮA�Ζʂł��K�v�����������̂�����A���ӂł���P�[�X�ł���Ηǂ����A��������悤�Ȃ��Ƃ͂�߂Ă������������B�O�����ݏؐl�̐q��͂ł���悤�ɂ��ė~�����ƌ��������A������Ă��܂����B�ʖ�l�́A�m�ۂ�����P�[�X�ȂǁA�퍐�l�ɂƂ��ăv���X�ɂȂ�Ηǂ��Ǝv���B
�@�u���̂܂Ƃ߂Ƃ��āA�v�ۂ���́u�h�s���ƌ����Ɨ����ɖڂ��������������A��^�ҁE�퍐�l�̐l������ς�����Y������^������̂��Ƃ������Ƃ��ӎ�����O���Ă͂����Ȃ��A�@��ْ̋����̒��ł�邱�Ƃ̏d�v���A�ΖʂŘb�����Ƃ̏d�v���͊ԈႢ�Ȃ�����v�Ǝw�E����ƂƂ��ɁA�u�h�s�����p���āA�ł���Ƃ���͏_��ɂ������Ƃ������Ƃٌ͕�m���v���Ă���̂ŁA����Ƃ��ӌ��������Ȃ���A���ǂ��Y���i�@��ڎw���Ă�����Ǝv���Ă���v�Əq�ׂču������߂�����܂����B
��������ɂ���
�i�Q���҂̎���ɓ����āj
�@��^�ҁE�퍐�l�͍ٔ��̎葱���ɏڂ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�ǂ��Řb���������v�Ƃ����ꏊ�̈Ⴂ�Ŕc�����Ă���Ƃ��낪����B�ꏊ���ړ�����̂͏d�v���ƍl���Ă���B�I�����C���̌�������ɂ��āA�ٔ��������ɗv�]����Ă����l�q�ł͂Ȃ������B
|
| |
 |
| |
|
�u�E���̕��S�v�ŏ���p���͉��߂�ׂ�
�V�^�R���i�����ǂ̓��ʋx�ɂ̉^�p�ɂ��� |
|
| |
|
�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����g�傪�����Ă����ߘa4�N�����A���ُ��]�x���y�я��]�n�ƍيǓ��ł́A�Z���ڐG�҂Ƃ��ĕی�������O�o���l�v�������E�����A���ǂ��������ҋ@�𖽂���ꂽ�ɂ��ւ�炸�A���ʋx�ɂ̑Ώۂł͂Ȃ��Ƃ���A�N�x���擾������Ŏ���ҋ@���s���Ă��܂����B���ɂ͓����Ƒ������đ����Ɋ�����������2�T�Ԃ��N�x���擾���Ă̎���ҋ@��������ꂽ�������܂����B
�@���N3���A�ō��ق͑S�i�@�ɑ��A���ʋx�ɂƂ��邽�߂ɂ͊����ǖ@�Ɋ�Â��O�o���l�v����E������K�v�����邪�A�O�o���l�v���������ǖ@�Ɋ�Â��v���ł������Ɠ��ǂ��m�F�ł����̂��ߘa5�N3���ɓ����Ă���ł���A�����͊����ǖ@�Ɋ�Â��v���ł���Ƃ̔��f�͂ł��Ȃ������B�܂��A�N�x�͋����������̂ł͂Ȃ��̂ŁA���ʋx�ɂւ̐U�ւ��s�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ��܂����B�����A�O�o���l�v���̍����ǂ��m�F�ł��Ȃ������͓̂��ǂ̎藎���ł���A�����������ǂ̔F���Ƃ͊W�Ȃ������ǖ@�Ɋ�Â��O�o���l�v����E���͎Ă��܂����B�܂��A�N�x���������Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����A�E���͓��ǂ��玩��ҋ@�𖽂�������ۂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A�ݑ�Ζ��𖽂����邱�Ƃ��Ȃ���A���ʋx�ɂ̑Ώۂł������Ƃ̐����ǂ���Ă���A������ꂽ����ҋ@�����s���邽�߂ɂ͔N�x���擾����ق�����܂���B
�@�{���ɂ��āA�����J�A�����ʋx�ɂ����F���Ȃ��������Ƃ͓��ǂ����r�ł����ē��ʋx�ɂւ̐U�ւ��K�v�Ƃ̔F���������Ă��܂��B���ǂ́A�x����n�A�̒Njy�ɂ��u�ݑ�Ζ��𖽂��Ȃ��������Ɓv�ɂ��Ă͎Ӎ߂��܂������A���̑��̑Ή��ɂ͖��͖��������Ƃ��āA���ʋx�ɂւ̐U�ւɂ��Ă͍s��Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B�������A�N�x�̎擾���������Ă������Ƃ��͂��߂Ƃ��ē��ǂ̑Ή��͂ނ����肾�炯�ł���A�ō��ق̉�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�����x��������ō��قɑ��Ĕ��_�����o���A�ō��قɉ����߂�悤���߂Ă��܂��B
�@�{���́A�����邲�ƂɔN�x�擾�ȂǐE���̕��S�ŏ��낤�Ƃ��铖�ǂ̎p�����@���ɕ\�ꂽ����ł����A���̂悤�Ȏp���͉��߂�����K�v������܂��B
|
| |
 |
| |
|
|
|
| |
�@6��27���A�ٔ������ϑg���̌��Z�^�c�R�c��J�Â���܂����B���N�x�̊������قڏI�����邱�Ƃ���A�S�i�@���E�̈ψ��݂̂Ȃ���Ɋ��z�������������܂����B
���ߍׂ₩�Ȕz�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃւ̕s��
�i�H�c�E��֏��q�j
 |
| �S�i�@���E�̉^�R�ψ��Ɗč��� |
�@�O��ψ��߂�������A�傫�ȈႢ���������̂��x���̓����ł��B����܂Ŋe�x���ŒS���҂����ߍׂ₩�ɔz�����Ă���Ă������̂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃɕs�����o���܂��B
�@�}�C�N���\�t�g�R�U�T����������A�l�X�ȏ�ʂŎ�����������Ƃ�ɂ������Ƃ���{�ƂȂ��Ă��Ă��܂��B�u�����蓖�̐��������ɊԂɍ��킸�ł��Ȃ��Ă����ȐӔC�v�ƂȂ�Ζ��ł����A�S���̑Ώێ҂�{�����c���ł��邩�ǂ������^��ł��B
�@����A�������i�ނɂ�����Njy���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ肾�Ǝv���܂��B
����ی��w���̎��{���Ⴍ�A�����P���~���H
�i�����n�فE���c���C�j
�@����ی��w���̎��{�����Ȃ��Ȃ����P���ꂸ�A�Q�O�Q�R�N�x�̎b��l��O��Ƃ���ƁA�Q�O�Q�U�N�x�ɍٔ������ϑg���ɉۂ����������Ҏx�����̉��Z�z���P���~���錩���݂ł��邱�Ƃ����炩�ɂ���܂����B�����������N�̈ێ��E���i��ړI�Ƃ��鐶���K���a��ɔ����I�^�p����������Ă��邱�Ƃ����ł����A���{���̌���͋i�ق̉ۑ�ł��B
�@�܂��A�������يǓ��̑S�x�����p�~����Ė{���ɓ�������܂������A�퓝�����̑g�����̐��Ƃ��āA���ϑg���{���͊��ӂ�]�����ꂽ���Ƃ݂̂��������Ă��܂��B�������A�퓝�����̑g�����̈ӌ���]�����{���͂ǂ��Ȃ̂��A���߂Ē�������K�v���������Ă��܂��B
�u���������v��͂ނ̂͑����قǂ悢
�i���m�E�{�c�Y��j
�@�^�R�ψ����o�����āA���ϑg���Ɋւ���m����u���������v��͂ނ̂͑����قǂ悢�Ɗ����܂����B
�@�m���郁���b�g�͂Q����A�P�͐l���ɖ𗧂Ƃ������ƁA�����P�͋��ϑg�����x�����ǂ�����u���������v�ɂȂ邱�Ƃł��B
�@���x��ǂ�����ɂ́A���[�U�[�̐����Ǘ��҂ɓ͂��邱�Ƃ����ʓI�ł��B���ɁA���l�Ȏ��_������萢��̈ӌ��́A���ϑg���A�Ђ��Ă͍ٔ����̖��͂����߂邱�Ƃɂ��Ȃ���܂��B
�@�F������������͂߂�悤�A������A�g����������ʂ��Ď��g���ψ���ʂ��ē����m���M���Ă��������Ǝv���܂��B
�d�����炵�����ǂ����̂ɂ��邽�߂�
�i�L���E���{���Y�j
�@���ϑg���́A�g�����̎d�����炵�����ǂ����̂ɂ��邽�߂ɂ���A���̑��݉��l�͘J���g���Ǝ����Ƃ��낪����ƌ����܂��B
�@�S�i�@�̐��E�ɂ��C�����ꂽ�������ψ��́A���ϑg���������Ƃ����Ɨ��p���l������K�v���̍������݂ɂȂ�悤�A�^�c�R�c��ŗl�X�Ȉӌ����q�ׂĂ��܂��B�@�����̑��̐����蒼���ɉ��P����鎖���͏��Ȃ��̂������ł����A������S�苭���\���q�ׂĂ��������Ǝv���܂��B
|
| |