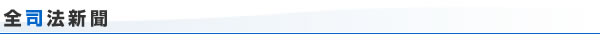 |
| |
各種課題で到達点を築く
要求の前進めざし運動の強化を |
|
| |
全司法は、10年諸要求貫徹闘争として、増員、「国民のための裁判所」、健康管理などの職場諸要求の前進をめざし、組合員一人ひとりの上申書提出行動や所属長交渉などの上申闘争、2次にわたる全国統一職場大会、職種・階層による署名などの各種行動を展開し、最高裁給与課長交渉、山場となる三局・一課、人事局長、事務総長との各交渉を実施しました。
全司法本部は、6月21日から24日まで、最高裁総務局、人事局、経理局、情報政策課との三局・一課交渉、人事局長交渉及び事務総長交渉を実施し、全国統一要求の前進に向けて追及を強めました。
その結果、増員要求の姿勢について、「平成23年度の増員を巡る財政当局との折衝はこれまでにない極めて厳しいものになる」と従来以上に厳しい見通しを示しながらも「必要な人員の確保に向けて最大限の努力をしていきたい」との姿勢を示しました。予算要求に当たっては、「家裁や支部・簡裁、検審を含めた職場の実態」や「職員団体の要望等を十分にふまえた上」、「職員の休暇等の取得や健康管理の面にもきめ細かく配慮」していく姿勢を示しました。
検察審査会制度等については、「職員団体の意見も踏まえながら引き続き態勢の整備に努めていきたい」との姿勢を示しました。
公務員制度、人事評価制度については、引き続き誠実対応を確認しました。また、級別定数の改定に向けては、「最大限の努力」姿勢を示しました。
この他にも職員制度、健康管理、超過勤務縮減等の各種課題についても到達点を築くことができました。
これらの交渉結果を踏まえ、7月15日に全国統一昼休み報告集会を開催し、到達点と課題の確認、秋に向けた運動の意思統一をはかります。
|
| |
 |
| |
|
|
|
| |
|
増員・欠員補充
次年度の増員要求について、「財政当局との折衝は、これまでにない極めて厳しいものになる」との認識を示しました。その上で、「裁判所の執務実態と裁判部門の充実強化のための人的態勢の整備の必要性を粘り強く主張」していき「必要な人員の確保」に向けて「最大限の努力をしていきたい」との最大限の努力姿勢を示しました。
「国民のための裁判所」の実現
裁判員裁判については、「今後、複雑な否認事件等の審理が本格化する中で、制度が適切に運用できるよう努めていきたい」としました。また、検察審査会制度等について、「より適切に運営できるよう職員及び職員団体の意見も踏まえながら引き続き態勢の整備に努めていきたい」としました。
時短・健康管理等
健康管理に関わって、「職員の健康管理については、引き続ききめ細かな配慮をするとともに、職員が健康で働きやすい職場環境の維持により一層努めていきたい」としました。また、超過勤務縮減については、「今後とも超過勤務縮減のための具体的な取組の実施や年次休暇等をより一層取得しやすい環境の整備に向けて、引き続き下級裁を指導していきたい」としました。
公務員制度・労働基本権
労働基本権については、「引き続き政府の検討状況を注視」、定年延長やそれに伴う給与制度の見直しの問題について、「職員及び職員団体の関心が高いことは承知している」、人事評価制度については、「客観性、公正性、透明性、納得性の高い制度として運用され、人材育成や執務意欲の向上に資するものとなるよう努めていく」とし、これらの各問題についての誠実対応を確認しました。
職員の処遇改善
級別定数の改定については、「財政当局との折衝は年々厳しさを増している」としつつ、「引き続き最大限の努力をしていきたい」との姿勢を示しました。
権利
全司法との誠実対応について、「今後もそのような方針に変わりはない」とし、「下級裁当局に対しても、職員団体に対して同様の方針で臨むよう、その指導を一層徹底していきたい」としました。 |
| |
|
最高裁人事局長交渉
必要な人員の確保に最大限の努力 |
|
| |
全司法本部は、6月22日、最高裁大谷人事局長と交渉を実施しました。増員、国民のための裁判所、昇格などにわたり追及し、最高裁から人員確保に向けた最大限の努力姿勢や級別定数改定に向けた最大限の努力姿勢などを引き出しました。
裁判員裁判
普段の検証、意見要望把握し運用に反映
増員について、次年度予算要求における基本姿勢を明らかにするよう求めたのに対し、「平成23年度の増員を巡る財政当局との折衝はこれまで以上に厳しくなる」という認識を示しつつ、「司法需要への的確な対処、適正迅速な裁判を実現する」に「必要な人員の確保に引き続き最大限の努力をしていきたい」と最大限の努力姿勢を明らかにしました。また、小規模家裁本庁、地家裁支部及び簡裁の人的整備については、「担当者が少数であること、書記官等が多様な業務を担当しているといった事件処理の実情等を配慮」していくとしました。地簡裁の民事部門及び家事部門への人員配置に関わっては、「事件数のみならず当該部署の事務処理状況等の種々の要素を総合的に考慮」していくとしました。
一方、定員削減に関わっては、「裁判部の充実強化を図っていく」ために、「定員削減に協力すべきところは協力していく必要がある」という従来の姿勢を示しました。
裁判員裁判に関わっては、「実施状況の不断の検証や裁判員等からの意見・要望等を把握し、運用に反映させていくことが必要」との認識を示した上で、「検討状況は、これまで同様、職員・職員団体に説明していく」としました。
また、検察審査会の充実について、「今後とも国民の期待する機能と役割が果たせるよう必要な措置を講じるべく努めていく」としました。
健康診断
安定的実施のための予算確保に努力
超過勤務縮減については、「今後も組織全体で超過勤務縮減の取り組みが求められており、引き続き下級裁を指導」、「超過勤務縮減をすすめるにあたって、サービス残業や持ち帰り仕事が生じないよう一層下級裁を指導」、「サービス残業、持ち帰り仕事はあってはならない。管理職員に対する指導を徹底したい」としました。
また、60時間を超える超過勤務を行った場合の代休時間の指定については、「職員の意向を確認するよう下級裁に対して指導している」としました。
健康診断の充実については、「今後も健康診断を将来にわたって安定的に実施するために必要な予算を確保できるよう努力していきたい」とし、地域実情に応じて全ての職員が受検できる環境を整えるべきとの主張に対して、「様々な難しい問題もあるが、職員が広く受検できるための態勢整備に向けて知恵を絞っていきたい」と前向きな回答をしました。
人事評価シートによる評価
職員に十分な説明が行われるよう配慮
労働基本権に関わっては、「具体的な措置が図られる際には、裁判所の組織の特殊性や職員の職務の特性を踏まえながら、適正に対応」、「これまで同様職員及び職員団体と誠実に対応」と引き続き誠実対応を確認しました。
今年の秋から本格運用される人事評価シートによる評価については、「人事評価シートによる評価制度の理解を深めてもらうため説明会を実施するなど、職員に十分な説明が行われるよう配慮」、「評価者が評価を行う上で参考とするための各種執務資料の整備を行い、評価者の評価能力、面談技法の維持、向上を図りたい」としました。また、「新たな人事評価制度の本格実施やその運用に当たっては、職員及び職員団体と誠実に対応」との姿勢を確認しました。
高齢期雇用の具体的な制度設計の検討の際の誠実対応姿勢を確認しました。
働きやすい職場環境の整備に努める
職務評価の向上については、「裁判所の官職に与えられた職責や期待される役割に応じて、それにふさわしい評価が与えられるよう努力してきたところであり、今後も同様の努力を続けたい」としました。
医療職員の問題については、「引き続き職員及び職員団体と誠実に対応していきたい」との誠実姿勢を示しました。また、「職員団体の要望も踏まえ、高裁医務室の常勤看護師に対して、1人1台の割合でパソコンの配付とウェブ閲覧権限を付与する方向で検討」することを明らかにしました。
採用試験の見直しについては、「人事院による意見集約結果の公表からそう遠くない時期に裁判所職員採用試験の見直しの概要を公表したい」としました。
第2期裁判所特定事業行動計画に関わって、「ワーク・ライフ・バランスの視点から、全職員が職場全体における仕事のやり方を見直し、働き方を変えていくことで、職員全体にとって働きやすい職場となるよう環境整備に努めていく」、女性職員の登用拡大については、次期拡大計画を検討するための基礎資料とするため、「前回同様に職員を対象とした意識調査を行うことも検討」することを明らかにし、その際、「職員団体の要望も踏まえて意識調査のあり方を検討」したいとしました。
母性保護のための権利行使については、「管理職員等の研修等を通じて、権利行使の重要性を認識させるとともに、権利行使が認められている趣旨を更に徹底し、取得しやすい環境作りをしていくよう指導していきたい」としました。
級別定数改定に向け最大限の努力
級別定数の改定については、「平成23年度予算折衝においても、総人件費削減などの基本方針の下に財政当局の姿勢が引き続き厳しいものとなることは必至」、「平成23年度予算における級別定数改定を巡る情勢は全く予断を許さない」との認識を示しつつも、「職員の勤務条件にも配慮しながら最大限の努力をしていきたい」との最大限の努力姿勢を示しました。 |
| |
|
| 最高裁3局(総務・人事・経理)、1課(情報政策課)と交渉 |
|
| |
|
人事局交渉
超勤縮減全体で取り組む課題
引き続き管理職を指導
人事局交渉は、6月21日、超過勤務縮減、健康課題などについて行われました。
超過勤務縮減については、「国民の公務コストに対する問題意識がかつてないほど高まっている」とし、「事務の簡素化・合理化、業務プロセスの見直し、事務の繁閑に応じた機動的な応援態勢の構築等組織全体として超勤縮減に取り組むことが求められている」との認識を示した上で、「管理職員に対して、部下職員の事務処理状況等をきめ細かく見て、事務の簡素化、合理化に向けた具体的な指導を行うとともに、職員に対して意識改革を徹底するよう指導している」としました。また、「サービス残業や持ち帰り仕事はあってはならない」、「そうしたことがないよう超過勤務について的確、遅滞なく把握するよう管理職員を指導する」としました。
健康管理に関わって、パワーハラスメントは、明らかな違法行為等は別として、業務上の指導との明確な線引きが難しいとはしつつ、「働きやすい職場環境の維持・運営の障害となる」、「職員の意欲の減退、メンタル不全の要因ともなりかねない」とし、「あってはならないこと」としました。また、「管理職員研修で、面接技法、傾聴法等についての講義を用意するなど、引き続き意識啓発、知識付与に努めたい」としました。
労働基本権については、引き続き誠実対応を確認し、人事評価制度については、制度への職員の理解を高めることの必要性の認識を示しました。高齢期雇用については、現在情報はないが、「入り次第示したい」としました。
宿日直に関わって、宿直明けの代休制度については、「職務専念義務の免除を認める規程がない以上、困難」としつつ、深夜・早朝に及んだ場合には、年休の取得を促すことや、年休取得の上で仮眠休憩場所を提供している庁があることから「工夫例の情報提供などをして、職員の負担軽減に向けて引き続き指導していきたい」としました。
人事・給与情報システムの導入スケジュールは検討中とし、システムの概要を近日中に説明するとしました。
総務局交渉
定員巡る情勢の厳しさを強調しつつ必要な人員の確保に努力
総務局交渉は、6月21日、増員、「国民のための裁判所」実現、職員制度を中心に行われました。
増員に対する積極姿勢を求めたのに対し、「厳しい財政状況の中で幅広く国民の理解を得ていくためには、事務の合理化、効率化等による内部努力は不可欠」とこれまで同様の認識を示し、増加している事件がある一方で減少している事件もあるという事件数の動向、国家公務員の定員を巡る情勢から、「平成23年度の増員を巡る財政当局との折衝はこれまで以上に厳しくなる」との認識を示しました。その上で、「多種多様な要因を総合的に考慮」としました。また、地簡裁の民事立会部門、家事部門の人員配置については、「事件数のみならず当該部署の事務処理状況等の種々の要素を総合的に考慮し、適正な人員配置に努めていきたい」、小規模家裁本庁、支部・簡裁については、「書記官等が多様な業務を担当しているといった事務処理の実情等を踏まえた配慮」をし、「効率的な事務分配の検討や支援態勢の強化などの検討も含めて事務処理状況等を考慮しており、その上で人的手当が必要とされた場合に書記官等の増配置を行っているものと認識」しているとしました。また、裁判員裁判の態勢整備について、「事件数が減少傾向にあることが直ちに刑事部からの人員シフトに結びつくわけではない」との認識を示しました。
書記官の増員については、「必要な人員の確保について引き続き努力していきたいと考えている」、調査官の増員については、「これから検討していくことになる」としました。
労働審判事件については、審判員の増員を図るなど事件増へ対応していることを明らかにした上で、「今後も事件数の動向や事務処理状況等には注視していきたい」としました。非訟事件手続法や家事審判法の改正に伴う情報提供について、「引き続き必要に応じ各庁に情報を提供し意見交換を行っていきたい」としました。
研修環境の整備ついて、「充実に努めていきたい」としました。
経理局交渉
庁舎の耐震対策
引き続き最大限の努力
経理局交渉は、6月21日、予算要求、庁舎、宿舎などの課題について行われました。
次年度予算要求に当たっては、「適正迅速な裁判の運営に必要な予算確保に向けて努力していきたい」との姿勢を示しました。また、最高裁は、下級裁から適宜の方法で要望等を聴取していることから「常日頃から現場の意見等を下級裁当局に伝えてもらいたい」としました。
庁舎の新営・増改築にあたっては、「部屋の配置等の計画作成に当たっては、職員及び職員団体の意見は十分聴取すべきであると考えている」とし、「今後ともこの趣旨を徹底したい」としました。
司法制度改革に対応した庁舎の充実について、「今後も新たな制度の運用に支障がないよう既存の設備等の有効活用を図るとともに、事件関係者のみならず職員の働きやすさにも配慮した上で、必要な整備を計画的に行っていきたい」としました。
老朽・狭隘庁舎の新営・増築については、「職員の勤務条件に関わる問題として、常に関心を持って努力しているところであり、今後も必要性・緊急性の度合いや当事者の利便を考慮しながら必要な予算を確保したい」としました。
耐震対策については、「今後も最大限の努力をしていきたい」との姿勢を示しました。
宿舎については、「今後も必要な宿舎戸数を確保するよう努めていきたい」としました。
SEABIS(シービス)については、「具体的な導入展開スケジュール等について示せないが、引き続き、会計課職員等に情報提供できるよう情報収集に努めたい」としました。
情報政策課交渉
IT化 職員の意見要望等の確実な把握が重要
裁判所全体にとって有益となるよう努力
情報政策課交渉は、6月21日、ITシステム化への対応を中心に行われました。
次期情報化戦略計画の策定について、「変化する社会情勢や環境に対応しつつ、最近のIT技術の動向も踏まえて、より使いやすい情報システムが構築できるよう検討していきたい」とし、その際には「職員及び職員団体の意見、要望等の把握に努めたい」としました。
IT情報システムの開発・導入及び現行システムの改善について、「実際にシステムを使用する職員の意見や要望等を確実に把握することが重要」との認識を示した上で、「今後も裁判所における情報化投資がシステムの利用者の意見を反映し、裁判所全体にとって有益なものとなるよう努めていきたい」としました。
IT情報システム部門の組織体制整備については、「まだ知恵を絞っているところであり、何ら説明できるものはない」としました。
職員に貸与しているパソコンの更新時期については、「当該パソコンで利用することになる業務システム等のOSへの対応状況やそのときどきの予算状況など諸事情を総合的に考慮した上で判断している」、パソコンの性能や機能についても、「利用状況や費用対効果等を総合的に検討した上で判断している」とし、「今後とも、執務に支障が生じることのないよう整備に努めていきたい」としました。 |
| |
|
|
|
| |
今年度で29回目を迎えた全司法機関紙コンクールは、6月15日(火)審査が行われました。今回の応募紙は32紙でしたが、(1)機関紙を活用した組織活動を行い、個性的に豊かなとりくみをしている。(2)みんなの声や職場の実情を取り上げる機関紙が増えている。(3)見やすい機関紙づくりの努力をしている等の特徴が見られました。
審査では、「機関紙大賞」は該当なしでしたが、高知支部「龍馬」、静岡支部女性部「ちゃっきり娘」、宮崎支部女性部「日向かぼちゃ」に「最優秀賞」を授与することにしました。各部門の入賞作品は表のとおりです。
また、一昨年から機関紙を補強するとりくみとして、各支部・地連作成のホームページのコンクールを行うこととしましたが、応募のあった中部地連が優秀賞となりました。
表彰は、第67回定期大会3日目に行います。各級機関紙が、職場の実態や要求と結びついた運動の牽引車として役割発揮を期待します。
| 全司法第29回機関紙コンクール入選作品 |
| 機関紙大賞 該当なし |
| 最優秀賞 |
『龍馬』 |
高知支部 |
| 最優秀賞 |
『日向かぼちゃ』 |
宮崎支部女性部 |
| 最優秀賞 |
『ちゃっきり娘』 |
静岡支部女性部 |
| 優秀賞 |
『東京地連ニュース』 |
東京地連 |
| 優秀賞 |
『全司法中部』 |
中部地連 |
| 優秀賞 |
『全司法大阪』 |
大阪支部 |
| 努力賞 |
『日刊するが』 |
静岡支部静岡分会 |
| 努力賞 |
『いぶき』 |
高知支部女性部 |
| 特別賞 |
『城鐘』 |
宮崎分会延岡分会 |
| 特別賞 |
『てべなん』 |
札幌支部青年部 |
【ホームページ部門】
最優秀賞受賞支部の声
「日向かぼちゃ」
宮崎支部女性の教宣紙は、十八名の女性部員の皆さんに二人一組で作成していただいています。
皆さんが苦労された点として、最近は、教宣紙をパソコンで作成しているがうまくソフトを使いこなせずに、結局切り貼りをして作成していただいています。昼休みも短くなって、あっという間に時間がたってしまい、ソフトを使いこなす練習をする余裕がないのが現状です。
また、記事の内容を読んで、読みやすさを一番に考えると小見出しを考えたり、一枚の紙面に収めるが大変という意見もだされました。
工夫している点としては、女性部らしく、柔らかいイメージを心がけています。たとえば、題字を手書きにするとか、ほんのちょっとした心使いが大切だと思います。
「龍馬」
今年は『龍馬』が大ブーム、この流れの中で教宣誌『龍馬』が最優秀賞をいただくことができました。「まっこと、うれしいちや」これからもつながりを大切にできるように頑張ります。【全司法高知支部 教宣部】
「ちゃっきり娘」
最優秀賞、ありがとうございます。思わぬ朗報を聞き、非常に驚いております。こんな事を書くとあれですが、「何か特徴だったものがあったかな?」「なんか意外とすごい賞をもらったぞ」こんな思いでした。
我が静岡支部女性部教宣部は「二名体制」でスタートしました。「みんなの顔がよく見える教宣」このタイトルだけはすばらしい目標に、早くも教宣部長は満足してしまいました。それがゆえに、編集計画はた立てたものの抜けているところが多く・・・。退職者の方からは暖かいメッセージを頂き、周りの女性達からは「これ書いてみたんだけど〜」と記事をもらい、執行部からはお尻をたたかれて、今日までやってきました。
振り返ってみると、まわりの大勢のみんなの気持ちが「ちゃっきり娘」に集まっていたんだと思います。結束力は、サッカーワールドカップ日本チームに引けをとらないでしょう。未来の組合発展のためにも「勇気」と「チャレンジ精神」を持ち続けたい。
(ちゃっきり娘編集委員一同) |