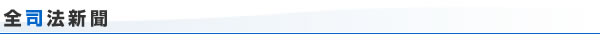 |
| |
10春闘 貧困・格差の解消、内需の拡大を
1月24・25日 全司法第70回中央委員会を開催 |
|
| |
全司法は、1月24日、25日に、神奈川県伊東市において、第70回中央委員会を、中央委員、オブザーバー、本部役員及び来賓の合計80名の出席で開催しました。春闘課題、組織課題などで議論を深め、10春闘方針等を満場一致で可決し、10春闘と組織拡大強化に向けて奮闘する決意を固め合いました。
中央委員会は、議長に大阪支部田邉中央委員、福岡支部永住中央委員を選出し始まりました。
冒頭、沖本委員長、来賓の宮垣国公労連委員長、岩波全法務委員長から挨拶がありました。
宮垣委員長は、大企業優遇から労働者保護への転換、国民的要求課題、社保庁分限問題などに触れ、運動への結集を訴えました。また、岩波委員長からは、全法務も全司法と同じく全国津々浦々に職場を持っており、各地域で、10春闘を、全司法と全法務がともに、奮闘していこうとエールが送られました。
牧山書記長の09年秋闘中間総括案、春闘方針案及び統一要求案・第2次JOプラン中間総括案の提案に引き続き、本間財政部長から中間決算報告、太田会計監査委員から監査報告があり、両報告は、満場一致で承認されました。
討論では、春闘課題、公務員制度改革課題、職場諸要求課題、組織課題などについて、のべ36名から発言がありました。
討論を受けて書記長の総括答弁の後、議案の採決が行われ、全ての議案が満場一致で可決されました。その後、社保庁職員の分限免職取消を求める決議と春闘アピールを採択しました。
各支部から推薦のあった14支部19名の組合員に対する永年組合員表彰を行い、代表して、青森支部今正則さんに表彰状が授与されました。
中央委員会は、10春闘の奮闘と組織拡大強化の決意を固め合う団結ガンバローで閉会となりました。 |
| |
 |
| |
|
|
|
| |
春闘をはじめ各種課題で深まる討論
秋闘の中間総括に関わって、「独簡の増員等の重点要求を掲げ、大衆行動、署名行動などを配置してとりくんだ結果、要求の前進があった」(大津)と職場からのとりくみを背景としたたたかいの成果が強調されました。
春闘課題に関わっては、「労働組合の真価が問われている。トヨタ総行動を成功させ、大企業の社会的責任を追及していく」(愛知)、「巨額の内部留保の一方、労働者の生活は追い詰められている。次の世代の将来も考え、官民一体となって春闘をたたかっていこう」(青森)、と10春闘での奮闘の呼びかけと決意が語られました。
労働基本権問題に関わっては、「裁判所の特性を踏まえた議論、国民的支持の必要、全司法の存在意義とそのための組織の拡大強化は不可欠」(福岡)、と今後のとりくみにとって重要な指摘がありました。また、「まだまだ職場では浸透していない。職場への情報提供が必要」(長野・神奈川)との意見がありました。
社保庁職員の分限免職問題に関わっては、「合理性のない分限処分。自分たちの問題として考えるべき。組合員の理解と納得を得ながらとりくみをすすめていくことが必要」(愛知)との発言ありました。
超勤縮減に関わっては、「昨年10月から毎月第3週が超勤ゼロ週間となった。しかし、事前の説明などが不十分で混乱した。超勤縮減は、職員の理解納得を得ながらすすめていくことが必要」(広島)、「超勤縮減や休暇取得の促進がただ働き残業に繋がるようなことがないようしなくてはならない」(千葉)、「超勤縮減は事務の効率化が不可欠。超勤をすればきちんと付けることは当然。支部の力量を高めて現場で解決できることは現場で解決していくことが組織の強化にも繋がる」(福岡)との発言ありました。
健康課題に関わっては、「健康安全懇談会の開催を追及し、数年ぶりに開催させた。当局、職場代表の外に医師も出席した。引き続き健康で働き続けられる職場環境を追求していきたい」(愛知)、「公務員の病休取得者は急増している。健康安全管理委員会の設置が必要」(大阪)、「健康診断の充実が必要」(愛知、大阪)、「メンタル不全者の職場復帰プログラムを充実させ、個々にあったプロクラムを柔軟に作るべき」(大阪・神奈川)と、健康対策の充実を求める複数の発言がありました。
家事相談の業務委託に関わっては、「家事相談の業務委託が解消された。人的手当が必要」(東京家裁・神奈川)、少年事件の審判傍聴に関わっては、「審判の傍聴が7件あった。3年後の見直しを注視したい」(神奈川)との発言がありました。
職種課題については、行(二)に関わって、「行(二)職種の将来展望を考える上でも全国行(二)集会の開催をする時期ではないか」(最高裁・福岡)との発言がありました。速記官に関わっては、「やりがいの確保のために裁判員裁判への速記官の立会を」(大津・神奈川)、「早期にステンチュラの官支給を求める」との意見が出されました。事務官に関わっては、「事務官の育成が進んでいない点がある。今後も大阪支部は、事務官運動で奮闘していく」(大阪)との決意が表明されました。
組織拡大強化に向けて固まる決意
組織課題に関わっては、のべ9名から発言がありました。
「定期大会以後、2名の未加入者の加入を実現できた。第一歩を踏み出すことが大切」「東北6支部が連携して組織拡大に頑張っていく」(青森)、「10月採用者が全員加入した。青年部が中心となり奮闘した結果。二の矢、三の矢が大切。JOプランが示している。改めてJOプランを読み込み、実践していきたい」(福岡)、「家裁分会は全員加入であるが全体としては思うように新採加入が進んでいない。同世代や職場からの呼びかけが重要。4月は青年部とも連携して創意工夫したとりくみで新採加入対策をすすめていきたい」(大阪)、「労働基本権の回復問題ををみすえた組織拡大が必要」(東京家裁・岡山)、「支部全体で組織対策を行うために組織拡大推進委員会を立ち上げた。徐々に拡大の効果が現れている」「組織強化の観点から職場会活動の充実が必要」「次世代の育成を意識して活動をすすめている」(宮崎)、「新採は地道に加入の呼びかけをして、一定の成果が出ている。12月には、未加入者も含めて新採を中心とする学習会を開催した。引き続き、複数の担当者を決めるなどJOプランを具体化してとりくみをすすめていきたい」(愛知)、「4月採用者の早期全員加入ができた。立ち上がり早くとりくんでいくことの重要性を改めて確認できた」(山口)と、組織拡大に向けた経験から導かれる教訓や決意が込められた発言がありました。 |
| |
 |
| |
|
10春闘、国民運動の一員に
要求の前進局面を作り上げよう |
|
| |
昨年8月の総選挙によって、政権が交代するという大きな政治の変化があった。この変化は、これまでの自公政権が推し進めてきた構造改革によって、格差と貧困が拡大し、国民生活が疲弊しきったことから、国民の政治を変えたいという強い思いから生まれたものである。10春闘は、国民的要求の前進の可能性が広がってきている情勢にあると捉えることができる。
10春闘の課題は、貧困・格差の解消、内需の拡大、雇用の確保という国民的要求の前進を勝ち取っていくことであり、国民の力が大きな政治的変化をもたらしたという前向きな情勢に確信を持ち、これをチャンスとして、政治を国民の方向に向かせ、財界・大企業の社会的責任を果たさせていくということにある。
そのために、学習と討論を深め、公務という枠内に留まらず、国民運動の一員となって職場や地域で旺盛なたたかいをすすめていくことが重要である。
また、社会保険庁職員の分限免職問題については、今後のとりくみに結集していくことが求められる。
組織課題に関わっては、第2次JOプラン中間総括案と第1次組合員拡大強化月間中間総括案を提示している。
同プラン中間総括案では、組織減少に歯止めを効かせられていない点を真正面から受け止めた上で、とりくみ上の課題と成果を率直に総括してある。一方、第1次月間では、例年と比べて、組織減少が縮小傾向にあるなど、一定の前進が見られる点を踏まえての総括案となっている。この二つを、相互に関連づけながら、それぞれの機関の実情とともにこれまでの4年間のとりくみと秋のとりくみを踏まえて、検討を深めていきたい。
要求の前進には、数と団結の力が最も重要であることは言うまでもない。また、労働基本権の回復を展望したとき、一歩でも組織を前進させていくことが求められる重要な局面にもきている。
二つの総括案の過不足のない総括とともに、組織の拡大強化に向けて積極的なとりくみを進めていく決意と明日から即、実践していくことが求められる。 |
| |
 |
| |
|
|
|
| |
中央委員会二日目冒頭に、柏木青年協議長から、青年の暮らし向きアンケート、新規採用者加入対策及び次年度総会と併せて開催される友好祭典の3点を中心とする青年協の活動報告がされました。
暮らし向きアンケートは、青年の生活実態をリアルに把握するもので、3月に配置している最高裁給与課長交渉において青年の生活実態等の主張の基礎となるものなど重要なとりくみであることが強調され、全支部でとりくみができるよう地連・支部への協力が要請されました。新規採用者加入対策は、各支部で新採用者加入プロジェクトチームを立ち上げるなどして、全員加入に向けたとりくみを強めていくとしました。また、次年度の総会は第20回という節目の総会であり、青年層の連帯を一層深め、組織の強化を図るために友好祭典を開催することとしており、多くの青年が参加できるよう地連・支部への協力が要請されました。 |