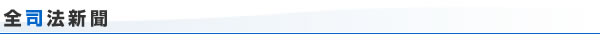 |
| |
08年度新採用のみなさんへ
WELCOME!! いい裁判所をともに作りましょう
全司法先輩からのメッセージ あなたも全司法へ |
|
| |
はじめまして、全司法です。私たちは、全国の裁判所で働く職員の労働組合です。
裁判所では、裁判官のほか、一般職員として、書記官、事務官、営繕技官、法廷警備員、家庭裁判所調査官、速記官、看護師、電話交換手、自動車運転手、守衛、庁務員などの様々な職種が、国民への司法サービスを提供しています。
全司法は、職員一人ひとりの労働条件や権利を守ることはもちろんのこと、国民に信頼される裁判所にするため、自由にものが言える「風通しの良い」職場をめざしています。
あなたも全司法に加入し、共にいい裁判所を作っていきましょう。
仲間が日々励みに
4月にはれて裁判所に入所した皆さん、おめでとうございます。…などとベテランぽく書き出すこの私、実はまだ裁判所に入って半年にもならない若輩者。ようやく仕事にも組合活動にも慣れてきたのかなあ、と思う今日この頃です。
組合活動に積極的に参加することによって、課を超えたはたまた所管を超えた仲間を得たという事実が日々励みになっています。
皆さんの新生活に、組合活動という彩りを加えてみるのもなかなかよいかもしれません。
(全司法秋田支部 T・N) |
| |
 |
| |
|
労働組合Q&A 大きなささえ労働組合
あなたの加入を待ってます |
|
| |
Q1.労働組合ってどんな組織
労働組合とは、労働者の利益を代表して、使用者と対等な立場で労働条件を決定する立場にある団体です。裁判所職員を含めて公務員も労働者であり、法律上団結権、交渉する権利は認められています(なお、争議権は制限されています。)。賃金、勤務時間、休暇、異動、宿舎、メンタルヘルス、パワハラ等労働条件や職場環境に関する様々な問題について、全司法は日々維持改善に努めています。
Q2.労働組合はなぜ必要か
今、格差と貧困が大きな問題となっています。3人に一人が非正規社員といわれています。それとともに、非正規社員のほとんどが未組織であるといわれています。その中で、ファーストフード店のアルバイトや旅行会社の添乗員が個人請負であったり、ファーストフード店の店長が名ばかり管理職であったり、意図して労働法による規制を免れるための手法が問題になっています。労働者を軽視し、人として扱わない姿勢が今問われています。使用者と対等の立場で交渉し、一人ひとりでは弱い労働者が人間らしく生活していくための権利を守るのが労働組合なのです。
Q3.困った時本当に力になってくれるの
賃金、勤務時間、休暇等法律や人事院規則等で決められる労働条件は、労働組合の加入の別なく平等に適用されます。しかし、これから裁判所で働いていく中で、困ったり、悩んだりすることがあると思います。その時、相談できるの頼もしいパートナーが労働組合です。どこの職場にも役員がおり相談することができます。また、組合に加入することで昇格、昇給等で不当に差別を受けることがないよう守られています。組合に加入しないのは、弁護人なしで刑事裁判にかけられている被告人のようなものだと思います。
Q4.労使関係はどうなってますか
1992年3月18日最高裁事務総長は「(1)全司法が、職員の勤務条件の改善のために努力されていることに対しては、敬意を表したいと思います。(2)私は、労働組合を敵視するようなことはあってはならないと考えていますし、(3)勤務条件に関する全司法の意見については謙虚に聞くべきであると考えています。(4)このような姿勢で誠実に対応する考えでおります。また、(5)特に要望があった職員(事務官、行(二))の処遇の改善、宿日直廃止、民訴法改正についての意見交換については、十分問題意識をもって受けとめたい。」と表明しています。意見が対立する部分はお互いに認めあい、尊重し合いながら、忌憚のない意見交換を行う関係が築かれています。職場で起こった労働条件にかかわる問題については、当局は、労働組合に誠実に対応することが求められています。
Q5.誰かがやってくれるものなの
自分ひとりくらい労働組合に入らなくても、他の人がやってくれるからいいのでしょうか。みんなが傍観者的な考えになってしまったら、職場はどうなるのでしょうか。労働組合は数が力です。数が減ることはその力が弱くなることです。その結果職場の要求も実現しにくくなり、今までの行使できた権利も行使しにくくなります。労働条件、職場環境は不変ではありません。時の政治情勢と当局の姿勢でいつでも変わるものなのです。数の力で日々職場を見つめているからこそ、本来の力を発揮できるのです。あまり重く考えず、「小さいことしかできませんが協力します。」という気持ちで加入していただけたらと思います。
用語解説
労働基本権
憲法第28条に定められている労働者の基本的権利です。
条文は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として、労働組合を結成する権利である団結権、使用者と対等の立場で団体交渉し、労働協約を締結する権利である団体交渉権、要求の実現をめざしてストライキなど団体行動をする権利としての争議権、これらを総称して労働基本権または労働三権といいます。
私たち公務員には、憲法の規定があるにもかかわらず、団体交渉権の一部と争議権が禁止されています。
今から60年前、アメリカの占領下であった時代に、マッカーサー司令官から政府に対し公務員の労働基本権を制限せよとの書簡が出され、その後、「政令201号」が発布され、国家公務員法が「改正」されました。
私たちは、公務員の労働基本権を全面回復すべきとして、ILO(国際労働機関ー国連の専門機関)に提訴し、私たちの主張を認めた勧告が3度にわたり出され、政府は現在、検討をせまられています。
人事院勧告制度
公務員の労働基本権が制約され、労働協約を締結することなどができないため、その不公平を緩和するため、制約の「代償措置」として第三者機関である人事院が設置され、民間と公務員の労働条件を調査し、公務員の方が低い場合には民間並に引き上げるよう、政府と国会に勧告する制度のこと。
勧告をつくるにあたっては、人事院は、使用者である政府と労働組合の双方から意見を聞き参考にしており、私たち労働組合は、賃上げなどの要求の実現のため、政府と交渉するのはもとより、人事院とも交渉し、職員の要求や意見を反映させています。
昨年は8年ぶりに青年層の賃上げが実現し、初任給が引き上げられました。 |
| |
 |
| |
|
コールセンター 職場実態をふまえて対応
3月13日 春闘要求で人事局長交渉 |
|
| |
本部は、3月13日、司法サービスの拡充と要員確保、労働基本権回復・民主的な公務員制度の確立、賃金等の改善、時短・介護のための短時間勤務の制度化、年金・退職金の給付水準維持及び4月昇格発令等にむけ、人事局長交渉を実施しました。
要員確保等
あらためて政府の定員純減方針への協力姿勢を撤回するよう求めましたが、「引き続き裁判部の充実強化を図っていくためには、定員削減に協力できるところでは協力していく必要がある」との回答に止まりました。
裁判員等選任手続におけるアウトソーシングについては、給与課長交渉での本部の追及点をふまえて、「裁判員制度に関する国民の不安や疑問等に的確に応えられるよう方策を講じていきたい」、「国民の様々な不安や疑問等に的確に答え、基本的にはコールセンターで対応が終了できるようにする」「業務委託業者と十分に連携をとりつつ、FAQの充実をはかるとともに、随時、これをアップデートしていく予定」「裁判所の担当部署にもFAQ等を情報提供する等し、裁判所における照会等の対応が混乱なく適切に行われるよう十分配慮」との回答を引き出しました。
基本権の回復
労働基本権の回復については、政府の「検討状況を見守る」との従前回答を脱しないものの、「裁判所の制度設計については、勤務条件に大きく影響する問題でもあることから誠実に対応していく」姿勢をあらためて確認しました。
また、公務員制度改革基本法案との関わりでは、「政府の検討状況を見守りながら、裁判所の組織の特殊性や職員の職務の特性をふまえて対応していきたい」との考えを示すとともに、勤務条件やこれに関連する事項については、引き続き全司法とも誠実に対応していく姿勢を示しました。
裁判所における新たな人事評価制度については、第1次試行のアンケート結果についてあらためて全面開示を求めましたが、「問題点やその対応策等については、必要に応じて説明することにしたい」との従前回答に止まりました。
賃金の改善など
賃金の改善については、「職員の生活が少しでも改善されることを常に望んでいる」としながらも、「意見を述べるべき立場にない」としています。また、初任給の改善についても、「裁判所の独自性を主張できるようなものではない」としています。賃金雇人の処遇改善等についても、「人事院等の動向についても注意していきたい」との給与課長回答の範囲に止まりました。
手当については、超過勤務・寒冷地・特地勤務・住宅の各手当について追及し、「これまでも種々の機会を捉えて、人事院に職員及び職員団体の要望等を伝える等、必要な時期に必要に応じた対応をしてきている」「今後とも同様の方針で臨んでいきたい」との考えを示しました。
その他、所定勤務時間の短縮については、「人事院の検討状況を見守るとともに、適切に対応できるよう情報収集に努めていきたい」、介護のための短時間勤務の制度化については、「職員団体の要望は人事院に伝える」姿勢を示しています。
退職金など
高齢者雇用制度等に関わり、年金・退職金等の給付水準の維持・改善を求めたことに対し、「関心の高い事項であることは十分に認識」「職員団体が同制度の見直しの問題を重視してとりくんでいることは十分理解」との認識を示したうえで、「国家公務員の退職給付は、国民の理解と納得が得られるものである必要がある」としつつも、「引き続き重大な関心を持って情報収集に努める」との姿勢を示しました。 |
| |
 |
| |
|
春闘山場越す
民間大手、昨年並み 「基本権署名」の追いあげを |
|
| |
2008年春闘は、全労連の掲げる「なくせ貧困、ストップ改憲!つくろう平和で公正な社会」のスローガンのもと、「総対話と学習、全員結集、地域共同」を合言葉に、全国津々浦々の職場・地域からのとりくみを展開してきました。
1月末には各地区・県国公主催の地域討論集会に結集し、各地における08春闘の意思統一を図りました。
2月には、全国の国公職場で要求書提出行動を配置し、職場からの上申闘争をすすめました。13日の全労連主催の中央行動には全司法青年協が結集し、銀座パレード等を繰り広げました。27日の地域総行動にも全国各地で結集し、地域春闘の一翼を担いました。
3月5日の公務労組連絡会主催の中央行動には全国上京団で結集し、人事院や財務省への要請行動等を展開しました。
本部は、最高裁給与課長・人事局長交渉で要求の前進をめざしたほか、国公労連に結集し、人事院、総務省との交渉も強化してきました。
2008年春闘は、大企業が5年連続で史上最高益を上げる一方で、「ワーキングプア」に象徴される貧困層やその劣悪な労働条件の拡大、原材料や燃料の高騰が国民生活に大きな重しとなっていたなかで、非正規雇用労働者をはじめ全ての労働者の賃金を底上げするとともに、国民生活の安定を図るあらゆるとりくみを進めていくことが求められていました。しかし、3月12日の大手企業の集中回答では、米国の景気後退や株安等を口実とした「前年並み回答」を押し返すまでには至らず、多くの組合が集中回答日以降もねばり強く交渉を継続していますが、厳しい状況が続いています。
国公労連は、3月19日に人事院、総務省との最終交渉を行い、「人勧制度の維持尊重姿勢の下、国政全般との関連を考慮しつつ適切に対処」、「(非常勤職員の実態は現在人事院が各府省から聴取しているが)政府としての必要な協力を行い、そのうえで必要な対応」(総務省)、「給与改定は、初任給を含め民間給与の実態を精確に把握した上で適切に対処」、「非常勤職員については、本年勧告時を目処としてその給与決定に係る指針を検討」(人事院)との回答を得ています。
また、所定勤務時間の短縮要求に対しては、「所定勤務時間のあり方については、所要の準備を行った上で、本年の民間給与実態調査結果もふまえ、民間準拠の原則に基づいて勤務時間の見直しに関する勧告を行いたい」(人事院)、人事評価制度については、「改正国公法の施行に向けてリハーサル試行を実施することも必要。評価結果の開示や苦情処理システムの在り方が大きな論点であると認識しており、職員団体とも十分意見交換し、理解と納得を得られるよう努める」(総務省)、「新たな人事評価制度の任用・給与への活用の在り方等は、皆さんの意見も十分に聞いて検討」(人事院)としています。
国民生活の安定を図るとりくみも一定前進しています。2月27日に全労連が開催した「労働者派遣法の抜本改正を求める院内集会」には、民主党、日本共産党、社民党からも参加がありました。労働組合の共同で労働者派遣法を改正させる条件が広がっています。
また、後期高齢者医療制度の廃止・撤回を求める運動には、裁退連も積極的に結集しており、3月5日に開催された「野党四党提出の廃止法案の成立をめざす共同緊急集会」において、全国から集約した署名を提出しています。
今後は、「公務員制度改革基本法」のとりくみが大きなヤマを迎えますが、現時点では、「ILO条約の批准について職員団体が強い関心を持っていることは十分認識」(総務省)と、極めて不十分な回答に止まっています。
本部は、3月16・17日の拡大中執会議で、「公務・公共サービス拡充署名」集約の徹底をあらためて確認しました。全ての職場・支部で署名の集約状況を確認し、最後の追い上げを図られるよう重ねて呼びかけます。 |
| |
 |
| |
|
はらはらどきどき 街へでたよ!
全司法大運動 神戸・福岡で宣伝行動
神戸22名、福岡50名が参加 |
|
| |
神戸支部
08年1月16日神戸支部は、総力を挙げて全司法大運動の街頭宣伝行動を実施しました。青年部と5分会で総勢22名の参加を得ると共に兵庫県国公の仲間の協力をも得ながら私たちは神戸第2の元町駅前で宣伝カーまで動員し堂々と国民に「裁判所の人的・物的充実の必要性」を訴えました。
最初は足早に歩く人々に訴えかけるという慣れない活動にとまどいを隠せない私たちでしたが、比較的受け取ってくれやすいビラ付きポケットティッシュを利用したこともあり、予定の1200個は僅か30分で配り終えました。
あっという間に予定個数を配り終えた私たちはまるで学園祭を無事終えた学生のようなすがすがしい笑顔で一杯でした。
殆どの参加者は生まれて初めての街頭活動だと思いますが、全司法大運動の成功という大きな目標のために一丸となってただひたすら通行人に呼びかけるうち強い連帯感も生まれました。
以下は当日貴重な体験をされた仲間の生の声です。(神戸分会A.I)
大盛況、意外に楽しかった全司法大運動の街頭宣伝行動
「初めて街頭宣伝行動に参加したので、ティッシュを配るという単純作業ですが、慣れないだけに最初はとまどいました。しかし、どのような人に渡せばよいのか工夫をするうちに取ってくれるようになり嬉しく思いました。楽しい体験をしました。(神戸家裁分会H.M)」
「慣れないティッシュとビラの配布にとまどいながらも、道行く人々に「よろしくお願いします。」と言いながら配りました。当日は寒い日で、ポケットに手をつっこんだまま、受け取ってもらえないこともあり、苦労もしましたが、良い経験をさせていただきました。(神戸分会N.K)」
福岡支部
『全司法大運動』もいよいよ終盤戦を迎えています。私たち福岡支部では今回二度にわたって街頭署名活動を行いました。福岡高地簡裁庁舎近くの「地下鉄赤坂駅」前交差点において通勤・通学帰りの人達に署名協力のお願いをしました。
第一回目は二月二二日、福岡分会の組合員を中心に実施し、総勢約三十名が集結した盛大な街頭署名活動を繰り広げることができました。集約した署名は一〇〇筆余り。
第二回目は春の陽気が一層際立って来た三月一八日。この日は、高裁分会及び家裁分会から約二〇名の組合員が参加しました。雨が降り出したこともあり、署名集約数が少なかったことが残念でした。
街頭でのビラ配りをやってみると分かりますが、なかなかビラを受け取ってはもらえません。ビラを渡そうとして拒否されるときのあの血の気が引くような感触は何とも言えません。しかし、回数を重ねるたびに『拒否されて当たり前』と心得て『拒否された段階からすべてが始まる』という境地で取り組めば、そこには喜びや楽しみさえも見いだすことができると確信しました。
これが、署名活動となりますと、実際に署名をして頂くまでには、さらに困難を要します。歩行中の人達に署名の趣旨を理解して頂くのに手間取りますし、よほど興味・関心がない限り話を聞いてもらえないのが現実です。しかし、今年は裁判員制度の実施が近づいていることもあり、立ち止まってくれる人は多かったのではないかと思います。署名をしていただきながら「公務員は天下りとかでいい思いばかりしてて、予算がそんなに必要なの?でもまあ頑張ってね。」と言われて複雑な思いも…。
今回、初めて全司法大運動推進委員として、街頭署名活動へ参加しました。街頭署名活動は、署名の集約という点では効率が良いとは言えませんが、組合員が一緒に街頭に出て、協力して行動する機会は大切ですし、一般の方々へ直接呼びかける機会となるこの活動は、今後も継続すべき重要な活動だと感じました。参加した組合員のみなさん、本当にお疲れ様でした。
福岡支部執行委員 I・K |